ヒナイチの場合
断じて、ここは巣穴ではない。
ロナルドもドラルクも、私のことをハムスターかなにかと思っているのではないか、と思うことがある。ここのことを巣穴と呼ぶこともそうだ。巣穴では、ない!
ドラルクお手製どうぶつクッキーをもそもそと口に運ぶ家主の表情は暗かった。こんなに美味しいものを食べているというのに。
「ロナルド。それで、相談というのは?」
「……うー」
一八〇センチ越えの恵まれた体型をした成人男性のうーはキツい、のが普通なのだろうが、なにせ彼は顔が良かった。甘みのある目元を潤ませてそんなことを言うな。
「あのさあ、……ヒナイチはさあ」
「うむ」
「ドラ公……、の、好きなもん、なんだと思う?」
「ちん?」
お前じゃないか? と口から出そうになって、堪えたらちんちんが出た。いや堪えたらちんちんが出るって本当になんなんだ?
「いや、ほら。クソゲーもクソ映画も、料理もさ、アイツの方が全部詳しいんだよ。そりゃ好きなんだから当然だろうけど……でもそれじゃ、俺、なにもできない」
「べつに、なにもできなくはないだろう」
クソゲーなら一緒にやるとか、クソ映画なら一緒に見るとか、料理なら食べるとか。なんならお前は全部やってるだろうと言ってやっても、ロナルドは納得しない。
「なんか、こう、……アイツが満足してくれそうなこと、なんもできねえ、俺ほんと仕事しか、……っていうか、仕事もなんなら、退治だって最近は変態とバカの相手してるばっかだしロナ戦だって締切ギリギリアウトの俺はゴミ排水溝のぬめり」
「ちんー!!」
落ち着け!
ドラルクを監視していると、四六時中となりにいるロナルドのことも実質監視しているようなものだ。そこからこのネガティブな思考についても把握はしているし、そのう……聞いてはいけないと思ったのだが……あの、あたたかな愛のことばを交わすところも、聞いてはいる。流石にプライベートすぎるので報告書にはまとめていないけれども、私にそんなことを言うあたり聞かれていることがロナルドもわかっているのかもしれない。直接こう、おめでとうとか言ってはいないが。
そうだ。このふたり、書類のうえでもしっかりと夫婦なのに。
「なんでそんなになっちゃうんだお前は。ドラルクなら毎日楽しそうだしそう報告書にもまとめている」
「お前はなにを報告してんの?」
「クッキーの味とか」
「クッキー!? せめてアイツの迷惑行動とか記録しろや!」
「それで討伐命令が出ちゃったら困るのはお前だぞ」
おぐぅ、みたいな声を出してロナルドがうなだれた。
「……あのさあ」
「うむ」
「気付いてんのかもしれないけどさあ……」
いや身内のこんな話聞きたくねえと思うけど、とぼそぼそ言われて、身内扱いに喜べばいいのかネガティブ思考を叱ればいいのかちょっと悩む。
わんこのどうぶつクッキーをもにもに弄りながら、ロナルドは言った。
「おれ、……俺さ、アイツ、ドラ公と……その、オツキアイ、を」
「ああ、そうだ。結婚おめでとう」
「ミ゛ッ」
「どうぶつクッキー!!」
バギャス!! と粉々になるわんこ。わんこーッ!!
「おま、おおおおまなん、なんで知っ、あ、エ!?」
「ああ、いや、すまない。先日ほら、ドラルクのお父上が来ただろう」
「っ、あ、のとき、いた……?」
「いた」
すごい。ロナルドの顔がりんご飴みたいに真っ赤になった。
「オア……」
「あああその手で顔を覆うな、顔面クッキーまみれになるぞ」
「ア〰︎〰︎〰︎」
言葉を失ったゴリラを宥めること数分。
なんとか落ち着き、クッキーの粉をウェットティッシュで拭って、ロナルドはうなだれている。まだ顔は赤いが、沸騰した時ほどではない。
「それで。ドラルクの喜ぶことか」
「う。ん。お前なら、アイツ監視してるから、俺が退治でいない時とかも見てるし」
なんか思いつくかと思ったんだけど、としおしおになってこちらを窺うゴリラ。
「べつに、今までどおりでいいんじゃないか?」
「うぇ……でも」
「ドラルクは欲しいものがあったらウザイくらい要求するだろう。してこないということはそういうことだ」
「俺はいらない……ってコト……!?」
「そこまで飛躍するなバカ!! ちっちゃくてかわいい謎生物かお前は」
いや、それを口に出してくれてよかったが。うっかり「そうか。わかった」とか言うだけ言って解散したら、そのまま二度とこの事務所に帰ってこないかもしれん。この男はそういう行動力があるのだ、悲しいことに。
「いらない、じゃなくて、満足しているんじゃないか。改めて要求しなくても、すでに手に入っているとか」
「んん……」
お前はもうドラルクのものだろうと暗に言ったつもりだが、しかし暗に言うと伝わらないのがこの男なのだよなあ。
「……わかんねえ」
「そもそもだが、どうしてそんなにドラルクを満足させたいんだ?」
まずはそこから探るべきかもしれない。
私の問いかけに、ロナルドはだってさあ、と口を尖らせる。
「アイツ、享楽主義の擬人化みてえなヤツじゃん。吸血鬼だけど」
「うん、まあ、そうだな」
「……今はまだ……興味あるのかもしれないけど。でも俺なんか、絶対そのうち、飽きられるから、だから、ちょっとでも、……延命というか」
「……………………………、」
これはドラルクも苦労するなあ、というのが、率直な感想だった。
底の抜けたバケツにいくら注いだところで、どんどんこぼれていくだけ。なんていうかもう、破れたというよりは製造段階で底をつけるのを忘れてしまった感じだ。ドラルクひとりで取り付けるのは重労働だろうし、多少手伝ってもバチは当たるまい。
「……結婚したんだろう?」
「うッ、……ん。でもそんなん、破棄できるし」
「転化の誘いくらい受けたんじゃないか?」
「あ、……なんで知ってんだ!?」
「そうなのか。良かったな」
「でも、でもよ。俺がもし吸血鬼になってさ、でもアイツが飽きたら、そしたら俺、ずっとひとりで生きてかなきゃなんねえ。それは怖いから、だから、断るつもりで」
「……ロナルド」
飽きたら、と繰り返し言うからには、今現在のドラルクの気持ちは受け入れられているのか。五平方センチメートルくらいは底ができてるかもしれない。なんとかそこにドラルクの砂が引っかかってる感じ。
「……断ったら、そこで居なくなっちまう、かな」
「そんなことはないと思うぞ。死ぬまで一緒にいて、看取ってくれるだろ」
「死ぬまで……まあ、長生きしないだろうしな。それくらいなら飽きないかなあ」
「一〇〇まで生きる気概を持て」
ハハハ、とか笑うんじゃない。
「……ほんとはさ、」
「?」
「信じてやれない俺は、ひどいヤツだってわかってんだよ」
だから、と。
「そんな俺に、……俺を、アイツに押し付けたくないのに。俺なんかやめろってさあ、言うべきで、なのに、俺、――うれしくて、」
はなれてほしくない。
吸い込まれそうなほどきれいなひとみから、ついに涙がこぼれ落ちた。
「わるい、ヒナイチに、こんな話して、おれ、困らせたいわけじゃなくて、」
「ああ、ああ。わかってる、安心しろ、ほら」
かわいい私の弟だ。泣かれてしまうと困る。隣に寄り、もふもふの銀髪を胸に抱きこんで背中を撫でてやって。
「深呼吸しろ、私はここにいるぞ。ドラルクだって、上でお前を待ってる」
「うん……」
たぶん、この会話を必死になって聞いているのだ。
「ドラルクのこと、好きなんだろう」
「ヴェ、……ん」
「なら、大丈夫だ。それを伝えてやるだけでいいさ」
「……むり、だ。恥ずかしくて殺しちまう」
「言おうとはしてるのか?」
「……、」
こく、と頷かれて、もふもふ頭がくすぐったい。
お前が引け目に感じることなど、なにもないのだ。
「大丈夫だ、私が保証する。だからほら、泣き止んで、ドラルクのもとに帰ってやれ。お前を待っててくれるよ、ジョンたちだってそうだ」
「……、ごめん……」
「そういう時はありがとうと言うんだぞ」
「あり、がと……」
さ、そろそろ我慢が効かなくなる頃だろう。
コンコンコン、という三つのノック音に、腕のなかのデカい身体がびくりと跳ねる。
『ヒナイチ君、いるかい? シフォンケーキが焼き上がったんだけれど』
「いただくぞ!」
「ッ」
強張った背中を撫でてやりながら、私は声を張り上げた。
「ロナルドもいる、食べるそうだ!」
「あっあっ……!?」
『なんだ、居ないと思ったらレディーの部屋に上がり込んでいたのかね。仕方がないからゴリラの分も用意してやろう、光栄に思えよ』
「……、ほら。いつも通りだ」
「は、……はは。ん、ありがとな、ヒナイチ。ていうかお前、クッキー食べた後にシフォンケーキ食うの?」
「ドラルクのおやつは無限に食べられるからな!」
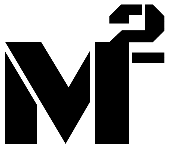

コメント