殺される直前見た顔は、真っ赤に染まっていた。
「ふっ……ざけんな! テメッ……」
「さて! そうと決まれば善は急げだな。ジョン、案内してくれる?」
「ヌン!」
記憶のない不愉快さなんて、もう忘れてしまっている。だって自分は、どうやらとても楽しい日々を過ごしていたみたいじゃないか!
「お父様も、ご足労頂いて申し訳ないのですが。そういうことですので」
「どーいうことだよッ」
「うん、うん! ポール、ドラルクは任せたからな」
「ちょ、待――」
ばさり、と羽音を立てて、お父様は窓から飛び出して行った。もちろん、ここに私が残るためである。お父様が残っていると、私が帰る選択肢が残ってしまうから。
「おま、え。さっきの、」
「うん?」
男――いや、ロナルド君。彼はわなわなとくちびるを震わせて、私を見つめている。
「かわいいねェ」
「はァ!?」
ふら、と後ずさる彼を追いかけたくなったけど、ジョンにマントを引っ張られた。
「イヌヌルヌヌ、ヌヌヌイ」
「ふふ、うん。そうだね」
ジョンを救いの神みたいに見ているロナルド君。そういえば彼、マジロ語わかるんだねえ。それだけの間一緒にいたのだろう。
脈無しではない、そういう確信があるのだ。
私との暮らしを、彼は夢だと言った。
夢のような日々を、失わせてたまるものか。
「君も案内してくれたまえ」
「……さっきも、言ったろ。俺、お前の荷物とかよくわかんねえよ」
「そうなの? 本当に?」
彼はこくりと頷いて、ようやく私を見た。
「キッチンは、入ると怒られたし……ゲームはよくわかんねえし。えっと、予備室にお前の配信に使ってたパソコンが……、」
そこまで言って、は、と彼が息を呑む。
「どうしたの?」
「ッ、あ、いや……! パソコンはまあ、あとでいいだろ。とりあえず、キッチンは見たらわかるか?」
「……んー。いや、配信って結構スケジュール立てたりするからね。すっぽかしたりしたくないし、配信環境は確認したいかな」
「え、あ、う……、」
んふふふふ。なんだろうね、なにがあるんだろうねー!
ぼぼぼぼぼ、って一気に真っ赤になっちゃって、かわいいったらないじゃない。
「さあ、案内しておくれ?」
「……わ、かった……」
さっきみたいに殴り殺せばいいのに、そうしないんだ。ジョンをちらりと彼が見る。無言でジョンが親指を立てるから、うええ、と彼は項垂れた。
なにがあるのかね。ゆっくり、行きたくないです、って主張する背中を追いかける。
おや? ジョンは来ないのか。
「まっすぐ、洗面所で……こっち、風呂と、トイレな。……で、予備室」
「ていうか、なんで予備室なの?」
「お前が来るまでは予備だったんだよ。その頃の流れでなんとなく呼んでる」
「ふーん。おっ邪魔っしま〜す」
「あ゛ッ、」
ひょい、と部屋に飛び込む。
確かに、私の配信用と思われるパソコン群。ちょっと買い換えたのかマイクが違うな。オーディオインターフェースは変えてないのか。ふむふむ。
そして、雑に置かれたマットレス。
「……君が後ろで寝てる状態で配信してたの、私?」
「いや、……これは、その、……」
ふるふる、と首を振って、彼は言った。
「おれ、は、リビングで寝てる。これは……」
「これは?」
「え、」
ずい、と顔を寄せてみると、彼は泣きそうに目元をゆがめた。
「……えっち、する、……とき、に……ひろげて、そのまま……」
「へえ。君が? 誰と?」
「ッ、……ぅ、ぐ」
私と、だったりする?
「……ぉ……まえ、……と……」
口角が上がって、牙が疼いた。
ふらふら後ずさる彼を、今度こそ追いかける。狭い予備室ではすぐに壁へぶつかってしまい、彼はぎゅうと拳を握ったけれど。それを私に振るうことはないのだね。
拳をやさしく撫でてやるけれど、ほどけない。
「なんだね。私たち、お付き合いしてたんだ。もしかして、あのお父様の感じからしてうちの一族公認? もう、最初からそう言ってくれればよかったのにさ」
「ち、がう……そういうの、じゃ、ない」
「そうなの? えっちはするのに?」
「……べつに、お前は、俺のことなんか好きじゃなかった」
「へえ」
そうなのかな。
私は完璧に一目惚れしたけど、『私』は違ったのかしら。
「なのに、えっちはしたんだ」
「……、なんだよ。尻軽とでも、なんとでも言えよ……」
「言わないよ……え? 私以外ともここでしてるの?」
ていうか、君が下なんだ。まあそりゃそうか、私ちんちんなんかいれられたら死ぬだろうしな。
彼は面食らってかぶりを振る。
「ッしてない、……けど」
「じゃあべつに尻軽とは言わなくない?」
同意を求めてはみたけど、彼に応える余裕はなさそうだ。透き通るようなひとみをうろうろ彷徨わせて、大きな身体を所在なさげに縮こませている。
迷子の子犬をいじめているみたいな気分になるなあ。
「ロナルド君」
「……んだよ」
「君のことを好きじゃないのに手を出すような『私』より、君のことを好きだから我慢できる私にしない?」
「――……、え?」
ぱ、と身体を離して、両手をあげる。なんにもしないアピールだ。
彼はてっきり抱かれると思ったのだろうな。拍子抜けと安心がフィフティ・フィフティって顔をして、ぽかんとこちらを見ていた。
「え、……なに?」
「ほら、私にとっては出会ってまだ一日も経ってないし、君の同意も得られてないし。無理矢理とか可哀想とかってダメなんだよねえ」
「……、お前、なにがしたいんだ」
ずるずる床に座り込んだ彼が、上目遣いにそう言う。うわー、顔面の破壊力すっごいじゃん。時代が違えば、一族総出で囲ってしまっていただろうな。
「そりゃもちろん、君としあわせになりたいのさ」
微笑みかけると、彼は驚愕をあらわにした。
「じゃ、次はキッチン見せて!」
はてさて。
一週間、二週間。私の記憶は戻らないまま、時間だけが過ぎていく。
「好きだよ、ロナルド君」
「……、おう」
彼がそう応えてくれるようになったのは、割と早い段階だった。また言ってるよこいつ、みたいな目はいただけないけど、とりあえず届いてはいるみたいだね。
彼について、わかったこと。
短気で粗雑かと思えば、ありえないほどやさしい。親切とも言うのかな? 献身が服を着て歩いているみたいだな、とさえ思う。退治人はおそらく天職だ。
ジョン、メビヤツ、キンデメ、死のゲーム。私以外の同居人たちは、私たちの関係を知っていたという。恋人同士。どうも、ロナルド君だけが、私が彼を好きじゃないと思っていたらしいのだ。
その原因と思われる、自己肯定感の異様な低さ。
二言目には、「俺なんか」だ。次にそれ言ったらキスして黙らせるからね、と言ったところ、「俺な、」で止まるようになった。かわいいね。アウトだけど頑張ってるから許してあげています。
だから私たち、キスもまだなんだよね。
あーあ、『私』は彼とどんなキスをしたんだろう。うらやましいなあ。けれども、『私』は彼を好きだったわけではないと彼が言う。あんまりやさしくしていなかったのかなあ。私なら彼の気持ちいいことしかしたくないし、しないのになあ。
私にしなよ、ロナルド君。
決まり文句になったそれは、「ごめん」の一言で切り捨てられてしまう。
「俺、『アイツ』のこと、好きだったから」
そう言って、彼は操を立てるのだ。
彼のことを好きじゃなかった『私』に。
「今日も美味かった」
「そう、良かった」
彼の好きな味付けはすぐにマスターした。美味しそうに頬張る彼をみると、ざまあみやがれと思うのだ。私にだってできる。『私』ができるのだから当たり前に。
「お前、そろそろ飽きねえの」
「ん? 料理なんて何年やってると」
「じゃなくて。……その、すきとか、自分にしろとか」
「飽きるわけないでしょ。好きに関しては君が認めてくれても言い続けるからね」
「……、そっか」
「そうとも」
だから折れてくれればいいのに。
「お前、さ」
「うん?」
「やっぱりあん時、親父さんとこに帰るべきだったんだよ。今からでも、べつに遅くないだろ」
マグカップを見つめながら、彼は言う。
「……結局まだ、爺さんにも声かけてないんだろ。普通に毎日暮らしてるだけじゃ、たぶん解決しねえと思う、から」
「まあ、それはそうだけどねえ。正直な話、記憶はべつに戻らなくてもいいかなって思ってるんだよね」
「……なんで」
「あ、君との暮らしを思い出したくないとかじゃないからな!?」
慌てて否定する。がばりと身を乗り出すと彼はたじろいで、けれど頷いた。
「でも、だってさ。君のことを傷付けてた私に戻りたくないっていうか」
「へ」
「そうでしょ、君が愛されてないって思っちゃうくらい、私冷たかったんでしょ?」
「あ、……いや、そういうわけじゃ、ないけど……」
「けど?」
「ただ……おかしいだろ。お前はともかく、『アイツ』にとって、俺は誤解で殺して、自分の城壊して、そのあともずっと殺し続けて、さ。そんなのを好きになるなんて、ありえないだろ。だから……」
「だから、揶揄われてるとか、そういうふうに思っちゃったの?」
がく、と項垂れたのか、それとも頷いたのか。首が痛そうなほど下を向いている。私だったら死んじゃいそう。
「ロナルド君。顔をあげておくれよ」
「おれ、……俺がだめなやつなの、二週間も見てたらわかるだろ。お前だってもう、幻滅した頃じゃねえの」
「しないよ。見目も中身も能力もいいんだから、ちょっとくらいだめなところがあるのはむしろかわいいと思うけどな」
「なんで……、」
彼はそこで一度言葉を区切って、
「なんで、『アイツ』と、おなじこと言うんだ」
「……そりゃあ、『私』だからじゃない?」
思考回路はおんなじだもの。
彼がゆっくり顔をあげる。潤んでしまった蒼天のひとみ。
「ごめん、ロナルド君。キスさせて。いやなら殺して」
「……、」
ああ、だめだよ。ひとみを隠してしまったら、それは受け入れているのとおんなじ。
くちびるを触れ合わせた瞬間、こめかみを激痛が突き刺した。
くちづけの記憶

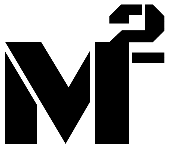
コメント