ずきり、とこめかみが痛んで目が覚める。痛み、というものをだいたい認識する前に私は死んでしまうから、それはとても珍しいことだった。
「……?」
見慣れない天井。
そもそも、眠っている場所が棺桶ではない。安っぽいソファに寝かされていたらしく、腰に違和感を覚えた瞬間死んだ。うん、まあ、これが正しい私なのよね。
「ヌァ!?」
「ジョン? ……あ」
いとしいジョンの悲鳴、と、耳慣れない男の声。
耳慣れないはずなのに、掠れたそれはやたら心地よく感じた。なぜだろう、と首を傾げようとして、再生していないことに気付く。ぽすぽすと柔らかい肉球が当たるから、きっとジョンが私の砂をかき集めてくれているのだな。
「ドラ公? なんで再生しねえんだ。いやていうかなんで死んでんだ」
「は?」
なんだドラ公って。思わずガラの悪い反応をしてしまうけれど、見知らぬ男に変なあだ名で呼ばれたらそんな反応にもなるだろう。そう思いながら再生する、と。
目を奪われた。
私たちを灼く銀の髪。同じく銀の睫毛に守られた目元は甘く垂れていて、ひとみは碧くひかっている。通った鼻筋、やわらかそうなくちびるがすこし不満げにむくれている、だというのにそのうつくしさを損なうことはないのだ。
「なあ、大丈夫かよ。お前が死なないで気を失うとか、絶対おかしいのはわかってんだ。……やっぱり爺さん呼んだほうがいい?」
「なん、……なんだって?」
待て待て待て。
私が死なず、気を失った?
それもだいぶおかしいが。爺さん呼んだほうがいいか、と聞かれた。爺さん。おじいさま――御真祖様を知っている?
くたびれた赤いジャージの、この男が?
「……お前は、何者だ?」
「は」
「ヌェ……!?」
え。
ジョンが、驚いている。顎が外れそうなほどあんぐりと口を開けて。その顔に気を取られて、肝心の男がどういう表情をしていたのか、確認することはできなかった。
「……、あー。まあ、なんだ。えっと、どこまでわかる? ジョンは?」
「ジョンを忘れるわけがあるか。なぜ人間が私のジョンを馴れ馴れしく呼ぶんだ」
「うん、ならいいや」
「ヌ!? ヌヌヌ!?」
ジョンの叫びに同意するも、無視される。男は勝手になにか納得した様子で、スマホを取り出した。電話をかけたらしく耳に当て、誰かに向かって話し出す。
「親父さん? 俺だよ俺。あ? うるせえな。今栃木の城? おー。じゃよろしく」
「は? 親父さんって、」
「お前の親父さんだけど」
「なんで!?」
なんでかあ、と男は肩をすくめた。だいたい今の会話でなにが伝わったんだ。なにをよろしくしたんだお前は。
「すぐ来るってよ。そしたら説明して、お前を連れて帰ってもらう。そのほうが、得体のしれない人間の家にいるよりいいだろ、どらこ……、ドラルクも」
「ヌヌヌヌ! ヌッヌイッヌヌ……」
「ジョン」
俺は大丈夫だよ。いまはお前のご主人さまだろ。
そう言ってジョンを撫でる手つきを見れば、わかった。この男は本当に、ジョンを大切にしてくれていたのだと。好奇心から触れているのではなく、ジョンがどう触れられたら心地よいのか、理解している手つき。
ずっと一緒に、と、ジョンは言いかけた。
この男と、私たちが、ずっと一緒に?
「安心しろよ。お前と違って親父さんも爺さんもすげー吸血鬼なんだし」
「はァ!? なんでお前にそんなこと言われなきゃなら――」
「ヌヌヌヌヌヌ!」
がば、とジョンが飛び込んで、私の顔を覆う。もふもふの腹毛は気持ちいいが、いまはそうじゃないだろう。ヌンヌン言いながら頭を叩いてくるジョンを剥がす、と。
なぜだろう。おそらく、私はきっと。
この表情を、絶対に、見たくなかったのだ。
「大丈夫。ゆめがさめるだけだから」
くちづけの記憶

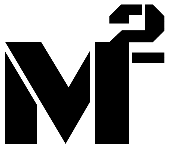
コメント