「ッロナルド君!」
「いやだわ。あんな泥棒猫より、わたくしのほうが大事でしょう?」
「……リヴィアナ」
不愉快だ。
むに、胸を押し当てられるのも、媚びた視線も。彼女がこの態度になってから、もうどれだけ経つのだろうか。毎回きっぱりと断っているにも関わらず、彼女は相も変わらず自分を私の婚約者だと思い込んでいるらしい。
そんなことよりも、だ!
「リヴィアナ。よくも私の愛おしい昼の子に、あんな顔をさせてくれたな」
「ふふ。なにを言ってらっしゃるのかしら? まあ、そうですわね、愛人は、愛する人間と書きますものねえ?」
愛してらっしゃるのねえ。そう嘯く彼女は、なにもわかっちゃいないのだ。
「そうだとも。君のことはこれっぽっちも愛しちゃいないが、彼のことは本気なものでね。わかったら離してくれるかい」
「まあ、まあ! ドラルク様ったら。どうしてそんなにひどいことを仰るのかしら。いつもいつも、わたくしは胸を痛めておりますのに……」
しなだれかかってくるな! アッ無理。
砂になった私を、まあ、なんて驚いたふりをしながら両手で抱えるリヴィアナ。やめろ、一部を持ち上げるな、復活できないだろうが!
うぞうぞと砂を動かしてその両手から逃げる。シルクの手袋はサラサラとしていて、逃げ出すのは容易かった。ぎゅうと握られようとも、特に問題はない。
「んもう。逃げないで」
「逃げるに決まっているだろう。私は彼を追いかけなければならないのだ」
「あっ、ドラルク様!」
居住スペースの扉を開けて、ロナルド君、と呼ぶけれど。
ソファあたりにいるだろう。そう思ったが、赤い外套は見当たらない。
「……、ロナルド君……?」
『……ぐぷ。……退治人なら、ドーナッツを買いにいくと出かけていったぞ』
「ハァ!? なんで!?」
ちょっと待って本当になんで???
『ジョンが退治人を好きだ、と。喜んだ退治人が、褒美にドーナッツを買い与えるらしい……詳しく聞いていたわけではないが』
「エッ本当にわからん。なにがどうしてそうなったんだ」
ていうか若造見なかったんですけど、どっから出ていったんだ?
『靴を抱えて洗面の方に向かったから、バルコニーから飛び降りるでもしたのでは』
「あのおバカーッ!!」
「ドラルク様?」
いやまああのゴリラが着地に失敗するわけないだろうけどもー!
髪が乱れるなんて気にせず、わしわし頭をかきむしる。諸悪の元凶――リヴィアナはきょとんとして、なにもわからないという顔をした。
「どうしましたの? 私よりも大事なことがありまして?」
「ああ、まったく! 君より何倍も大事だが!?」
ううううむ。
どこのドーナッツ屋かはわかる。若造とジョンの気に入りの店があるのだ。わかるが、いまから追いかけても……すれ違いになりそうだぞ。どうしようか。
――悪い。
そう言った、彼の顔が頭から離れないのだ。
普段はきりりと釣り上がっているはずの眉が、へにゃりと曲がって、下がって。
なのに、微笑みを湛えた口元。
ぼんやりと、私のことも彼女のことも、映さない瞳が。
きっと、彼は、もう二度と。私にあの蕩けた笑顔を見せてくれないと、わかってしまう。ふにゃふにゃと蕩けきって、私に信頼を寄せてくれているような、あの。
想いを耳元で囁いたときの、心の底からうれしい、というような、あの。
――ふ、へへ。どらこー。俺も……。
俺も、どうなのか。最後まで、彼は確実なことばをくれなかった。あとはそのひとことを、引き出すところまで来ていたのに!
「……ドーナッツを食べてくるなら、食事を用意するのは悪手か……? クソ、どうしたらいい、どうしたらあの子を、私は……」
『落ち着け。まずはその女性を処理したほうがよいのでは……居る間に退治人が戻るほうが面倒なことになりそうだぞ』
「まあ! 処理だなんて人聞きが悪いですわねえ。金魚の同胞なんて、また妙なものと暮らしているようですけれど。こんなものたちより、わたくしのほうが――」
「リヴィアナ」
『……、』
わあ。
キンデメさんの冷たい目線、初めて見たかも。彼ってロナルド君に似て、なんだかんだで優しいところがあるのにねえ。世界征服なんてすっかり忘れて、ロナルド君をいつも心配している優しい金魚が、まぶたもないひとみで彼女を睨みつけていた。
「……、発言の自由は君にある。けれど、責任も君にある、というのはわかるかね」
「――……ええ、まあ。でもわたくし、事実しか」
「ならば。君には責任を取ってもらおう」
靴を脱ぎ、クローゼットを目指す。何も知らずに着いてくる彼女は無視して、彼の退治道具が詰め込まれているスペースへ手を伸ばした。麻酔弾の箱、ではなく。その横の、銀の弾丸が詰められた箱を手に取り、くるりと振り返る。おのれに視線が向いたと勘違いした彼女は、嬉しそうに両手を合わせた。
「まあ! 贈り物ですか……、ッ」
「ああ、君に贈ろう。ただし、高いからひとつだけだがね」
彼女が言い終わる前に箱を開ければ、ひく、と流石の彼女もたじろいだ。予備の銃もあることだ、本来の役目として撃ち出すこともできるけれど。貫通して壁に跡を残すのもいやだし、なにより、彼の銃で撃たれて死ぬなんて、彼女のようなものには勿体のないことだろう?
なにより、塵のなかから回収すれば、消費したことにもならないしね。
「飲み込みたまえよ。……ああ、君も吸血鬼だからな、つまみあげることさえできないか。ふむ、菜箸でも使うかね?」
「え、あ、……ドラルク……さま?」
私の過去一番の拒絶に、ようやく彼女も現状を理解し始めたようである。
というか、まあ。さんざ拒絶自体はしてきたけれど、こういう確実でわかりやすい方法を取らなかった私がもっとも悪いのだ。それはそれとして、何度説明されても理解を示さなかった彼女には、それなりの報いを受けてもらう必要がある。
「私が菜箸を取ってこよう。箱を持っていてくれるかな?」
「あ、……あ、? ドラルクさま、ご冗談を……」
「冗談? まさか」
ふ、と笑い飛ばす。差し出した箱から後ずさる彼女を、ゆっくりと追い詰めた。
「さあ。箱を持って?」
「――〰︎〰︎〰︎ッッッ!!」
とす、と背が壁に当たって。
ついに彼女は逃げ出した。土足のまま上がり込んでいた彼女は、律儀にもちゃんと事務所の出入り口から出て行ったようである。半田君式逃亡されなくてよかったあ。
ばたばたと慌ただしい足音を追うことなく、重たい箱をクローゼットに戻す。
「あー、重みで死ぬかと思った」
『ぐぷぷ。よい演技だったぞ』
「んふふ、大根の若造とは違うのだ」
はーやれやれ。
「というわけでキンデメさん。若造のケアどうしたらいいか会議をします」
『今回ばかりは任された』
「なんて?」
「ウアーッ!?」
私はビックリ死を決め、キンデメさんは昇り竜になった。
ひょこ、と。
振り返れば、ジョンとドーナッツの箱を抱えた若造が、いる! 首を傾げたその顔は、まったくもっていつもどおりの彼でしかなくて。それが逆に、違和感をもたらす。
「ロナルド君、」
「なあドラ公、嫁さんが泣きながら走ってったけど。どうせお前なんか酷いこと言ったんだろ? 謝んなきゃダメだぞ。電話とかしとけよ」
「は」
嫁さん。
嫁さんって誰!?
私にジョンを返却して、ロナルド君はキッチンに向かう。ドーナッツをパン類と一緒にしてから、クローゼットに向かい衣装を脱ぎ出した。今日はもう休業、ということなのだろうか。
「――いや、いや! 結婚してないからアレは嫁じゃないし、そもそも婚約者なんてのも彼女が勝手に言ってることだから!」
「……みたいなこと言って怒らせたんだな? かわいそうだろ、そんなの」
「違うって、ロナルド君、私は」
「ドラ公」
すっかり、いつものジャージに身を包んだ彼は。
「わかってる、から。大丈夫。もう恋愛映画なんか見ないよ」
そう言って、私に向かって微笑んだ。
「でも、ちゃんと否定しておけよな。愛人じゃなくて、ただのセフレだ、ってさ」
すべてを、諦めた、顔で。
「そんで、もう、もう二度と寝ないって。ちゃんとはっきり言ってやってさ、安心させてあげないとダメだぜ。吸血鬼の夫婦は、永いあいだ一緒なんだろ」
待て。
「ちょっと、待て……」
「あ?」
いま彼は、なんと?
「私と、君が。なんと?」
「え? ……セフレ、だろ?」
セフレ。
セックスフレンド!?
「はああああああああああああああああッッッ!!!???」
「ウワッビックリした!」
大声をあげすぎて死んだ。
いやいやいやいやいやいやいや超真剣交際だが!?
あまりのショックに復活できず、うごうごと砂のまま蠢いて、私は叫ぶ。
「なん、なんで!? いつ誰が私と君をセフレだなんてひどいこと言った!」
「え、言ったっていうか……べつにお前、俺のことすきでもなんでもないじゃん」
「ハァ!?」
「すき同士じゃないんだから、別に恋人でも愛人でもないだろ」
「ハァー!!!???」
エッ言いましたけど!
セックスしてる時ひたすらずっとかわいいと好きを連呼してましたけどォ!?
なんとか復活しながらそう突き付けても、彼は首を傾げるだけだ。
「雰囲気づくりだろ? たしかに俺はお前によく騙されるけどさ、そんな大事なことまで勘違いしたりしねえよ。だいたい、本気にしたら迷惑だろ、お前もあの人も」
「迷惑なワケないだろうがあ!! 全部。全部だ。セックスのときに君にかけた言葉で、嘘なんかひとつもないわ!!」
「え、じゃあお前、ひどいやつだな。俺、ほんとに愛人だったのか。そうならそうって言えよ、あの人にやっぱり謝らないと」
「違ァうッ!!」
ロナルド君に詰め寄る。彼女と違って、彼は逃げなかった。わけがわからないという顔をして、お前なんか変だぞ、とかのたまっている。その肩を掴み。
「私は! 君と! お付き合いをしているつもりだったんだが!?」
「……、……………………………………………………………え?」
至近距離でそう伝えれば、蒼天のひとみがまたたいた。視線を逸らされそうになったので、顎を捉えて捕まえる。ああ、これはキスをするときのしぐさだな、と思ったが。いまはまだ、まだだろう。
「君が、私を受け入れてくれたあの日に。君が抵抗しないで、身体を委ねてくれたあの日に! 想いが通じたのだと思った。好きだと言ったら、君がうれしそうに微笑んでくれるから。俺も、と――そのさきをいつ言葉にしてくれるのかと、期待して」
「う、ぇ? え、でも……」
「君がラブストーリーを持ち込んだとき、私がどんなに嬉しかったかわかるかい。二回目をいつお願いしようか、君は純情ゴリラだからな、ブエー殺すな! とにかく、悩んでいたのだ、君にどうしたらスマートな二回目をお願いできるのか。そうしたら、君から映画に誘われて、しかもラブストーリーだった! まさか同じ方法をとってくれるなんて、思っていなかったからね。うれしくて、まだ二回目なのにずいぶん激しくしてしまった。あのときはごめんね、流石の君も翌日つらそうだったしな」
「べ、べつに、俺は強いし、」
「いまそういう話じゃないんだよ。とにかく、とにかくだ! 私は君が好きだ。愛している。あんな勘違い女のために君が身を引く必要なんかどこにもない!」
「あ、ぁ、ぁぅ……?」
『同胞よ。退治人がキャパオーバーのようだが』
む。
見事なまでに真っ赤っかな、茹で上がりゴリラが目の前にいた。
牙が疼く。
「――かわいいね」
「っひ、ぅ」
「かわいいよ、ロナルド君。……ねえ、どうして、私が君を好きじゃないなんて、そんなふうに思ってしまったの。私がセックスのときにしかそういうことを言えない、意気地なしだからかな。君が不安だったことに気付けなくて、本当にすまない」
「え、や、あ」
「好きだよ、ロナルド君。キスをしても?」
「だ、だめ」
「どうして?」
ゆらゆらと左右にさまよった挙句、ひとみはまぶたに隠されてしまった。いやだなあ、もったいないなあ。見せてほしいなあ、と目元をゆっくり撫でてみたり。
「え……あ、だって、」
「うん」
「ジョ、ンも、キンデメも、死のゲームも……見てる……から、」
「恥ずかしい? じゃあ、予備室行こうか」
「うぇ、」
あー! ここで彼をお姫様抱っこして連行できるイケメンマッチョになりたい。実際イケメンマッチョなのは彼のほうなのだなあ。ぐぬう。悔しさをバネに彼の手を引くと、ビクともしなさそうなそれは案外するりと動いてくれた。
予備室まで、無言。先に彼を入れてしまって、後ろ手に鍵を閉め。
「ロナルドくん」
「ッ、ぅ……」
「こっち向いて。キスをしよう? 恋人のキスをしようね、ロナルド君」
「どら、こ……」
ああ。
だめだよ、ロナルド君。そんな、期待に潤んで蕩けたひとみをしたら。
「……その顔、私以外に絶対見せるなよ」
「へ、ぁ、んむッ!?」
ちゅ、ちゅ、と何度も触れ合わせる。それじゃあもちろん足りないのでずるりと舌を差し込んだ。大きな身体をびくりと震わせ、だけど抵抗しない彼は。
「んぇ、♡ はむ、ぅーっ……♡ ンん、ッ♡」
「は、ふ。……ロナルドくん……」
「ぁ、や、まて、待てって、どらこ、」
いちど息継ぎさせてあげてもう一度、今度はもっと深く。そう思ったのに、ぱし、とその大きくてあたたかい手のひらで拒まれてしまった。
「ろあうおうん?」
「ひっ! ……あの、あのな、なんか、だめだから……」
「……、なにがだね」
「えっと、……その……、」
ううう、と唸るゴリラ。急かさずに、辛抱強く彼が口を開くのを待った。あやすように頭を撫でてやれば、気持ちよさそうに懐いてくるのがたまらない。
「こ……恋人、の、ちゅー、……なんか、きもちよすぎて……俺、へんになりそうだから……、だめ……だと、思う……」
「…………………………、ごめん」
「へ、」
「このまま恋人セックスもしよルド君」
「え!? あ、ちょ、やッ♡ ひゃ、ま、ってぇ……!」
「待てない。ごめんね、後で殺して、今は殺さないで」
「あッばか、バカ! どこ触っ、ひぇ、あ……ッ♡」
紛うことなきラブストーリー

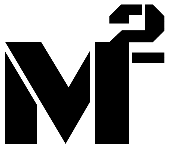
コメント
わぁぁー!リクエストされた方へのイラスト拝見いたしました!!最高にかわいくて大好きです!!!もー!すきです!かいてくださった柗村様もリクエストしてくださった方も、ありがとうございました。
オ! ありがとうございます〜🙌