2
まるまると大きいスイカを買う、なんつうのは、『ロナルド様』としちゃあできねえ話だ。
というわけで、ネットスーパーしてみた。
「おお……」
ノコ……、かぼ……、と、かわいいものたちも若干引いている。まあちょっと、なあ。ほらまあ、通販だとさ、いまいちサイズがわかんねえっつうかさ。センチ表示に現実味がねえっていうかさあ。
……俺の家の包丁でこんなモンが切れるのか?
「……まあ、やってみるか」
ナイフや剣なら使えるのだ。リンゴの皮をくるくる剥くやつはできなくても、ただ何等分だかにスイカを分けることはできる。できるはずだろう。
ドラルクはただの果物を出さない。
飾り切りとかならまだしも、なにかしらの加工がされちまうのだ。なにを勘違いしているのか、あれが作る料理はどっかのディナーとか、コース料理とか、そういう感じのやつが多い。パトロン気取りのキモいおっさんに連れて行かれるヤツよりか一〇〇倍うまいさ。うまいが、そうじゃねえ、となるときも正直な話、あるのだ。
たとえば、ただスイカを切り分けただけのヤツ、だとか。
結論から言えば、スイカの解体だけならやってやれないことはなかった。やや段ができたところもあるが、そもそも包丁の長さが足りなかっただけだから、俺の技術がどうこうという話ではない。……ないよな? スイカがデカいのか、包丁が小せえのか……一般的なサイズがどちらもわからない俺には、判別がつかねえんだけどさ。
うーん。半円状のやつに噛みつくこそスイカを食べている感じがする気もするが……ツチノコやかぼちゃには大きすぎるか。
一口大に切り分けようとして、事件が起きた。
「あ、こら、ノコ!」
食いしん坊のツチノコが、ひとつのカケラを丸呑みしたのだ。いや、予想はついていたが、マジで呑み込むと思っていなかった。種も皮もなにも気にせずに、ぺろりと呑み込まれてしまう哀れなスイカ。
うーん。包丁を持っている状態で、ツチノコと攻防したくはない。
なので、ペットキャリー閉じ込めの刑に処す。ツチノコも所詮は蛇だから、呑み込めないモノに太刀打ちできないのである。どんなに顎を外したところで、四方八方を囲まれちゃあ手も足も出ない。手も足もないが。
ノコノコと不満を漏らす声には耳を傾けずに、のこりのスイカを切り分けていく。うん、まあ。いい感じに、夏の風物詩っぽい雰囲気が出た。
このままふたりに渡してもいいんだが……もうひと手間かけてやりたいところがある。
繰り返すが、手も足もないのだ。ツチノコにもないし、かぼちゃにもない。それがわかっていて、種を丸呑みさせる訳にはいかない……たとえ排泄されるとしたって、異物を呑み込んでいることに違いはないんだから。かぼちゃは排泄もしないが、食べたものがどこにいくのかを気にしたらきっと俺の気が狂うので、考えないことにしている。
俺の家につまようじなんてものがある訳もなく、箸でひとつずつ抉り取る羽目になった。銃の手入れだって自分でするくらいには手先が器用な自覚はあるが、とはいえ種をほじくるだなんて作業に慣れているはずもねえ。ときたまスイカは折れてしまって、それはかぼちゃの……口……? に、呑み込まれていった。はじめはツチノコが嫉妬をして暴れていたが、そのうち静かになったので、おそらく拗ねたのだろう。
「……、ふう」
なんとか三角のカタチを保ってくれたスイカも生まれたぜ。大量の種を棄ててしまい、おそらく喰いきれないであろうスイカたちはラップをして冷蔵庫へ。ペットキャリーを覗くと、ツチノコはやはり丸くなって拗ねていた。出入り口を開けてみたが、出てこない。
「ノコ」
無言。
「ノーコ。スイカだぞ」
尻尾がすこし動く。
「ノコがいらねえなら、ぜんぶかぼちゃにやる」
びく、と身体が跳ねる。
「ノコ。いらない?」
ちろり、とついにツチノコがこちらを向いた。そこに微笑みかけてやれば、ようやくツチノコが動き出す。手のひらを差し出すと、ふだんの半分くらいのスピードではあるが乗ってくれた。やさしく額を撫でてやりながら、かぼちゃの待つダイニングへと向かう。
スイカを目視したツチノコはといえば、さっきまでの拗ねかたが嘘みてえに俊敏な動きで、ひらりと俺の手から離れていった。
――待て、皿ごといくんじゃない!
ツチノコを皿から引き剥がして、椅子を引く。種と同じく丸呑みにされると困るので、スイカの皮部分も切り落としたのだ。スイカっぽさって、赤と緑のバランスにも寄るんだなあ。そんなどうでもいい知見を得つつ、赤い果肉をそっとつまむ。ちなみに、赤のみになったスイカを見て、最初っからカットスイカを買えばよかったんじゃねえか、とか気付いたのは内緒だぜ。
「ほら、ノコ。あーん」
掛け声のとおりに、ノコがデカい口を開く。音もなく外れていく顎に怯えたのも昔の話だ。
あぐあぐと喰まれて、スイカはノコの口に消えていった。
「うまい?」
ノコ! という元気な返事からして、どうやら機嫌も直ってくれたらしい。
ふふ、と笑みが溢れる。ツチノコは食いしん坊で、放っておけばなんでも口にしちまうからさ。どうせなら、うまいものを喰ってほしいじゃん。ヒトに飼われて、つまりは自由を制限されているのだから、野良のころよりもうまいものを喰えるぐらいの恩恵はやりたい。その程度で恩恵とまで言っていいのかは疑問が残るが。
本当なら。あれのように料理をしてやれたなら、きっとツチノコはもっとしあわせになるのだろう。素材の味がどうこうは言い訳に過ぎない。ただ、俺にはこれしか用意できない、というだけだ。
「……、」
意識が散るのを咎めるように、ツチノコがすりと手にすり寄った。ごめんな、という声音は、我ながら白々しい。
この程度しかできなくて、ごめんな。
□■□■□
「こんなに部屋が余っているんだからさ、ひとつぐらいなら俺が使ってもよくねえか」
「え!?」
え!!!???
え、あ、は!? いや、いつかは一緒に住めたらなァ……とか思っちゃいたさ! でも急すぎるよ、なんにも用意してないよーッ!!
そんな私の混乱をよそに、彼は私を見ないままことばを続ける。
「ツチノコとかぼちゃにさ、広い部屋をやりたいんだ。ツチノコの誤飲だけは気をつけなくちゃあならねえけど、俺があいつらの部屋を新しく借りるより、おまえに預けたほうがいいだろう」
「え、あ、あー……?」
あれ、そういう話ですか?
彼の手に握られたコントローラは、なんの操作もされないままだ。よくよく観察していれば、彼のひとみだってべつに画面なんか見ちゃいない。
「おまえの料理が毎日喰えるってなら、あいつらも文句なんか言わないだろうし、……」
「ま、まあね。ジョンひとりぶんだけよりは、たくさん作れて私も楽しいかもしれないが」
「……俺が帰らなくても、飢えたりしないしさ」
うん。
うん?
帰らなくても、とは。
「ロナルド君」
「ずっと考えていたんだ。まだ伝えてはいないけど、あいつらもおまえのことを嫌っちゃいないし……俺のところにいるよりも、おまえのところのほうがよほど恩恵があるだろう?」
こちらを振り向く彼のひとみに、気付く。
彼は見ていないのだ。
あの子たちの、私に対するときと、彼に対するときの態度の違いだとか。あるいは、ときたま彼からあの子たちを預かったあと、彼が帰ってきたときの喜びようなんかでもいい。
恩恵。恩恵なあ。
ヒトによって、なにがうれしいのかなんてそれぞれだろう。私だって、彼がどうしたら満たされてくれるのか、わからないままでいるしね。
ロナルド君はひとみをとうめいにさせたまま、歌うように、あるいはしあわせそうに続ける。
「今度さ、スイカでなんか……なんでもいいから作ってくれよ。で、あいつらに喰わしてやって」
「……いいよ。きみも食べるんならな」
「?」
なにひとつ理解していないような顔をして、彼は素直に首を傾げた。
無意識であろうとも、私を頼ろうとしている、というのは評価してあげるべきだしね。
そして、怒られればいい。
そんな私の思惑通りに、彼は計画を嬉々としてあの子たちへ披露し――渾身のたいあたりを受け、困惑に目を白黒させていた。
「がッ、ぐ……!?」
「ざんねんでした、ロナルドくん。君の計画は穴だらけなのだよ」
「は、はァ? どこがだよ」
「君がいないだろ」
とん、と長い前髪で隠れた額をつついてみる。わかりやすく答えを突きつけてあげたのに、彼はそれでも理解していないみたいだった。
「君も一緒にうちに来るなら、あの子たちも許してくれるかもよ?」
「……? ……???」
――だめだこりゃ。
彼の情操教育には、まだまだ時間がかかりそうである。彼を除く、その場にいる全員が、深くて大きいため息をついた。
スイート・スイーツ

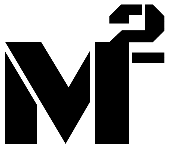
コメント