オレンジのショートケーキだった。
「……あ?」
「君がちゃんと脱稿できると信じて、用意していたのさ。疲れた脳には糖分だろ」
疲労でぼやけた視界に差し出されているそれ越しに、見慣れた吸血鬼を眺める。落ち窪んだ目元はやさしく緩んでいて、およそ吸血鬼が退治人に向けるものではない。
「……、」
またダメだったのだ。
たくさん、たくさん用意している。戦闘した吸血鬼の情報はかならずメモを残しているし、体験をどう表現したらいいのかずっと考えているはずなのに――また、気が付けば締め切りはすぐそこに迫っていた。発行部数のプレッシャーかなんなのか、巻を追うごとに俺が原稿を提出するスピードは落ちていく。編集がそれをせっつくことなく、大丈夫だと微笑みかけてくることがなおのことよくなかった。
だって、ノルマを達成できないほうが悪いに決まってんだろう。
ぎりぎりで原稿を送信して、自己嫌悪に苛まれる。それがきまりになり始めていて、この吸血鬼――ドラルクの城に入り浸っているがゆえに、それはドラルクと、ジョンにはすっかり知られていた。
まあ、つまり。
「……いらねえ。ジョンにあげてくれ」
「どうして? ジョンなら、もう自分のぶんを食べたよ」
「…………なら、ノコに」
「あの子ももう食べてる。あとは君だけ」
「………………」
やさしくされる理由がない。
叱られるべきなのだ。おまえはできないやつだ、と事実を述べるだけでいいのに、ドラルクはいつもそうしない。あまつさえ、がんばったね、などと頭を撫でてきさえする。ヒトなど吸血鬼にとっては愛玩動物でしかない、なんてことはわかりきっているが……いくらペットのすることとはいえ、突然押しかけて執筆部屋をつくれとねだるのは――ふつうに迷惑でしかないはずだ。
そうだ、俺はまた、迷惑を。
はじめのあの日から、なにも変わっちゃいねえ。
「わる、い。受け取れねえ……ごめん、」
「どうして? ああ、泣かないで。たくさん書いて疲れちゃったんだろう。あたたかい紅茶も淹れてあるよ、君の好きな茶葉を使っている。ね、ひとくちでいいから」
どうして、はこっちの台詞だ。
それを言葉にする前に、ドラルクがそっと俺の肩に触れる。ゆっくりと撫で下ろされると、涙は引っ込むどころかあふれて止まる様子がなかった。
吸血鬼の胸は意外に広い。
肩幅からして、骨格が無駄にしっかりしているのだろう。肋骨の幅はふつうの男と変わらないから。座ったままの俺が立っているドラルクに抱き込まれれば、頭は自然とそこに当たる。ガリガリで、やわらかくもなく、布地越しの肌は冷たい。感覚としては悪いはずだが、なぜか俺はそこに寄りかかってしまう。
呼吸が震える。
痙攣する背中を、角張ったてのひらが撫で下ろしていく。
「……大丈夫だよ。紅茶を飲んで、ケーキを食べたら、きみは元通りだ。涙を止めて、鼻もすっきりさせないと、せっかくの紅茶のかおりが楽しめないぞ」
うん、という声は鼻声で、とても聴かせられる声ではなかった。
六等分のケーキ

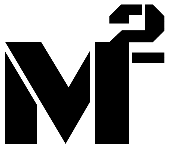
コメント