6/25無配でした。半分くらい雫さんの個人誌に寄稿したような内容です。
――もうすこし警戒してくれたっていいのに。
それが、率直な感想だった。もちろん、彼が誰にでも気を許すようなヒトじゃないだとか、むしろ気を許してもらえていることがとても稀有なことだとか、そういうのは理解してるよ。理解しているけれど、でもやっぱり、思うのだ。
私は吸血鬼で、彼は退治人といえど昼の子で。
尚且つ、われわれは恋人同士であるというのであれば――多少は警戒していたって、彼にバチは当たらないどころか、彼を救うのではないだろうか?
いや、ね。目の見えていない今の彼に手を出すなんて、そんなジェントル違反はもちろんしないとも。しないとはいえ、だ――単純に、ただ私が男として見られていないだけ、というのがちょっと、こう、癪というほどかといえばそんなこともなく……。
「ドラルク」
「ほぁ!」
「……なに?」
ビックリ死を耐えながら振り向けば、すぐ近くにロナルドくんの美しい顔がある。
けれど。
普段ならぴたりと合う視線が、やや下にズレていた。
深海のようにどろりとした、青いひとみ。その焦点が私に合わない、というだけのことなのに、どうしてこんなにイライラするのだろう。
「ご、ごめん、気付かなくてだね」
「はあ。気付けよ、お前は見えてんだから」
呆れまじりの言葉。叱責ではなく、茶化すような軽さのある声音だ。
それが、余計にしんどかった。
こんなことはなんでもない、そう言いたいのだろう。盲目をもたらす催眠を受けた、それ自体はいくらでも本のネタになる。そう言った彼に、その言葉を一言一句漏らさず代筆させられたのはこの私であるから、それが嘘でないことはわかっているけれど。
防げた事故だった。
私が同行していなければ、だ。
あるいは、きちんと吸血してことに及んでいれば。
吸血鬼を殺す方法を熟知しているのは、退治人だけではない。吸血鬼本人もまた、自身の死因となるものは把握していて当たり前だ。復活することのできない死に方、というのだって――当然のように。
私が狙われなければ、催眠を受ける隙など彼にはなかったのだ。
「――お前さァ」
探るような両手が、するりと私に絡みつく。
いや、探るように、ではない。彼には私が見えていないのだから、探らなければならないだけだ。そうしなければいけないのは私のせいで――。
「聞けよ、なあ。……俺はお前にいなくなられたら困る。お前は死なずに済んだ。ンで、やっこさんは塵になった。なのに、お前はなにが気に入らねーの」
「え、あ」
「お前以外の催眠を受けたから? どうせ採血したら死ぬじゃねえか……、それとも。この程度の催眠を受ける『ロナルド様』は解釈違いか」
「違う!」
『ロナルド様』なんて偶像はどうでもよくて、私は、ただ。
「君が、私を見てくれないから!! わたしは、……」
「ふは」
うれしそうな吐息がかかる。あたたかい、体温の失われなかった昼の子の身体を、私は私の全力で抱きしめた。
「……、ああ、くそ。そうだよ、君が私を信じていてくれたなら、君が私を庇うことはなかった。私は君が私を庇ったことなんかより、信じてもらえるほど強くなかったことを恥じて、悔やんでいるんだ……!」
「――お前がいなければ、俺はふつうに勝って終わっていたかもな。でも、実際はそうならなかった。お前がいて、俺はこうなったけど、でも勝った。目が見えなくても、お前がいたから、勝てたんだ。わかるか?」
「……、」
「もしものことなんか考えるな。……とりあえずさ」
ほんのすこしだけ身体を離して、彼は言う。
「トイレ行きてえ。連れてってくれ」
「君ほんとそういうことは早く言えよ!!」
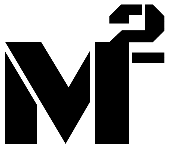

コメント
そういうとこだぞ!というオチが好きです。読ロ様のことなのできっと1人でも行けたんだろうなとなどと想像してにまにましてしまいました。
コメントありがとうございます!
たぶん一人で行けましたし、一人なら特にネタにもならないような戦いだったんでしょうね……。