我輩は吸血デメキンである。
名をキンデメ。
いや、名なのか、これは? まあ、渾名も名のひとつにはなろう。
とにかく、我輩はロナルド吸血鬼事務所で飼われている。飼われている、とみずから宣言することに多少思うところはあるが、しかし事実だ。
「おはよ、キンデメ」
『おはよう』
からり、と笑う男に挨拶を返す。男は嬉しそうにして、我輩の水槽に餌を入れた。フレーク状のそれは特別美味でもないが、すっかり慣れ親しんだ味だ。食べるところを見せつけると、男が安心したように微笑む。
繰り返すが、我輩は吸血デメキンである。
吸血鬼なのだ。
そしてこの男は、ロナルド吸血鬼事務所の主人、ロナルドその人で。
つまり、吸血鬼退治人である。
吸血鬼退治人が、吸血鬼に餌をやり、それを食べるところを確認して微笑んだ。
この事実を見て、異常性を理解していただけただろうか。
この男は知らないが、我輩はこう見えて(と言うのもなんなのだが)世界転覆を目論んだものだ。それがまあ、こうして大人しく、会話のできる金魚として飼われている。問われれば応えるし、まれにこちらから口も出した。
この狭い部屋に住まうのは、我輩とこの男だけではない。
高等吸血鬼がひとり。
その使い魔のアルマジロが一匹。
ツクモ吸血鬼が一機。
そのどれもを、この男は許容した。受け入れてしまっている。我輩へこうして餌をやり、挨拶するのと同じように。もちろん、受け入れられるため、それぞれ努力はしているのだ。それにあまりにもあっさりと、この男は絆されてしまう。そして、その自覚が、この男にはしっかりとある。
そのせいで。
「なあ、……ちょっとだけ事務所、連れてっていい?」
『うむ。いつものか』
「……、ん」
しっかりと赤い外套を着込んだ退治人は、その大きな体躯を縮めてこう言うのだ。
「ごめん、な。……すぐ終わらせるから」
抱え上げられて、ちゃぷ、と水が揺れる。
事務所のデスクは、すでに我輩の水槽を置くためかパソコンが端に寄せられていた。我輩はしっかりとデスクの真ん中を陣取ることになる。男も己のチェアに腰掛け。
「はあ〰︎〰︎〰︎ッッッ……」
頭を抱えてデスクに突っ伏した。
つむじがよく見える。指というものが吾輩にあるのなら、そこに突っ込んでみたいものだ。我輩に指はないし、そもそも人間の体温に触れたら火傷してしまうのだが。
「ドラ公さあ〰︎〰︎〰︎アイツさあ〰︎〰︎〰︎ほんとにさあ〰︎〰︎〰︎……」
『うむ』
「はあ、……はあ、あー。ごめん、な。……うう」
『まだなにも聞いていないが?』
「うん……。あ゛〜……」
曰く。
「わかってる、んだ。全部俺の勘違いなんだよ、うん。ドラ公はただ、ジョンが食べるから、ついでに俺の分を作ってくれてて。自分の洗濯のついでに俺の分も回しとけば、昼間にまとめて俺が干す。天日干しのほうが部屋干しより絶対いいから、それで洗濯回してて。んで、掃除は当然自分が使う部屋が汚くないためでさ……、」
つまるところ、吸血鬼ドラルクの行動は、自分のためではない――ということに、したいのだ。
「わかってる、のに――さあ、」
『……、』
「はあ、……」
自分のためではない行動には、喜びたくない。
「思い上がって、る、よな。ほんと……」
『そんなことはないだろう。そもそも、貴様が家主だ』
「そう、そうだよ。俺は住まわせてやってんだから、それくらいやらしても……、」
いい、と断言することさえできず、へにゃりと萎びた男。
「俺、さあ。てーしゅかんぱくなの? 俺、亭主なんかじゃないのに」
『……今度はどこで誰に言われた』
「ギルドで、ショットに」
たまにあれは遊びに来る。その時の様子からして、軽いからかいで言ったのだろう。
けれどこの男には、どうにもぐさりと突き刺さってしまったようで。
「……どらこー、が、いやなら……やんなくていいって言ったほうがいいよな、」
『……いやがっているようには見えないが?』
そもそも、家事なんてものは高等吸血鬼にとっては趣味のひとつだ。取り上げたほうが弱るだろう。それを説明しても、男は納得がいかない様子である。
「う〜……そう? なの?」
『うむ。あの男の脆さなら、いっそ家事を奪われたショックで死もあり得る』
「えぇ? うそだろ、靴下と家事が同等なの? マジでわかんねえ、吸血鬼……」
いや、まあ。
執着という点では惜しいところまでいっているが、そうではない。
執着している人間の世話ができなくなる。それは高等吸血鬼にとって、多大なるストレスとなるのだ。それも、本人からの拒否となればなおさら。
それをどう言葉にするか。吸血鬼からの恋慕を、吾輩が伝えるのは野暮にも程がある。うまいこと隠しつつ、けれど、けして悪意はないと伝えなければ。
『退治人は、どうなのだ』
「ぁえ?」
どこから出したんだ、その声。
『あの男に家事を任せるのは、いやなのか』
「へ、あ。……ん……。最初は、吸血鬼の飯なんかとか、思ってたけど……」
最初は、ということは、今は。
「……飯、うまいし。どんどん、俺の好きな味付けになってて……でも、それも変な話だよな? ジョンの好きな味付けじゃなくて、俺のなんて。ジョンと俺、味覚一緒じゃないぜ? ドーナッツとか、選ぶの全然違うもん」
『そうなのか?』
「うん、だから……普通の料理も、たぶん違うだろ。でも、アイツの料理はジョンのおまけで、なのに味付けは俺寄りって……え、おかしいな!?」
お。
これは、自分で真実に辿り着くのでは?
「お、俺! 起きたらアイツに言わねえと。ちゃんとジョンの好きな料理作ってやれ、って! そうだよ、なんでいままで気付かなかったんだ!?」
『………………、……』
なにがどうしてそうなった。
『……吸血鬼とその使い魔が、望んで退治人好みの料理を作っているのでは』
「は? そんなわけないだろ。ドラ公はともかく、ジョンがきっと気を遣ってるんだ……ショット、もしかして、それに気付いてたのかな。だから亭主関白なんて……」
ぎゅう、とその手を握りしめて、退治人は高らかに宣言する。
「決めた! 俺、アイツらに気を遣わせないように頑張る」
『頑張る、とは。どのように』
聞いておかねば。そして暴走を止める役割が、吾輩にはある。
「えっと。まずは、ドラ公にジョン好みの料理を作ってやれって言うだろ? それから、ジョンには気を遣わなくていいんだぞ、って言ってやらなくちゃ」
『ほう。気を遣ってなどいないと言われたら?』
「そんなの! ……ジョンはたしかに、やさしいからそう言うだろうけど。でも、本当にいいんだ、って教えてやらなきゃ。俺はそんなふうにされる価値なんてない」
『な、』
――この男は、どうして。
「……ジョンの、おかげだ。ジョンがいてくれるから、アイツが作る料理のおこぼれにあずかれてる。だから、ジョンが食べたいものを作るべきなんだよ」
『退治人よ』
「ん? どした、キンデメ」
『退治人よ。よく聞け』
素直に、おう、と応える男は、ひどくまっすぐな、澄んだ目をしていて。
心の底から、自分には価値がないと信じきっているのが、わかる。
ならば。
『――我々は、貴様を愛しているぞ』
「ん、……ん!? あ、え、は!?」
『我輩はもちろん友愛だが』
「エッアッ、うん、そうだよな! ……え、我輩『は』なの?」
『とにかく、愛していることに代わりはない。退治人は、兄を貶すものをどう思う』
「なに? え、兄貴を貶すやつなんか法の許す限りボコボコにするけど」
『それもどうかと思うが……つまり、それと同じことだ。我輩は、我輩の愛する退治人を貶されて、腹が立った』
「あいする、はんたー……?」
『貴様のことだぞ』
「え? ……え、あ、うん。……???」
『たとえば、扉の向こうで耳を澄ませている高等吸血鬼も。同じ意見だろう』
「えっ」
がば、と立ち上がり、退治人がドアを開け放つ。ドアに体重を預けていた吸血鬼が、思いっきり退治人の胸に飛び込むかたちとなった。それを退治人が事もなげに抱き留めたはいいものの、どちらもぎしりと固まったまま動かない。
それでも、先に口を開いたのは吸血鬼のほうだった。年上の意地だろうか?
「あ、あー……えっと。その、ロナルド君……、」
「ど、どらこ……おまえ、どこから、聞いて」
「っ……、うん? まあ……君が、キンデメさんに相談し出した頃……から」
「うそだろ今日の話じゃねえの!?」
「ウアーッ!!」
あまりのショックに力が入りすぎたのか、物理的に退治人が吸血鬼を抱き潰した。砂の一部を抱えたまま、へなへなと床に座り込む。うーうー唸って、絶望の淵と言わんばかりだ。そんな腕のなかからなんとか砂塵を抜け出させて、吸血鬼が再生する。
「……ロナルド君」
「……っ、なんだよ、笑うなら笑えよ! 気持ち悪いならそう言えよッ」
「言わない、笑わないよ。……だって、私も同じ気持ちだもの」
「……、え」
「ね。……せめて、顔を見て、目を合わせてから言わせてよ。こっち見て?」
やさしく、諭すような声音を出す吸血鬼。けれど、退治人は首を横に振る。
「い、いや、だ」
「どうして」
「おっ、お前は、冗談でも。俺、……俺、キンデメに相談するくらい本気なんだぞ」
「私だって、冗談でいまから言うことを口にしたりなんかしないとも」
「……ッ、でも……」
『あー、ごほん』
「「ッ!!」」
うむ、忘れられていたな。
がばり、とふたつの顔がこちらを向く。真っ赤で情けないそれらはよく似た表情で、そういえば一緒にいると表情が似ていくことがあるらしいな、とぼんやり思った。
『ここは来客もある。大事な話なら、予備室を使え』
「あ、う、うん……」
「……えっ、と。行こっか、ロナルド君」
「……、ん……」
差し出された吸血鬼の手に、ゆっくりと退治人のそれが乗る。とはいえ、吸血鬼に退治人を引き上げるような力はない。それはあくまでポーズでしかないが、けれど、ふたりにはきっと必要なものだった。
連れ立って生活スペースの奥に向かうふたりに、思う。
『……我輩を戻していけ、と言うのを忘れたな……』
「ヌン!」
『うむ? おお、頼めるか』
それはそうか、このマジロがいるではないか。厚意に甘え、定位置へ帰る。
さて、あのふたりはどうなることやら。
彼はスーパーアドバイザー!

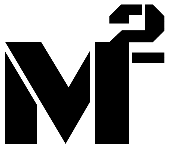
コメント
『今度はどこで誰に言われた』ってキンデメさんテライケメン···。この一文いろいろ感情詰まってる気がして好きです
コメントありがとうございます!
デメさんがロ君を想っている、というのを意識したセリフなので気付いていただけてうれしー!