殴られたのであろう箇所がじいん、と痛む。
ぴと、ぴちゃり、と水が垂れる音。一定の間隔を保つそれのおかげで、この地下牢らしき場所が静寂に包まれることはなかった。ほう、とため息をついてみても、なんの意味も持ちはしない。監視のひとりもいないのはどうかと思うのだが。
「……、」
ドラルク、は。うるさい家主がいなくなって、せいせいしているかもしれない。
ジョンはやさしいから、心配してくれるかもしれないが。
メビヤツは俺の味方だから、このまま帰らなかったら悲しんでくれるかもだし。
キンデメのごはん、ちゃんとドラルクがあげてくれるかな。
死のゲーム……は、もともとドラルクのだから。俺に関しては何も思わないだろ。
うん。
未練みたいなものは、メビヤツくらいだ。
でもメビヤツも、なんだかんだ半田がよく相手してくれるからな。きっと、寂しくなんかない。だから、大丈夫。
俺がこのまま帰らなくても。
兄貴やヒマには遺書を残している。問題はなにもない。
このまま、死ぬまで放置されるのか。それとも、生きたまま血を抜かれるのか、わからないけど。でもまあ、退治人なんだから、こういう終わりを迎えることもある。フクマさんだって、俺になにかあればロナ戦が突然終わることもわかっているんだ。
目を閉じれば、水の滴る音が響く。
大丈夫。
俺は強い。
後ろ手に縛られているから、血の巡りがおかしくなってつらい、とかもないし。
大丈夫。
誰も助けになんか来なくても、自力で出ることはできるだろう。今のままでは無理だから、なにかしら、見回りの一つでも来れば。
来なかったときは、まあ、諦めるしかないが。
「……、」
ああ、でも。
最後に、ドラ公の飯、食べたかったなあ。
好き、だった。想っていられるだけで幸せだったから、悔いはないけれど。
ドラ公がしあわせになるところを、祝ってやれないことだけは、残念かもしれない。
なあ、ドラ公。
俺、お前を好きだってこと、ちゃんと隠し通せていたよな。
譲れなかった。
これだけは。これだけは、どうしても、お前に笑われたくなかったんだ。
俺がこのまま帰らなくても、お前はどうにでもやっていける。お前は俺とは違うから。享楽主義の名の下に、好きなことだけして、面白おかしく暮らしていけばいい。
俺のことなんか、さっさと忘れろよ。
コツ、という靴の音に、まぶたをひらいてそちらを向く。
見たことのない女性が立っていた。吸血鬼のコスプレをしてるのか、本当に吸血鬼なのか……って疑うくらい、テンプレートな服装。そう、ゴルゴナさんとかの服に似てる気がする。年に一回会うかどうかだから記憶は朧げだ。
「お目覚めかしら」
「……、おかげさまで?」
とりあえず、そう答えてみる。女性はくすりと笑って、俺の前でしゃがんだ。
絶対に、たとえ腕が縛られていなくても、届かない位置。
「……、」
「ねえ。どうして、あなたなのかしらね」
「?」
なんだ?
どうして、俺なのか。
え、マジで何?
疑問が顔面に出ていたのか、また女性に笑われる。
「竜の一族は高貴な血なの」
「……?」
「もちろん、血族として迎えられた方々も素晴らしいけれど。……『D』は……御真祖様と、その血を受け継ぐ方たちは」
御真祖様。トンデモハリケーンジジイの真顔ダブルピースがはっきり思い浮かんで、ちょっと口が歪んだ。
「ドラウス様。そして――ドラルク様」
「……、」
「ドラルク様がおかしくなったのは、あなたのせいでしょう。だから聞いたの、どうして、あなたなのかしらねって」
「どうして、って言われてもな。俺のほうが知りてえよ」
どうして、俺なんかと居てくれるんだろうな、ほんと。
本心からの発言だったが、女性は不愉快そうに歯軋りをした。そのときに牙が見えて、ああ、吸血鬼だったんだな、と思う。
「忌々しい。忌々しいわ。こんな人間が現れなければ、あの方は高貴なままだった」
「まあ、たしかに最近アイツ口悪いよな」
俺がそう言った瞬間である。
どちらかといえば温厚そうだった雰囲気が一変して、ぎ、と睨まれた。
「あいつだなんて、口を慎みなさい!」
「え、あ、はい?」
やべ、うっかり『ドラ公』とか『砂』とか言ったらそれだけで殺されそうだ。
ちょっと気をつけるのを心に刻む。
「まったく。……御真祖様が人間との和を望まれなければ、こんな人間すぐに吸い殺してやるというのに……」
拉致監禁は和じゃねえと思うんだけどなあ。そこんとこどうよ?
とか聞いても殺されそうな気がする。
うーんうーん。暴力が封じられるとどうにもなあ。
怒りとか、不機嫌とか。
そういう空気を滲ませていた女性が、ふ、と雰囲気を和らげた。
「とはいえ、」
「?」
そうだな……例えるのなら、Y談おじさんとかがよくする、あの顔だ。
「これで、あの方達は正気に戻ってくださるでしょう」
――狂わせる原因が、なくなるのだから。
取り出した小瓶を揺らして、女性は唄う。
「あなたには血を飲んでやるほどの価値もない。事切れたら、きちんと始末はしてあげる。だから安心して、この毒を飲みなさい」
「……、」
毒。
毒なら、手を差し出してくるんだろう。
手に噛みつくチャンスがあるだろうか。うっかり口に入るかもしれねえから、頭突きとかのほうがいいのか?
きゅぽ、と栓を抜く、間抜けな音。
女性は一度腰を上げて、もう一度近付いてくる。コツ、という靴の音と、ぴちゃ、という水の音を聞きながら、タイミングを狙った。
だけど。
ずがん!! と、轟音とともに牢が揺れる。
「なに……!?」
「ッ、」
女性はふらりとよろめいて、毒らしい液体をちょっとこぼした。なんかこう、じゅわっと床が溶けたりはしないんだな。アレは漫画とかの効果なのかなあ。
ざっ、ざっ、っていう、靴とは違う足音が近付いてくる。女性も俺も、息を呑んでそれの到着を待つしかなかった。
白銀の狼、って――聞いてはいたけど、見たことなかったんだ、俺。それに、俺の知っているあの吸血鬼は、もうちょっと、こう……ポンコツだったので。
狼が口を開いても、すぐにはイコールでつながってくれなかった。
『まったく。探したぞ、ポール』
「……親父さん?」
日本語を喋る狼。アニメならカッケー! ってなるけど、いまいち現実だとなんか、……シュールだ。
『おいポール、貴様いま失礼なことを考えているだろう』
「んなことねえって、」
ざりざり言ってたのは親父さんの爪の音らしい。こちらにどんどん近付いてくる親父さんに、女性がふと我に返った。瓶を投げ捨てて、膝をつき、こうべを垂れる。
「ドラウス様……!」
『……、』
「へ?」
あれ?
親父さんみたいな人でも、誰かをシカトとかするんだな。
女性には目もくれず、まっすぐ俺に向かってくる。無言のまま、ちょい、と俺の後ろに戯れついた――違う、これ、俺の拘束を爪で壊したんだ。すげえな、ちょい、で壊れるようなもんじゃねえだろ、これ。俺が全力でガチャガチャやっても壊れなかったのに。あらためて、その能力の高さを知る。
『さ、帰るぞ。ドラルクが入り口で待ってる』
「は? ドラ公も居んのかよ」
クソザコのくせに、なんでまた。拘束されていたせいで固まった関節をほぐしつつ、首を傾げると親父さんがちょっとぶーたれる。その姿だとカワイイな。
『当たり前だろう。まったく、心配――、は、していないが! そう、私はべつに』
「まあいいや。サンキュ」
『聞けクソポール!』
「……っ」
ざわ、とゆらめく殺気。
親父さんに倣って、あえて無視してみたんだが。女性は簡単に煽られたみてえだな。それでも俺に飛びかからないのは、理性がまだあるのか、親父さんがそれだけ怖えのか。……まあ、拉致監禁されている時点で、俺が暴れるに足るものはある。
でもなんとなく、最後のひと押しが欲しいので。
「親父さん。いつまでその姿なんだ?」
『む』
「戻れよ。俺が拘束されてないなら、親父さんがその姿でいる必要はないだろ?」
『! ……、ふむ。確かにな』
ゆらりと狼のすがたがゆらめき、見慣れたオッサンが現れる。傷も汚れもない、いつもどおりの風貌だ。まあ、余裕だったんだろう、ここに来るまで。
つまり。
俺が暴れられるなら、親父さんが暴れる必要はない。
俺みてえな人間でも、コイツらを抑え込むにはじゅうぶんだ。
吸血鬼どもが求める、畏怖の正反対。
明白な侮蔑を受けて、女性は我慢がきかなくなったらしい。
「ポールの装備を取りに行くか。こちらだ」
「なんだよ、先に持ってきてくれてりゃあ――」
外見が女性であろうと。
吸血鬼であるならば。
人間を害する吸血鬼であるならば、容赦する理由はどこにもない。
「楽ができたのに、よお!」
「ぐ、ぎゃ!?」
爪を掲げて飛び掛かってくる女性の動きは、完全に肉体の強さに頼り切った、技巧もなにもないものだった。それなら、避けるんじゃねえ。受け流して、利用してやる。
ちゃんと道場とかでこれを習うなら、合気道とかになんのかな? 知らんけど。
女性はきれいに一回転して吹っ飛んでいく。……でもなあ、縛り上げるためのツールとかも、銃と一緒に没収されちまってるんだよな。仕方ねえから、このまま放置して、荷物を取り返したほうがいいかもしれねえ。
「じゃ、親父さん。案内してくれ」
「……、うむ」
なんか言いたげな空白のあと、大袈裟にマントを翻した親父さん。こうやってさあ、ちょっとした動作が一緒なんだよなー、ドラ公と。
んふ。
そっか、アイツ、来たのか。
なんもできねえクソザコのくせに。
てめえの親父に全部任せることになるなら、事務所でもここの入り口でも対して変わらねえのに、それでも来たのか。
「……、ふ」
「監禁されて興奮するタイプの変態だったのか?」
「あ? だったら拘束とかれる前に興奮すんだろ。つか興奮はいまもしてねえ」
ただちょっと、嬉しいだけだ!
――どうか目を覚まされてくださいまし。
ふざけた手紙を握りつぶす。目を覚まさないのは、貴様たちだろう。いつまでも旧時代に取り残された、遺物たちの戯言だ。
お父様に電話を。
それから、御真祖様にRINEを。
「ヌヌヌヌヌン……」
「ん? うん。大丈夫だよ、ジョン」
クラバットにきゅうと縋る、ちいさな手を握る。
震えているのは、どちらか。
「――大丈夫、」
「おまたせ」
ばさりと響く羽音。自分で呼んだんだから来るのはわかっていたとも。でもねえ、それでも急に来られたらビックリ死は免れないのだよね、悲しいことに。
ヌーヌーと泣くジョンをあやしながら復活すれば、そこにはもちろん、御真祖様が佇んでいた。
「行く?」
「ええ」
「ヌ!」
ふ、と御真祖様の気配がすこしだけ和らぐ。表情には現れにくい、微笑み。
差し出された腕にジョンを差し出し、それから自分もしがみついた。
「じゃ、行こ」
どこに、なんて。
そんなもの、とっくにお父様が割り出しているとも。
わあお、死屍累々。
でもまあ、本当に死んでたら、ここは塵だらけになっているはずだ。人間のかたちを保ってる、ってことはここに転がってる連中はみんな生きてるんだな。
「ほら、あったぞ」
「ん、おお。うっわ、雑にまとめやがって」
俺、気になるんだけどさあ。
親父さん、人間の姿のままでも鼻いいんだろうか?
この部屋まで、この姿で迷わずまっすぐだったんだが。単に場所をもともと確認してたんだとしたら、そん時持ってきてくれりゃよくねえ?
ガンベルトを装着するのがめずらしいのか、じい、と親父さんが見つめてくる。
「んだよ」
「着けなくても、持ったまま出ればよかろう」
「え? あ、まあ。なんだよ、急かすなよ」
ぽす、と帽子を頭に乗せれば、支度完了だ。
「よし、帰っか」
「……ポール、お前わざと」
知らね知らね、っと。
出入り口を知らんから、また俺は親父さんのあとをついていくだけだ。むにむにとくちびるを歪ませて、だけどなにも言わないまま、親父さんは歩き出す。途中、意識を取り戻しかけた吸血鬼を踏んづけたりしつつ。
「よ」
「……、よ、じゃないだろう」
あくまで軽く、気楽に手を挙げて言ってみたけど、まあ、ダメか。
弾丸みてえにジョンがぶっ飛んできて、腹に直撃する前に受け止める。ヌンヌン泣くジョンはかわいくて、かわいそうだから、必死に丸まった背中を撫でてやって。
「ヌー、ヌゥア!!」
「あー、どした? よしよし、いい子だぞお」
……、……。
ジョン越しに、ちらりと覗き見たドラ公は。
意外と、怒ってなかった。
「……?」
「ロナルド君。怪我は」
「ん、ん。多分、殴られたぐらい?」
「そう。痛みは?」
「もうねえ。起きてすぐはあったけど」
「……、そう。でも、一応医者に行こう」
「おう……」
ゆっくりと近付いてくるドラ公に、そっとジョンを渡そうとする。だけどジョンは俺の腕にしがみつくようにして、離れてくれない。
「ジョン?」
「んふ。きみのそばがいいってさ」
「無事で何より」
「オア!?」
急に背後を取るなバカ!!
このヒマリほどじゃねえにしろ、端的な言葉遣いは特徴的だ。
「……爺さんまで呼んだのかよ」
「うん、呼ばれた」
「当たり前だろ」
ピースする爺さん、ジョンがいなくて手持ち無沙汰なのか、珍しく腕組みなんかしてるドラ公。……いいのかなあ、これ。竜の一族三代揃っちまって。
「ま、私で十分だったがな!」
ふふん、とふんぞりかえる親父さんに苦笑して、らしいな、と返す。
「さ、ロナルドくん」
「ん?」
す、と差し出された、枯れ枝みてえな手。肌触りのよい(というより、悪いやつを使うと死ぬだけだが)手袋に包まれたそれが、なにを求めてるか分からねえわけじゃねえ、ねえ、けどさ。
でもべつに、俺、恭しく手を引かれるような淑女じゃねえんだ。
ただの同居人。
たまたまそうなっただけで、いてもいなくてもかわらないはずのもの。
なのに、お前はわざわざ、親と爺さんに俺を助け出させて。
こうやって、手を引いて帰ろうとするのか。
「……、ばーか。クソ砂おじさん」
「急な罵倒!?」
罵倒のショックで砂になったドラ公に、ジョンが悲しそうな泣き声をあげる。砂山にジョンを下ろしてやって、スマホを取り出した。
圏外。
「あれ?」
「ポールを探せないようにだろう。人間が作ったモノで言う、チャフに近い」
「ええ。わざわざ?」
なんでまた、そこまでして俺をとっ捕まえたんだ。
吸血鬼の考えることって、いつまでも理解できねえ。ドラ公とこれだけ一緒にいるのに、そのドラ公の考えがなんもわかんねえんだ。知らねえ吸血鬼の考えなんか、わかるわけもなく。
「いまの場所がわかんねえと、帰りかたもわかんねえじゃん」
「はあ? そんなもの、私たちが連れて帰ってやる。ポールは大人しく荷物になればいい」
「え、いいよ、わざわざ助けてもらったんだし。あとは自力で」
「ロナルド君」
「かえ、う?」
いつのまにか復活していたドラ公に、ぐい、とジョンを押し付けられた。んで、そのジョンが、俺の顔をそのちっちゃい手で挟み込む。ジョン〜♡ かわいいね♡
「んむ?」
「ロナルドくん。一緒に帰ろう」
よじよじ肩にのぼってくるジョンがかわいくて頬を緩めていると、ドラ公はあたりまえのことを言う。
「え、うん。え? お前は帰るだろ。帰んないの」
「……、うん。そうだね、……はあ」
???
あれ。ドラ公はもしかして実家のほうに帰るのか? そう思って、聞いてみる前に抱きしめられた。
は?
「え」
疑問が形になる前に、今度はドラ公ごと爺さんに抱きしめられる。え? なに?
「ちょ、」
「舌を噛むよ」
ばさり、と広がる巨大な翼。
え。
一緒に帰る、って。
一緒に飛んで帰る、ってことか!?
「〰︎〰︎〰︎ッ!?」
こわいこわいこわい!!
爺さんはともかく、貧弱クソ砂の腕力が怖い! こいつ、途中で疲れたとか言って腕の力を抜いて落ちていったりしねえよな? かといって抱き返して潰すのも怖い。
緊張でがちりと固まった俺に、ヌー、という優しい声がかかる。
「ヌヌヌヌヌン。ヌシヌシ」
「うあ、ジョ、ジョン〜……♡」
「チョロゴリラめ。……心配しなくても、来る時もこれだったんだから。そんなガチガチにならなくていいよ」
「ッ、うるせ……」
そんなこと、言われても。
仮に、ドラ公が死なねえとしてもだ。大前提として、好きなやつに、抱きしめられてるわけ、で。どっちにしたって、緊張するじゃんか、そんなの。
俺、俺さ、誤魔化せてる?
密着して、照れてるわけじゃなくて。ドラ公が死ぬのを恐れて、それで心臓がバクバクしてるって、そういうことにできてんの、かな。
こわい。
知られたくないんだよ。
笑われるのも、蔑まれるのも、同じくらいに恐ろしくて。
「……、ッ」
ずっと想っていたい、から。
「ロナルドくん」
「なん、だよ」
「帰ったら、君に伝えることがあるから」
「あ?」
なんだろう。
もしかして、バレた、のか。
出てく、って言われるのかな。
いやだ。いやだなあ。でも、バレたんだったら、それは俺の不手際だ。仕方がない。諦めるしか、ないだろう。
ずっと黙ったままの爺さんは、淡々と翼を動かしている。これさ、物理法則がどうこうじゃなくて、『これを動かしたら飛べる』、そういう決めごとみたいな、っていうか。明らかにおかしいんだけど、『それはそういうものだ』っていう、有無を言わさず刷り込むみたいな、強制力のようなものを感じる。
あ? って聞いてやったのに、ドラ公はそれきりなにも言わなくなった。ジョンもそれに倣うみたいに静かだから、そうしたら俺も黙るしかない。ばさ、ばさりと、羽の音だけが聞こえている。
そうっと、ドラ公に回す腕を、ほんのすこしだけ強くした。最後なんだから、それくらいのことは、許されたかったんだ。
メビヤツに帽子を預けて、外套を脱ぐ彼を見ている。
まあ生命力に溢れたゴリラだからね、怪我は大したことなかったよ。一応立ち寄った病院でかるーく手当を受けて、無事に事務所へ戻ってきた、私のかわいい昼の子。
「ロナルド君」
「――、ん」
君に伝えることがあるから。そう言ったはいいものの、だ。こうして名前を呼んでしまったのだから、もう言わないわけにはいかない。だけど、恐ろしくって、恐ろしさだけで死んでしまいそうだった。
「あの、さ」
「……なんだよ」
ああ、どうしてこっちを見てくれないんだろう。向かい合って座ったら、こっちを見てくれるかしら。
「その、……ようやく帰って来られたんだから。ゆっくりしよう。ダイニングにお座りよ、ホットミルク作ってあげる」
「あ、……おう」
ヌヌヌヌヌン、とジョンに促されて、ロナルド君がテーブルにつく。どこか動きが鈍いように感じるのは、やはり疲労からだろうか。それはそうだ、暴行からの拉致監禁を受けて、疲労しないものは人間にも吸血鬼にもいない。
くるくるとミルクをかき混ぜながら、心を落ち着ける。
大丈夫。
伝えなければなにも始まらないのだ。それどころか、こうして奪われようとしてしまう。ぬるま湯のように心地よいものでありながら、相反するように刺激的な日々。それにあぐらをかいていたらいけないのだ、と。
拒絶を受けてしまったら、まあ、その時考えよう。
にっぴきぶんのホットミルクがダイニングに並ぶ。
「どうぞ」
「ん、」
ヌフー、ヌフー、というジョンと、ふぅ、ふぅ、というロナルド君の、ミルクを冷ますための吐息の音。穏やかな時間の流れを感じて、緊張がほぐれていく。私はまだ、ミルクに手をつけていないのにね。
「ヌイシー!」
「ふ……、うん。うまいな」
「そう。よかった」
諸手を上げて喜ぶジョンに、ロナルド君の表情が和らぐ。彼がかわいいものを愛でるときにする、だらしのない顔が好きだ。
そう、好きなんだよ。私は、彼のことが、好きだ。
「好きだよ」
「――……、え?」
「ヌヒッ」
ぽ、と頬を染めたおっさんマジロは、もう彼の眼中になかった。
「好き。好きだよ、ロナルド君。君が好きだ、愛している」
「ちょ、……え、は? 待て、」
「君をあんな目に遭わせたのは、我々の一族の落ち度だ。本当にすまなかった」
「待てって、」
「好きだ。好きなんだよ」
手をつけられないまま、私のミルクは冷めていくけれど。
この気持ちは、グラグラと煮立ってしまうのだ。私は享楽主義であり、そこに蓋をしようとしていたのが間違いなんだよね。
彼の膂力で握り締められて、みしりとマグが悲鳴をあげる。そのゆびさきにやさしく手を添えてやっても、振り払われないことに期待してもいいんだろうか。
「ロナルドくん」
「ま……待って、くれよ。おまえ、」
「待たない。違うな、待てないんだ。待ってるばかりじゃ逃げられてしまうだろう」
「逃げ、るって」
「私の気持ちと、君の気持ちから」
もし。
もし、私の告白が不愉快ならば。
嫌悪とか、侮蔑とか、そういうものが、表情に表れるだろう。
けれど。
けれど、彼の表情は。
赤く熟れて、熱を持っている。
それは。
それは、期待してもいいのだろう、なあ?
「ドラ、ルク……!」
テーブルが邪魔だ、と思う。彼と向かいあうために、利用したというのにね。イスを蹴って立ち上がり、死なないように腰を曲げつつ、彼の頬に手を添えて。
ホットミルクの甘い、甘い味がした。
ミルクに込めた愛

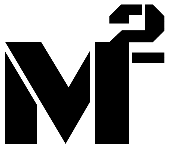
コメント
あー!パパが!畏怖格好良い!!
ロナルド君とドラウスの絡み大好物です。ありがとうございます。
畏怖カッコいいやった〜!
前回のパパがかわいそうだったので、活躍していただきました😉👍
コメントありがとうございます!