「なあ、爪切りって借りれたりする?」
「爪切り?」
ゲームを一時停止して振り返る。ソファでカタカタと原稿を打ち込んでいたはずのロナルド君は、おのれの手を見つめて眉をひそめていた。
「なんか……気になって集中できなくなってきた。爪切りてえ」
「ああ、なるほど。爪切りなら……」
ある。
あるし、貸すのもまったく問題はない。
問題はないけど……面白くもないよな。どうせなら、やってみたいことがあるし。
「そのまま座っていてくれ。準備をするよ」
「?」
ん、とうなずいた彼は微妙そうな顔のまま、とりあえずはキーボードを叩くことを選択したらしい。信頼されているのはありがたいが、よくわかんないままうなずくの、やめたほうがいいと思うんだけどな。まあ、私は彼に危害を加えるつもりがあるって訳じゃないからいいけどさ。
座っていた棺桶を開けて、道具を取り出す。肌色の悪さを隠すための、マナー用品といったところのネイル道具。ガラス製の爪やすりと、削りかすを落とすための水をいれるカップが必要だ。水を汲んで戻ったら、彼は興味深そうにやすりを眺めていた。
「爪切りは?」
「ほんとはな、切らずにやすりで形を整えたほうが爪にいいんだ。やってあげよう」
「ふうん」
いかにも興味なさそうなふうんをいただきながら彼の隣に座る。
素直に差し出された手を受け取り、ゆっくりと爪にやすりを当てた。痛みがあれば言うように、と言い含めたが、みょうな我慢をしないといいけど……。
そこまで力をかけずとも、爪は簡単に削れていく。削りすぎに気を付けながら、ぐ、と手を動かせばあっという間だ。当然爪切りのほうが早いとは思うけどさ、やっぱりこういうのを丁寧な暮らしって言うんじゃないか?
形を整えたら、軽く表面も磨いてやる。そうすればピカピカに光ってかわいらしい爪になるのだ。色を施す訳じゃないし、甘皮まではいいかな。
「できたよ。反対側も見せてくれるかい」
「あ、うん……」
やたらぼんやりとした声音。
違和感をもって顔をあげると、彼はほんとうに眠そうにしていた。爪を削られても眠くはならないと思うんだけど……それはふつうの反応であって、彼は彼だしなあ。リラックスが苦手なロナルド君にとって、ゆっくり爪を削るのは初体験だろうし。
なるべくやさしく。意識しながら、もう片方の爪もととのえてやる。時折やすりのカスを水で落としながら、肉を削らないように細心の注意をはらって……。
「――うむ。きれいになった」
「……、あ」
「あ、待ってくれ、まだ終わりじゃないんだ。もうちょっとそのままな」
ほんとうは水気を拭くだけで終わりなんだけど、いい意味でいじわるをしてやろう。ティッシュでささっと水気をとったら、爪にネイルオイルを垂らしてやるのだ。
彼は首をかしげて、いいにおいだ、と言った。
「これはひのきの香りがついているからな」
「ひのき……風呂?」
「ふは、まあ、よく使われるのは浴槽かな。やわらかくていいにおいだろ?」
「うん……」
「ほんとに寝そうになってるじゃないか」
爪と肉のあいだにうりうりとオイルを塗りこんでやる。余ったぶんも手全体に向け行き渡らせてから、できたよ、とささやいた。彼がほうとため息をつく。
「結局、仕事って感じじゃなくなっちゃったな」
「いいじゃないか、休憩ぐらい。紅茶のおかわりでも淹れるか? せっかくだしな」
「いや……それはあとでいい」
「うん? うわっ」
がし、と腰を掴まれ、身体を持ち上げられる。彼の膝にまたがる形で降ろされた。クラバットに顔をうずめて、彼がまぶたを閉じる。抱き枕にされちゃうのか?
「眠くした責任とれよ。俺は仕事が捗らないから爪切りてえって言ったのに」
「え〜……いやまあ、たしかに君のオーダーを叶えてはいないのか。どうしようか? ベッドまでエスコートする?」
「それじゃほんとにガチ寝しちゃうじゃん。ちょっと休んだらそれでいい……」
このままガチ寝しそうなとろっとろの声してますけども。
「……おまえに大事にされるの、眠くなる……」
「……、それはよかった。私、君が気を緩めてくれるのがなによりうれしいんだ」
「ん……」
大事にされている自覚が持ててなによりだ。銀糸をゆっくり指でもてあそぶ。
「何分寝たら起こす?」
「五分……」
「短すぎるわバカ。三〇分な」
「うん……」
こて、と彼の首が力を失った。
うーん、心配だ。ちょっと身体の力を抜かせただけでこれとは……。起きたらまた仕事をしたがるんだろうけど、静止してベッドまでエスコートしたほうがよさそうか。
抱きしめた身体の呼吸はおだやかだ。
私が膝に乗っていたままでいいのか悩む。彼がそうしたいと思ったのならばさせてやるべき、とも思うが、こんな骨ばかりの身体でも五〇キロはあるんだぞ。膝の上に三〇分乗せていていい重みではない。隣で寝転んであげるとかならやぶさかでないが、仮に念動力なんかを使って運んだりするとして、途中で彼が起きないはずもないし。
う〜む……。
――おおい、ジョン。
テレパスで呼びかけた愛しい使い魔は、すぐに駆け寄ってきてくれた。ツチノコやかぼちゃたちもついてきて、眠っている彼のようすに首をかしげている。
「ヌ?」
「ちょっとボトルを持ってきてほしいんだ。このままじゃいくら彼でも潰れてしまうかもしれないだろう?」
「ヌイ!」
結論、ちょっと浮く!
重みが完全になくなっても違和感で起きるだろうから、多少は残さないとかなあ。いまの私、そんな器用なことできるんだろうか。やや不安は残るが、起こしてしまうならそのとき、きちんとベッドまでエスコートして添い寝でもしてやろう。
文字にすると「ケツでホバリングする」とかいうめっちゃダッサイ字面だが、実際めちゃくちゃ技術の要ることなんだからな!
あんまり急いで血を飲んだって私の場合は咽せて死にかねない。あくまでゆっくり、じっくりと血液を摂取した。ジョンにグラスをお願いして……魔力を込める。
「おお……案外できるな」
「ヌフフ」
「笑わないでくれ、ジョン。絵面が面白いのはわかるよ」
これで彼の足がうっ血することもないだろう、たぶん。
ロナルド君はかわらず、おだやかに寝息をたてている。私もジョンも声をひそめているとはいえ、この近さではじゅうぶんに騒音なはずだ。それでも……彼にとっては不快なものではない、らしい。
「……ふふ」
ゆっくり眠っていてほしいと思うし、起きて、私に笑いかけてほしいとも思う。
彼がこんなにすべてを預けてくれる日が来るなんて、過去の私は思わなかったよ。
「ロナルド君。ロナルドくん」
「……ん……」
軽く肩を叩きながら呼びかけると、長い銀のまつげがふるりと震える。
深海のようなひとみはしばらくぼやけていたが、私を見つけて驚いたようだった。君が膝に乗せたんだけどなあ。
「ド……。ああ、そうか……」
「思い出したかい。よく眠れた?」
「んん……たぶん」
眠りに落ちる前とおなじく、ふわふわとした口調。いとけなさを滲ませられると、庇護欲だけではなく性欲までも掻き立てられてしまうようになった。異常性癖者だと罵られてもおかしくないかもしれない。いや、彼は成人だが……。
おだやかさもそのまま湛えていて、すり、と胸に懐いてくるいとしい子。たまらずひたいにキスを落とすと、そこじゃない、とかわいらしくくちびるが尖る。
「ん……♡ はぁ、む……」
目覚めたばかりの身体はまだまだあたたかくて、口内となればなおさらだ。
ふわふわとしたロナルド君は、ふわふわのままキスに応えてくれる。かわいいな。口の中で私がおこなう狼藉に、不満や反抗はみられない。
ちゅ、とわざと音を立ててくちびるを離せば、彼は顔を真っ赤にしていた。
「ぷぁ……♡ は、ふ……」
「ふふ……。かわいいな、ロナルドくん」
「ん……なあ、ベッド……」
「うむ、エスコートしてあげよう。でもセックスはしないからな」
「は?」
まだまだ眠そうにしていた彼のひとみが、急に芯を取り戻す。
そりゃあ私だってさァ、ふわふわとろとろ寝起きルド君とまったりスローセックス、というのがやりたくない訳じゃない。いや、むしろめちゃくちゃやりたいほうだわ。しかし、今の彼にそんなことをしたらいけないのもまた当然。爪を磨かれた程度で、人間も吸血鬼も寝落ちる訳がないんだ。彼が自覚のないまま限界状態にあるってこと、それはつまり全力で彼を休ませなければならないということである。
「な、なんで」
「君はいまセックスできるようなコンディションじゃないだろ? もちろん、来るとわかっていたからベッドメイキングは完璧だ。安心したまえ」
「そ……、いや、そんなことない。元気だ」
「元気な子はすこし気を抜いた程度で眠ったりしないのだよ」
それに、私が軽くなってることにもいまだ気付いてないだろうし。
「なあ、ドラルク……」
「ダメだよ。ほら、君から降ろしてくれ」
「……、せ」
「せ?」
彼の腕は眠る前とおなじく、いまだ私の腰に巻きついたままだ。ほどかれないと、膝から降りることができない。
彼はなにかを言い淀んで、かあと元から赤くなっている顔をさらに赤くした。
「せっかく……。おまえにもっと、甘やかされたいって、思ってたのに……」
「……こ」
このバカ〰︎〰︎〰︎……ッッッ!!
こいつ、私が我慢してる訳じゃないと思ってからに! やりたくないからだとか、ぜったいそういう勘違いしてやがる……ッ!! ああダメだ、口調が荒くなってしまう。
「ゆ、指だけでいい……。挿れなくていいから、なあ、それならさ……」
「ッき、……君に触れたくない訳じゃない。不安にならなくていいんだ。まずはそう、ゆっくりおやすみ。な?」
挿れたいに決まってますが〜!? ふわふわとろとろの君の内側に迎え入れてほしいですけども!!
私の台詞はただ宥めるためだけのものだと届いているのか、彼はなおも「高望みはしない、触ってほしい」と繰り返した。私だって触りたいとは思っているのに!
彼の両手は腰から離れるどころか、むしろ背まで上がってすがりついてきている。かわいい。クソーッかわいいって思っちゃいまはダメなんだってば!
「ドラルク……」
「うぐ……ウググググ」
絶世の美丈夫渾身の上目遣い、効く……ッ!!!!!!
私があんまりかわいいかわいいと言い続けたからか、マジでロナルド君がかわいくなってきている気がする。いや、かわいくないのにかわいいと言っていたって訳じゃもちろんないが……こう、彼がかわいこぶるようになったというか……。
きゅうと眉根を寄せる、しょぼくれた表情。彼のいう『ロナルド様』であるならば確実にしない表情だ。それはつまり『ロナルド君』の表情だ、ということであり……私がずっと見たかったものでもある。しかし、そこに私の誘導がまったくないとは、残念だが言い切れないのだ。本人に自覚があるかどうかもわからない。
私は結局、私の願うように彼を歪めているに過ぎないのかもしれない――それを、忘れてはいけないと思う。
「……ロナルドくん」
「ん」
「私は君が好きだよ。愛している。だから君が心配なんだ」
「……んん」
「一度横になってみないか? どうしても寝れなかったらやぶさかじゃないけど……休んで、また次に起きたら、そのときにする、そうしよう。な」
「……、……」
むに、とくちびるを歪めてしばらく考えていた彼は、ゆっくりとうなずいてくれた。
「……寝るまでそばにいてくれるんなら」
「もちろん! ああごめん、大きい声出ちゃったな。君のパジャマを持ってくるよ、降ろしてくれたまえ」
するりと彼の両手がほどけていく。左手を捕まえてその甲にキスを落としてから、待っていてくれ、とささやいた。彼はひとこと、バカ、とつぶやく。
彼が泊まってくれるという予定は先にわかっているから、ベッドメイクは完璧だ。ふわふわになっているパジャマをとりに、私はクロークへと向かった。
コト、と棺桶の蓋が開けられた。
私のそれは最新式の棺桶で、オートロックがかけられるようになっている。しかももしもの時のために、サブ端末を設定できるのだ。当然、そこにロナルド君の端末が登録されていた。
——寝るまでそばにいてほしい。
私としては起きるまでそばにいたいところだったんだが、それはいい、と言われてしまう。まだまだ日が昇るには時間があったから、自由に過ごしてほしい……、と。
身体を重ねる、という要求をひとつ蹴っている訳だから、健気な彼のことばに私がうなずかない理由はない。きっと彼は日中起きるだろうから、朝食を作り置きする、など有意義に過ごしたよ。そうして私は棺桶に戻った。彼の隣に潜り込んでもいいと思いもしたけど、それで起こしてしまうのはいやだったんだ。
さて、現在に戻って、彼が棺桶を開けた訳だが……私はまだまだ眠くて、まぶたを開けるのが億劫だった。せめてどうしたんだい、とぐらいは声をかけてやりたいのに、まともな声が出る気もしない。彼が活動するために必要なあかりを、ぼんやりと薄くまぶた越しに感じることしかできなかった。
する、と頬を撫でられる。あたたかな手のひら。ヒト特有の熱。
彼は静かだ。棺桶を開けてから、まだひとことも発していない。頬を撫でる手にも、私を起こそうという気は感じられなかった。むしろ、起こさないよう慎重になって、すり、すり、とかたちをたしかめているようだ。
それが離れて、棺桶が軋む。
なんだろう、と思っているうちに、くちびるへやわらかなものが触れた。いや……きっとこれは彼のくちびるだ。やわらかく吐息も触れる。なにかを惜しむみたいに、それはゆっくりと離れていった。
ロナルド君が自分からキスしてくれることなんてそうない。うれしくて小躍りでもしながら抱きつきたいと思っているのに、身体はまだ動かなかった。
すう、と彼が深く呼吸をする。それから、ロナルド君はこう言った。
「……じゃあ、な」
その瞬間、急激に脳が覚醒するのがわかる。じゃあな。それは別れのことばだろう。
なにか用事があるだけのことかもしれない。でも、それなら叩き起こしてくれてもいいはずだ。私が起きないように、だけど顔を見て、触れて、別れを告げる。そんな必要、ないはずなんだ。
急に起き上がった私に、彼はかなり驚いたようすだった。声も出ないままあんぐり口を開けて、深海のようなひとみを見開いている。
「――おはよう、ロナルド君」
「あ、え……おはよう……」
「目が覚めるのが遅れてすまないね。朝食はちゃんと食べたのかい」
「ん、うん……おいしかった。皿、洗ってある」
「洗わなくていいって言ってるじゃないか……でも、ありがとうな。口にあっていてよかったよ」
「お前の料理、まずいことないだろ」
会話だけならいつもどおりだが、彼の目線は私に合わない。時折ようすをうかがうようにこちらを覗いては、すいと逃げるの繰り返しだ。
私は棺桶を出る。彼が床に座っていたから、私もそうした。私だけがふかふかした寝具の上で、彼はつめたい床の上、というのがいやだったんだ。
「……ロナルド君」
「……、」
「じゃあな、って、どうしたんだ。仕事が入ったりした?」
「……あ……」
さ、と彼の血の気が引く。
昨日は素直に甘えてきて、かなり調子が良さそうだったんだが……。
「き……、昨日」と彼は声を絞り出す。「おまえに、……我がままを、言い過ぎたと、思ったから……」
「うん」
「帰って……。頭を冷やそうと、思って……でも、挨拶しないのも、失礼だと、……思って……。寝顔見たら、起こすほうが悪いかもってなったから、……」
「……、そっか。そうか」
彼をそうと抱きしめてみる。予想に反して彼は逃げも暴れもしなかった。ただし、抱き返してももらえないが。おたがいにパジャマだから、すごく心地がいい。
「ほんとはさ、棺桶が開いた時に起きてたんだ。眠くて声がかけられなかった。すぐ目を開けてあげられなくてごめん」
「え、あ……。いや、俺が起こしたのが……」
「私はまったく気にしていないよ。城を出る前に顔を見にきてくれたのもうれしい。君からキスをしてもらえたのもうれしかった。次は起きてる時にしてくれたまえ」
「……、……わ、かった……」
些細なことが、彼のなかで失敗に置き換わる。失敗はトラウマに置き換わって……彼の胸をぎりぎりと痛めつけてしまう。記憶力のよさは仕事にも活かされているが、彼にとってはデメリットのほうが多い気がするよな。そのぶん、ある程度文字として吐き出しているというだけでだいぶマシだ。
九九九、現在はそれ以上の退治。
それはつまり九九九、現在はそれ以上の被害があるということだ。それのすべてを彼がひとりで背負うなんて――間違っている。
書籍が『うまくできた』部分の抽出に過ぎないとしても、それが認識できている、ただそれだけで素晴らしいことだし……抽出がうまくできないから、締切に追われてしまうのだ。ロナルド君がいちばん悩むのはプロットの部分である。
「いいかい、ロナルドくん。君は我がままを言う権利がある。それは悪じゃないよ」
彼はなにかを言おうとして胸をふくらませたが、結局ただの吐息として吐き出した。その背中をゆっくりと撫でてやりながら、もう一度いいんだ、とつぶやく。
「大丈夫。君はなにも失敗なんかしていない。もっと甘えてもいいくらいだ」
「……ドラルク」
「嘘じゃないよ。君を甘やかしたいんだ。仕事なら仕方ないし我慢する。だけど……そうじゃないなら、一緒にいられるギリギリまで、ここにいてほしい」
腕のなかのあたたかな身体が、やわらかくなっていくのがわかる。とろり、と私に体重をあずけて、彼はわかった、とうなずいてくれた。
「よかった。……目が覚めたし、着替えようか」
「あ、いや……時間が」
「うん?」
彼が差し出した端末には、一一時の表示が出ていた。たしかに、時間がまずいなァ。とはいえ、これで二度寝するからと彼を放置するのも気が引ける。
「じゃあ、日が落ちるまで一緒にダラダラする?」
「一緒に?」と彼は首をかしげた。
「うむ。棺桶のなかでダラダラしよう」
「……でも、狭い、し」
「そりゃそうさ、棺桶だからな。一度君も入っておいでよ、人生経験として」
どうせ転化したら毎日入ることになるんだし……、というのはまだ早いか。いや、私はベッドで眠るのを否定する派閥じゃないけど。どちらでも、彼が選ぶほうでいい。
彼はしばらく、困惑したようすで私と棺桶を見比べている。
ソファで休むのでもいいよ、と助け舟を出すのはかんたんだ。だが、自主性までを奪いたい訳ではない。いやならきちんと否定してほしいし、やってみたい、とほんのすこしでも思ってもらえるなら、いくらでもやってみてほしいのだ。
根気よく待つと、ロナルド君がゆっくり口を開く。
「……狭くて死んだり、しないか」
「どうだろうな。君と密着できること自体はとてもうれしいと思うけど。とりあえず入ってみてから考えてもいいかもしれんね」
「とりあえず……」
入ってみるかい。
そう声をかけてしまったのは、やっぱり我慢が足らなかったな。彼はうなずいたが、果たして彼の意思だっただろうか。
私が手振りで示すと、ロナルド君はゆっくりと棺桶に身を沈める。見よう見まねで身体をよこたえて、ほう、とため息をついた。
「意外と広いんだな」
「うむ。寝心地もいいだろう?」
「うん……」
でも、もうひとり入るのは無理じゃないか。そう見上げてくる彼のひとみはやはりうつくしい。さっき彼がしてくれたのとおなじように頬を撫でたいしキスがしたい、そう思わせるにじゅうぶんだった。
そんな欲を押し込めて、私も棺桶に向かう。ロナルド君は思いっきり身体を寄せて、なんとかスペースを生み出そうとしていた。そこまでしなくても大丈夫なのに。
「ほら、寝れた。まあ狭いは狭いけど」
彼はああ……、とうなずく。軽く腕を叩いて、枕にさせてくれよ、とねだってみた。ぎくしゃくと伸ばされた腕にそっと頭を乗せると、彼がほっとしたような息をつく。
「あんがい大丈夫なものだろう?」
「そう……、だな。おまえのにおいがする」
「私の?」
「臭いって言ってる訳じゃない。いい意味で」
「そ、そうか。ヴァブリーズとってくるべきか悩んだよ」
「そんなことしたら湿気て眠れないだろう」
言いながら、彼が目を閉じる。私もすっかり目が冴えたつもりだったが、目の前でいとしい子が眠ろうとしているすがたにつられたのか……ふわりと眠気が戻ってきた。私にはまだまだ睡眠時間が足りないのだ。ただでさえ吸血鬼は人間より長く眠る。
「やばい。寝ちゃうかもしれん……」
「いいよ。日が落ちたら起こす」
「いや……、そのすこし前、がいいな。……それなら、日が落ちてすぐ、……動けるから……」
「わかった」
私が眠気でバカになっているのでなければ、彼の口調がしっかりしている気がする。気鬱からすこしは抜け出せたんだろうか。結局ひとりにしてしまうけど、さみしくはないだろうか。それとも、一緒に眠ってくれるのだろうか。
どんな表情をしているか確認してやりたいのに、目が開かない。
「ろなるど、くん……」
「ん」
「棺桶、出ても……いいからな……。君のしたいことを……、していていい……」
「わかってる。……起こして悪い」
「ちがう……ちぁ……」
違うんだ。
私はすごく、うれしかったよ。
そう伝えたかったのに、意識は私の言うことを聞いてくれなかった。
□■□■□
手持ち無沙汰は苦手だ。思考がぐるぐると回って、俺はそのハンドルを握れない。制御不能のコーヒーカップに乗っていたって酔うだけだ。
それでも、ドラルクのおかげですこしだけ気は楽になった。起こしてしまったのは誤算だし、申し訳ないとも思うけど……思ったよりも、昨日のやらかしは大きい問題ではなかったみてえだな。ドラルクのようすはいつもどおりだったから。
ドラルクの用意した朝食で腹も膨れているし、二度寝しようと思えばできなくない。けど、場所がドラルクの棺桶なばかりに落ち着かなかった。昨日燻った熱を思い出し、腹がもぞもぞする。しばらくは努力したけど、寝付くのはやはり難しそうだ。
ゆっくりと腕からドラルクの頭を下ろす。かわりに枕をいれてやる。
起こさずに済んでほうと嘆息してから、俺はゆっくり起き上がった。棺桶を出て、したいことをしていていいと言われている。俺にわざわざするような『したいこと』なんてないけどな。結局、昨日中途半端なところで放り出していた原稿の続きを書くことにした。筋書きが仕上がったからあとは書くだけなんだ。単純に文字数の関係で時間がかかるだけで、悩むことはないから……集中力さえ続けばなんとかなる。
いつもこうならいいんだけどなあ。
蓋を閉めてやるべきか悩んで、開けたままにしておくことにした。起きたらすぐに声をかけてやりたいからだ。ドラルクがそれを望むかどうかはわからねえけど……、でも、したいことをしていていいと言われた、から。
言われたとおりにするんだから、きっと怒られない……、はずだ。
かぶりを振る。不安になったら、日が暮れるすこし前に棺桶へ戻るのもいいだろう。いまはとにかく仕事をしよう、とワープロソフトを起動した。
腹が空いて時計を確認したら、一八時だった。また昼飯食うのを忘れたらしい。
日が落ちる前に起こせと言われたのを思い出す。ドラルクはまだ眠っていた。
棺桶を開けたままだから騒音に気を配ったが、そのおかげか起こさずに済んだかな。目が覚めても、起き上がらずにいてくれただけなのかもしれないが。
パソコンを閉じて、棺桶の前にひざまずいてみる。昼にやったように頬を撫でて、感触を確かめた。今回は起こしていいので、あそこまでおそるおそるではなくだ。
ドラルクは細いし、皮が余っていない。急激に痩せたんじゃなくて、過去に一度も太ったことがないんだろうな、と予想している。本人に聞いた訳ではねえというか、体型みたいなことはセンシティブな領域だから好奇心だけで聞かないほうがいいよな、と思っていた。
ええと。ドラルクは、俺の肩を叩いて起こしたよな。
とん、と軽く叩いてみる。とはいえあまり強く叩くとドラルクを殺してしまいそうだし、なるべく弱い力加減からスタートした。ぽふ、ぽす、とすこしずつ力を込める。
しばらく繰り返して、ようやくドラルクがううん、と唸った。
「……ロナルド君?」
「ん。おはよう」
うん、という返事はふにゃけていて、いつもの紳士然とした喋り方とはまるで別人みたいだ。かわいいな、と思う。俺も昨日こうなっていたなら、すぐにセックスだ、とはたしかにならないかもしれねえ。いや、すぐにキスはされたんだったか。
ドラルクはしばらくぼうっとしていたが、やがて意を決したように起き上がった。
「起こしてくれてありがとう、ロナルド君。おはよう」
「いや。時計見てなくて、ちょっと遅くなった」
「大丈夫さ。私が寝てる間、ちゃんと水分摂ったりしたか?」
「ああ。レモン水もらったぞ」
それはよかった、そんなことばと一緒に頭を撫でられる。はるか歳下なことくらいわかっちゃいるが……。
ドラルクは棺桶を出て、俺のとなりに座った。つまり床だ。ソファに上がろう、と声をかけるより先に、ゆるく抱きしめられる。
ドラルクの腕のなかは安心するんだ。そういうふうにしつけられてしまった。腕は細くて頼りないけど、骨格がしっかりしているから胸が意外と広い。背中をまるめてそこになつくと、なんだか赦されているような気分になる。よしよしと撫でられても、不服さはなかった。
「昼のあいだ、なにしてたんだ?」
「原稿。まだ終わってないけど、だいぶ進んだ」
「そうか。休んでいてもよかったんじゃないのか?」
「お前と休むからいい」
そのぶん早く寝たようなものだ。
ドラルクはぐ、と息を詰めてから、そうだな、とつぶやいた。……だめだったか。
「ええと、いま何時かな。おやつは食べた?」
「一八時。食べてない。ちょっと腹減ったかも」
「そうかそうか。じゃあまずは晩御飯からだな」
昼飯食ってないんだ、というのは伏せておく。怒られそうだろ、そんなの。
でも、もうすこしだけ。そう言って、ドラルクは俺を抱きしめなおした。
やさしい手つきに、すきだな、と思う。いまはまだそれでいいはずだ。ドラルクにいつか、もういらないと言われるまでは。
『ロナルド様』のふるまいと、昨日みたいな失敗を重ねて、そのうち俺は嫌われる。でも、そうなるまでは……いいはずなんだ。
施しは、いつまでも続くものではねえ。
いつかドラルクが、ドラルクのために誰かをあいする日まで。
「……ドラルク」
「うん?」
「その……」
ドラルクの声音はやわらかい。やわらかいから、伝えるのをためらってしまった。べつに、伝えなくてもよくないか。言われたって面倒なだけかもしれないのに。
言いたい、とたしかにあった気持ちがしぼむ。
俺にすきだなんて言われても、ドラルクは困るだけだろう。
「……、」
「ロナルド君?」とドラルクが俺を覗き込もうとする。
俺はドラルクの胸に顔を押し付けて、ぜったいに見られないようにした。
「――晩飯……動いてねえから、あんま食わない、たぶん」
「ん、わかった。ずっとここで原稿してたのか?」
「ああ。ずっとって言っても、仮眠したりもしたけど」
ドラルクが起きたあと、また早く寝ちゃったらもったいないしな。
進んだようでなによりだよ……そう言うドラルクの声音が甘くて、褒められているみたいな気分だった。
君ならできるだろう。
そう言われると、胸が脈打つ。やってみせるという気持ちになる。
だから俺は、役に立たないとわかっていても、ドラルクを退治に連れて行くんだ。
晩飯とおやつが半々、みたいなメニューをみんなでたいらげる。軽食って言うのか。照り焼きチキンのサンドイッチ。ジョンもツチノコもおいしそうにしていた。
こういうとき、かぼちゃがなにも食べられないのはかわいそうだな、と思う。口を彫ってやるべきだった。正直、うまく吸血鬼化するとは思っていなかったんだ。
つるつるの表面を撫でてやると、かぼちゃはうれしそうに微笑む。
「頭をいっぱい使っただろう。デザートだよ」
そう言いながらあれが用意したのは、小さく切られた冷凍スイカだった。ごろごろフードプロセッサにスイカ、練乳とレモン汁をぶちこみ、ガーッと粉々にするだけ。ずいぶん手軽なアイスだ。
「君にも作れそうだろう? 包丁は使えるんだし」
「まあ……。でも俺、種とかとるの得意じゃない」
「まさか。手先が器用な人間にしか銃の手入れなんかできないだろ」
塩をかけてもいいし、練乳足してもいいよ、とはジョンの弁である。夏場のきまりらしい。ジョンがまっさきに飛びつくあたり、きっとおいしいんだろうな。
「君には出したことがないなと思ってさ。さ、食べてみてくれ」
「ありがとう。いただきます」
しゃりしゃりとやわらかい食感。こういうタイプのアイス、なんて言うんだったか。サンドイッチの味が濃かったから、口の中がリセットされる感じもする。ドラルクは自分に味覚がほとんどないくせに、こういう組み合わせをよく思いつくよな。
無言で食べ進めていると、おかわりも作れるよ、とあれがにやついて言う。
「スイカの冷凍ストックはまだまだあるからな」
「……食べたくなるからやめてくれ」
「食べていいって言ってるんだ」
「……、」
無言で皿を差し出したら、声をあげて笑われた。
食器を一緒に片付けて、一息。
お客さんなんだから君は仕事をしなくていいんだ、とはよく言われるけど、そんな理論を通すなら俺の家にドラルクが来た時はどうなるんだって話だ。お客さんであるはずのドラルクが結局家事をやるし、あれは調子がいいので「これは泊めてもらう礼だから」などとのたまう。なら、俺だって『泊めてもらう礼』として皿洗いをしても問題なんかないはずなのにな。
今日は結局、「朝は皿洗いしてくれたんだろう?」というドラルクに押し切られて、流しまで運ぶことしかさせてもらえなかった。昼食を抜いたのがバレている。まあ、痕跡がないんだからしゃあねえか。
ソファに並んで座る。大きな間隔を空けず、むしろぴたりと寄り添って。する、と細い腕が俺の腕に絡んでくるから、すきにさせる。
ふふ、とドラルクは上機嫌に笑っていて、よかったな、と思う。昨日のことなんかドラルクはほんとになんにも気にしていないのかもしれない。……それは、その気がない、という意味でも。起きたらしよう、たしかにそう言っていたはずだ。
でもまあ、それでよかった。セックスが目的で付き合っている訳じゃない。あれがやりたいことをやるべきだし、やりたくないことはやらなくていいんだ。
「ロナルド君、今日はまだ仕事があったりするかな?」
「いや……思ったより、原稿ちゃんと進んだんだ。このあとゆっくりするぐらいなら、大丈夫だと思う」
「いいな、優良進行じゃないか。褒めてあげよう」
「うるせえ」
ドラルクはほんとうに俺の頭を撫でてくれたし、俺は口だけの反抗にとどめた。
だって。
「……昨日」
「?」
「おまえに、爪を削ってもらったおかげだと……、思う」
余計な気を取られないと、作業に没頭できる。それはたしかに、ドラルクのおかげだと思うから。
ドラルクは虚を突かれたように固まったが、やがてゆっくりと破顔した。
「よかった。君の役に立てて」
「……ありがとう」
ドラルクに大事にされると、眠くなる。
勘違いしすぎないようにしないといけないって、わかっているのにな。
身体はもうとっくに、ドラルクの手に堕ちている。心がなんとか踏みとどまって、依存しきらないように意識できているだけだ。それもいつまでもつものか。
ドラルクがすきだ、と思う。
だから……負担にはなりたくない。
ドラルクはきっと許すだろう。だからといって、そのおこないが善だとは限らない。みずから進んで地獄に落ちるバカはいないんだ。ただ、行き着く先が見えてないだけ。なら、しかるべきところで引き留めるのが俺の役目だよな。
「次来るとき、爪切り買ってくる。借りてる部屋に置いてもいいか」
「え? いいけど……、次は削らせてくれないのかい」
「毎回お前の手を煩わせはしねえよ。置くのが難しいなら荷物に入れておく」
「いや! 手間じゃない。手間じゃないから、爪切りは買わなくていい。これからは私が君の爪を整える、そういうことにしよう。な?」
「……ドラルク」
またはじまった。
ドラルクはなぜか、俺の世話に執着する傾向がある。そういうのはいい、と何度も伝えているが、結局押し切られることばかりだ。皿洗いひとつにしたってそうだろう。
「ほんとうは爪切りもあるんだ。貸し出すのも問題はない。でも、どちらかというと私が君を整えたいんだよ。だから、これからも君の手入れをさせてほしい」
「そこまでする価値なんか俺にはないだろう。撮影の仕事の前とかならわかるけど」
「あるよ。私は君が大事で、君を愛していて、とくべつあつかいがしたいんだ」
「……、」
ドラルクの目は真剣だ。他意はないんだろうと思うし、からかっている訳でもない、というのはわかっている。わかっているけど……それでも、理解ができなかった。
ドラルクが俺の手を握る。爪のさきにくちびるを落として、頼む、と言った。
「おねがいだ。君を手入れさせてくれ」
「……、……」
ドラルクはたぶん、俺がそう遠くないうちに死ぬってわかっちゃいないんだ。
この仕事をしていて、長生きできるはずはない。吸血鬼の被害は確実に減っているといえど、ゼロになった訳じゃ当然ないし、俺の仕事は無くならないんだぞ。たぶん、ドラルクは人間の寿命がよくわかっていないんだよな。腹が裂けたらあっという間に死んじまうことも。
「おまえ、そうやって俺にばっかりこだわるなよ。俺がいなくなったらどうする」
「いなくならせたりしないよ。ぜったい捕まえてやるからな」
「そうじゃなくて……」
刺激の強い言葉を避けたら、うまく伝わらなかった。
「そうじゃなくない。私は君を失うつもりなんかないんだ。死なせないし、ひとりになんか戻してやらない」
……と思ったが、伝わっていたらしい。
「時間なんていくらでもあるんだ。私は君と永遠を過ごしたいと思っているからな」
「永遠?」
「そうだ。君を転化させたいと思っている」
「は……」
さらりと告げられたことばに瞠目した。
転化。永遠を過ごす。
責任が取れないならペットを飼うな、という理性的な教訓は吸血鬼にはないのか。いや、ないな。今まで倒してきたヤツらからして。
「いますぐに応えろとは言わないさ」とドラルクは殊勝ぶって言った。「君の準備が、きちんとできたらでいい。私も君のための毒を練らないといけないし。ただ、」
祈る神なんかいないくせに、俺の手を両手で抱えたドラルクは、敬虔な表情をして目を閉じる。
「これは私のことしか考えていない提案なんだ。ただ、私はわたしのためだけに……君を手に入れようとしている。君たちの基準だと、これも敵性に入るかい」
「……いや。思想は自由だから……むりやり咬みついてこない限りは、べつに……」
「そうか。よかった、君と敵対する訳じゃないんだな。君と一緒にいたいだけなのに、そうあれなくなったら意味がないから怖かったんだ」
「……、おまえって」
「うん!?」
ずい、と身を寄せてきたドラルクが若干怖いが、走りだした口は止められない。
「俺のこと、すきだったのか?」
「は、……ハァ!!!???」
「あ……いや、そういう意味じゃなくて……」
説明が難しいんだよな。べつに、ドラルクは俺に興味がないとまで思っているって訳じゃない。ただ……、ドラルクが「わたしのため」と言ったのが信じられなかった。
「俺がそばにいても、おまえに得なんかないだろう。世話をしなきゃいけなくなる。たまにだから面白いだけで、毎日やりたいことじゃないと思ってた」
「んな、……はぁ〰︎〰︎〰︎……」
「だって……なにかの世話をしたいだけならジョンでじゅうぶんだろう。なんだって、俺がいることがおまえのためになるんだよ」
「そりゃあ当たり前だ。私は君の世話をしたいと思っているからだ!」
「ヒトの世話がしたいなら、もっといい相手がいると思うぞ」
「ヒトなら誰でもいいなんて思っちゃいないよ。私は君だから手を伸ばしている」
「俺だから……」
「君が聞いたんだろう。そうだよ、私は君が好きだから、君のお世話をしたいんだ」
顔が熱い。顔っていうか、目のあたりが。鼻もつんと痛む。
「……うまく伝えてくることができなくてごめん。ごめんな。大好きだよ、愛してる。だから、転化のこと、前向きに考えてほしい」
「……皿洗い」
「へ?」
「皿洗い、すると怒るのも、世話がしたいから?」
「おこっ……てはないけどな!? でもたしかに、そうだな。君が食事をしてくれた、そのよろこびを皿洗いで噛み締めたいというか」
「なんだそれ……」
なんだそれ。
じわりと滲んだ涙を、ドラルクが手袋で吸い上げた。
ドラルクは、俺をよく抱きしめる。いまもまた、その広い胸に抱き込まれていた。ゆっくりと髪をすきながら、すきだよ、すきだよと繰り返す。
ドラルクのための恋をしてほしい。
その気持ちは変わらない。俺がそれになれると思えた訳でもない。なのに……俺がそれだと言われたことが、どうしようもなくうれしかった。
ゆっくりと深呼吸をしてから、口を開く。
「爪……」
「爪?」
「赤いの、俺にも塗って。どうせ外じゃ、手袋外さねえし」
「え、ああ! もちろん。でも、君に塗るなら紫がいいな。うちの一族の色なんだ」
「一族の色?」
もぞりと顔をあげると、ドラルクはやさしい表情で俺を覗きこんでいる。ちょっとビビった俺に苦笑してから、あれはうなずいた。
「吸血鬼は血族主義だ。だから一体感とかを持つために、けっこう『うちの一族ならコレ!』みたいなものを決めるんだよ。で、うちの色は紫」
「へえ……」
「マニキュアはそもそも血色の悪さを誤魔化すためのものだから、みんな赤にする。紫はほら、スーツに使っているだろう?」
「ああ、そういえばそうか。マントも裏紫だよな」
「そう! 見ていてくれてうれしいよ」
君の肌にはどんな紫が合うだろうな。そう言うドラルクは楽しそうで、よかったな、と思った。爪を塗ってほしい、というのは間違った希望ではないようだ。
「……あとさ」
「うん?」
なんでも言いたまえ、と大人ぶったドラルクの腕から抜け出す。さみしそうな顔のくちびるに、自分のそれを重ねてみた。
「……え」
「……起きたらするって、言ったよな」
ごくりと息を呑んだのはどちらか。
ドラルクのセックスはちょうどいい。
痛いことはぜったいされないし、きもちいいのが苦しいぐらいになったら休ませてもらえる。脳みそが心地よくとろけて、なにも考えなくていいのにきもちがいい。
任せきりで申し訳ない気もするけど、向こうも満足そうだし……そういうのがいい、とドラルクも思っているのだと今日知ったし。罪悪感なく任せられるようになると、こっちもなんか前よりきもちがいい気がする。
地下の温泉で汗を流して、湯船にふたりで並んでいた。アイスティーを持ち込んで、水分補給しながらの長風呂だ。セックスでへんなところの筋肉が凝っている。それをあたたかくほぐすのにちょうどいい。
「ロナルド君、やっぱりちょっと髪伸びたよな」
「んん? そうかもな。濡れて下りてるだけじゃなくて?」
「自覚ないのかい? ほら、耳がもう隠れそうだよ」
「鏡ねえからわかんねえよ」
「はは、たしかに」
ちゃぷちゃぷと湯を揺らしながらたわむれる。
ドラルクはすこし黙って、真剣な表情を作った。
「髪も切りたい」
「?」
「爪と同じでさ、君の髪を私が整えたいんだ。吸血鬼になると、そういうのの発育も悪くなるというか……あまり意識しないと伸ばせなくなるんだよな。だから、勝手に伸びてくるうちに、整えることをしたい」
「俺、まだ転化するなんて言ってねえけど」
「わかってるよ。でも、君が転化せずに死んじゃったら、それこそ二度とできない。だからいま、やらせてほしい」
「……、……まあ……」
床屋にこだわりがある訳じゃないというか、むしろ自分でテキトーに切ってるだけだしな。ドラルクに任せたほうがむしろ失敗がなさそうではある。
髪をいじっていた手でそのまま俺の頭を撫でているドラルクに、ほんのすこしだけ身を寄せた。うれしそうにもう片方の手で抱きしめてもらえる。
「前髪短いのはいやだ」
「わざと伸ばしてたんだ?」
「まあな。目があうの、あんまり得意じゃないから」
「え!」
「ん?」
なんだそのデカい声は。
ドラルクのようすをうかがうと、なんかマジでショックを受けた顔をしている。
「ドラルク?」
「わ……私、けっこう君の目を覗きこもうとしたりしちゃってたぞ。大丈夫なのか」
「え、ああ、いや。おまえはもう慣れたけど、依頼人って基本みんなハジメマシテのひとばっかりだろ。人見知りなだけ」
「あ、あ〜……そういう……」
たまに下等吸血鬼の巣が再発して……って人ぐらいだもんな、リピーターって。
しかもみんな『ロナルド様』が目当てだから、やたらキラキラ輝いた目をしている。ふつうにあてられてしんどい。そういう依頼人の目なんか、自分の髪越しじゃないと見るのがつらいんだ。帽子を深く被り、格好つけて顔を逸らすと、そういう視線から逃れられやすいので助かっている。
そういうことを説明してやると、ドラルクはずいぶんほっとしたようすだった。
「ほかには? 私が君にしていて、いやだなと思うことはないのかね」
「ほかに……? べつに思いつかないな。よくしてもらってる」
「ほんとか? すこしでもいやだと思ったらすぐに言うんだぞ。ぜったいだぞ」
「そうやってしつこいとこ」
「ウグー!」
アイスティーをひとくち。つめたくてうまい。
俺はこれがあるからいいけど、ドラルクはどうだろう。
「おまえ、のぼせてないか。もう上がる?」
「うん? かなりぬるくしてあるし、まだ大丈夫だ。ありがとう」
「そうか……」
吸血鬼のほうが体温は低いから、俺よりも湯を熱く感じているはずだ。大丈夫とは言ってるけど、表情とかよく見ておいたほうがいいかもしれねえな。
そんなことを考えながら、もうひとくちアイスティーを飲む。おいしい。ほんとは酒を飲んだりするものなんだろうな、温泉だし。
明日の朝には帰らないといけない。ドラルクが寝たら城を出て、自宅で寝て、翌夜取材の予定が入っている。前後でどれだけ原稿が進むかどうか。
「君、いま仕事のこと考えてるだろ」
「ん゙」
「表情が硬い。考えるなとは言わないけど、忘れるときがあってもいいと思うぞ」
「ん〜……」
……見られているのは俺のほうだったらしい。
ぐ、と腕を伸ばしてみる。たいしてなにかを守れる訳でもない腕だ。でも、取材を受けるのは『ロナルド様』だから、明日は百戦錬磨のスペシャリストに成らなければいけない。
でも、いまはべつに俺でもいいんだよな。いまはドラルクのとなりで、俺もあれも裸で、衣装なんか着ていねえんだから。
「ドラルク」
「うん?」
「あがったら髪、切ってくれるか。明日の仕事、話だけの予定だけど、もしかしたら写真も撮られるかもしれねえから」
「! もちろん!!」
ぱあ、とあれの顔がほころぶ。
それに俺は安心して、よろしく、とささやいた。
あるおだやかな日

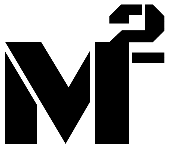
コメント