――かぜひいた。
目覚めてすぐ確認したあまりにも端的すぎるRINEの内容に、危なく端末を取り落とすところだった。もしも顔面に落としていたらとんでもないタイムロスである、あぶないあぶない。棺桶でゴロゴロしていた私はすぐ起き上がり、ジョンへと協力を要請した。頼もしい丸はどんと胸を叩く。
すぐに行く。そう送信すれば、ありがとう、と返ってきた。無理に返信しなくてもいいから寝ていてほしいんだけどな。
ジョンに用意してもらったブラッドボトルをひっくり返してひとっ飛び。
もう何度も飛んだルートはすっかり覚えている。それでも彼のことが心配すぎて、うまく飛べている気がしなかった。だってさ、あのロナルド君が自分から不調を連絡してくる、なんてことが信じられないんだ。ものすごくつらい状況なんじゃないか? そんなときに、私はどれだけ力になってやれるのだろう。
逸る気持ちを抑えて、紳士に、真摯に。
「ロナルド君、来たよ」
「ああ……」
合鍵はもらっている。
インターホンを鳴らしがてらゆっくりと玄関を開けると、もぞもぞと起き上がっている気配。ぱたぱたとスリッパを奏でながら出てきた彼の手には、ペットキャリーが抱えられていた。
ペットキャリー?
「よが、った。ゲホ……ノコと、かぼをさ、見ていてやってほしくて……」
「……はい?」
「ちょっと……ごはんとか、やってやれなさそうな気がするからさ……」
……これは……。
いや、まあ、うん。あのロナルド君が連絡を、とたしかに思ったさ。思ったけど、こうも彼がいつもどおりだとは思わなかったというか……。
「ハァ〰︎〰︎〰︎……」
「?」
首をかしげた彼の表情をうかがってみる。
頬は紅潮し、ひとみもうるんでいた。それだけなら扇状的ともとれるのかも、とは思うけど、その理由を知っていたらそんな目では見られない。身体の軸もふらふらとしていて、このまま立たせていてはダメそうだ。
「お説教はあとにしよう。部屋へ戻ってくれ、ロナルド君」
「お説教ってなんだよ。風邪ひいたぐらいで怒るなよ」
「違う。いいからほら、行った行った!」
ふだんの感じで軽く押したつもりなんだが、彼は力が抜けているし、私は血を摂取したばかりだし、でみょうに釣りあってしまった。ふらりと崩れた彼を慌てて支える。
「ほら。私に押されてぐらつくくせに、ひとりでいようとしない」
「う……」
ペットキャリーのなかからじたばたと暴れる気配がするのだって、彼にはよくよくわかっているはずだ。しぶしぶ彼は部屋へと向かってくれてほっとする。
テーブルの上でキャリーの扉を開放すると、一目散にツチノコが飛び出してきた。座ったロナルド君の膝に飛び乗り、『もう動きません』という意思表示をしている。
「ツチノコも怒ってるみたいだけど」
「んん……」
ノコ! と同調するような声。大人しくキャリーにおさめられていたのは、暴れてロナルド君を疲労させたくなかった、とかなのだろうな。彼にはわからないかもだが。続いて取り出したかぼちゃも、表情がひどく沈んでいる。
「ほら、かぼちゃなんか泣きそうだぞ。なんだってこんなことを?」
「……だ、って。……」
はく、と彼が空を噛む。はたして、そんなに言いづらいような理由なのだろうか。ツチノコはちょっと謎だが、少なくともかぼちゃはおそらく吸血野菜と思われるので、彼の風邪はうつったりしないはずだ。うつすと悪いから、という理由は成立しない。
けほ、けほ、と彼が咳き込む。背中を撫でても跳ね除けられなかった。
「我々には君の風邪はうつらないよ。素直に看病されてくれないのかい」
「けほ、……それは知ってるけど……しんどいだろう、看病って」
「しんどい?」
こく、と彼はうなずき、申し訳なさそうに言った。
「……他人がしんどそうなところって、見るだけでしんどい、だろ。多少……一緒に生活をしてるようなヤツがしんどそうだったら、もっとしんどい……」
「……、……」
多少一緒に生活をしてる、他人……。
看病なんかより、その言い様のほうがよっぽどひどい。ほら、びったんびったんとツチノコが尻尾で彼の膝を叩いているし。
「いた、いたい、ツチノコ?」
「当たり前だろう。享受したまえ」
「ええ?」
困惑している表情はかわいらしいが、その中身がこれじゃあなあ。また彼がひとつ咳をする。空咳ではなく、重たいそれだ。
「咳がかなり出るな。喉も痛い?」
「あ……ああ。けっこう……」
「はちみつが喉にいいらしいぞ。たしか君の家にはあったと思うけど、捨てたか?」
「いや……捨ててない、かも……?」
「かもか。探してみよう」
その捜索は一秒で終わった。最後に私が使った場所にそのまま置いてあったからだ。まあ、彼は自炊をしないし、捨ててないならばここにあって当然といえよう。確実に『使い切ってなくなった』という可能性は存在しない。
加湿を兼ねて多めに湯を沸かす。
「ほかの症状は? 熱はかなりありそうだな」
「ん〜……、ゲホ。頭、痛いかな。風呂も入れてない、し……」
臭くないか、と笑う顔には余裕がありそうだが、どちらかというと『ロナルド様』らしい、というほうが近い。彼にとってはまだ無理というほどではないんだろうけど……あまり起こしてばかりではよくないな。はちみつ湯を飲ませたら休ませるべきだ。
氷で湯温を調整したぬるま湯に、とろりとはちみつを垂らす。彼が猫舌なだけではなく、あまり熱にさらさないほうが栄養的にいいらしいよ。
彼に差し出すと、ありがとう、と微笑まれる。両手でうやうやしくカップを抱えて、じいとそのまま見つめていた。
いや、飲みたまえよ。そう思いながらも、私は向かいに座って語りかけてしまう。
「ロナルド君。まず、君が頼ってくれてうれしいよ。どんなかたちであっても」
「あ、……」
「私は君に頼られて、うれしいから、看病したくなったんだ。させられてる訳じゃあない。私の意思だ、わかるかね」
「……、ああ。わかる」
「よかった。……たしかに君が苦しんでいるところを見るのはつらいとも。だけど、だからこそ、早く楽になってほしいし、そのために看病ぐらいいくらでもできるんだ。ゆっくり飲んでくれ。そうしたら身体を拭いて横になろう」
「ん……」
ようやくカップを傾けはじめた彼を確認してから、私は洗面器を取りに向かった。
□■□■□
こんなつもりではほんとうになかった。
なかったが、うれしい、とも思っている。
正直、看病してもらう、という選択肢が頭のなかに浮かんですらいなかったんだ。あたりまえのようにドラルクがそうしたから、ちょっと驚いてしまってすらもいる。
はちみつを溶かしただけのお湯なのに、喉の痛みがだいぶ楽になった。不思議だ。端末で検索したら、喉の保湿をしつつ殺菌効果もあるらしい。つよ、はちみつ。
ついでにあたたかいから、ぼんやりと眠気もやってくる。
「おまたせ。飲めたかい」
「ん」
「いい子だ。寝室に行こう」
空になったカップを見せつけたら、ドラルクがやさしく微笑んでくれた。でもこれ、子どもあつかいだよな。撫でられながら思う。
ベッドに座ってパジャマを脱ぐ。ドラルクがきつく絞ったタオルで拭いてくれた。あれの力加減はやわらかく、ほふ、と吐息が漏れる。思ったよりもさっぱりとして、意味があるんだな、と思った。入院したときに看護師の清拭を受けたりもしたことはあるけど、怪我の時は発汗とかそこまでないもんな。
全体的に色素が薄いせいで、熱なんかで体温が上がると身体がピンク色になるんだ。なんか子どものままみたいで、ドラルクに見られるのがはずかしい。
「着替えを用意してくるから、股間は自分で拭いておきたまえ。下着も替える?」
「ん……あー、替えたいかも……」
わざわざ湯に通し、絞り終えてから渡されたタオルを受け取ろうと、して。
不意にドラルクの股間が視界に入る。
め……、めちゃくちゃ勃起、してる……!!
え? は? びっくりしてドラルクの顔を見たが、クソほど真顔だった。え???
股間はパツパツになるほど膨らんでいるのに、文字どおりおくびにも見せず、だ。俺がタオルを受け取らないから、頭が痛いのか、熱が上がってきたりしたか、などと心配そうな声を出している。いや、そう、じゃなくて、心配しているのかもしれない。
……でも、めちゃくちゃ勃起してる…………。
「あ……、アリガトウ……」
「……? 辛かったら言うんだよ。解熱剤とかは飲んだのかい」
「ん、あ、いちおう……。でも、メシまだだ。食後の薬もある」
「そっか。喉が痛いんだよな。こういうときはおかゆなんだっけ?」
「たぶん。さっきのでだいぶ楽にはなったけど、やっぱ唾液飲み込むと痛い」
「ふむ……。着替えを持ってきた後に作るよ。行ってくる」
「うん……」
めちゃくちゃ勃起してるのに……ほんとうにまったく気にしないようすで、あれが部屋を出ていった。
発熱が由来ではなく体温が上がった気もするが、頭痛も増した気がする……。これ、いますぐは収めるのを手伝ってやったりできないぞ。ドラルクもそれがわかるから、表情に出さないようにしてたのかもだけど……。
いや、そんなぼうっとしてる暇はないよな。さっさと股間を拭き終えて、洗面器にタオルを戻した。ドラルクもすぐに戻ってきたから、持ってきてもらった服を着る。ちょっと身体がさっぱりしただけなのに、案外楽になるものだ。ドラルクは洗面器や脱ぎ散らかした服をせっせと片して、また俺の頭を撫でる。子どもあつかい。
「すこし表情がよくなったな。よかった」
「……そうか? でも、着替えたらたしかに楽になった。拭いてもらえたのも」
「ふふ、よかったよ。おかゆができたら声はかけるけど、寝ていてもいいからさ」
「ン」
こういうときは、素直にうなずくのがきっとよろこぶ。
そんな予想どおりに、ドラルクは満足そうな顔でうなずいた。
できたよ、と声がかかったころには、ドラルクの股間も落ち着いたらしい。いや、人んちで処理をしたのかもしれないけど、ドラルクが隠そうとしているならつついて辱めるのは看病される側のやることじゃないと思った。ほとんど寝そうだったけど、こんな状態でも空腹感は覚えている。
べつに毎日料理を作ってもらっている訳じゃないのに、味覚はすっかり把握されていた。吸血鬼にはそういう能力でもあるのかもしれないが。とにかく、おかゆは俺にちょうどいい塩気で作られていたんだ。マシなほうというだけでやっぱ喉は痛えけど、無事に完食できてほっとする。
「ごちそうさま」
「おそまつさま。よかった、食べられたな」
「助かる。……」
このまま治るまでそばにいてもらえたら、きっと楽なんだろうな。
そういうことばが喉まで出かかって、飲み込む。いくらなんでもあつかましい。
空になった食器を台所に片してから、ドラルクが緑茶のおかわりを淹れた。緑茶のアイスティーってなかなか見ないよな。でもおいしい。おかゆに合わせた和食なのか、と思ったが、これも殺菌効果狙いだと。どこまで効果があるもんかねぇ。ほんとならスポドリとかもいいらしいけど家にはない。このあと買い出ししてくるよ、とあれが笑うから、ありがとう、と何度目かわからない礼をした。
やたら出された薬を飲み干し、一息。
「水分とってゆっくり寝たまえ。汗をかいたらまた拭いてあげよう。寝てるあいだに掃除とか洗濯をしておいてあげるよ」
「あ、え……」
寝てるあいだに……。
時計を見る。まだ安全に帰れるであろう時間だ。日が出かかってるから家に残ってくれるのかと思ったが、違うらしい。
うーん。
わかんねえことは聞くしかないよな。なんか怒られる気はするけど……。
「おまえ、いつまでいるんだ」
「……君さえ良ければ、治るまで看ていてあげたいと思ってるけど?」
「でも、ジョンは?」
「君のことを伝えて、お留守番してもらっているよ。彼は大人だ。心配しなくても、ひとりでじゅうぶん生活できる」
「……、」
「ジョンに悪いとか思っているかい」
うなずく。
ドラルクの口調に、いまのところ怒気はない。
「もちろん聞いたさ、一緒に来るかって。でも、自分にやれることは少ない。それに体調の悪い君を置いて、ツチノコたちと遊んでいるだけなのも忍びない。だから彼は、君の邪魔をせずに城で残ることを選んだんだ。もちろん、君がジョンに会いたいなら、連れてきてあげられるよ」
「あ……」
食事で潤っていたはずの喉が、それでもひっくり返った。しばらくドラルクに背を撫でられながら咳をやりすごす。
どうだろうか。
ジョンには会いたい、けど、こんな身体で会ってどうするんだろう。ひとりにしておくのはきっとさびしいけど、弱った俺に会っておもしろい訳もねえ。
「……治ったら」
「うん」
「城、行きたい……。ゲホ! ……その前に、おみやげ買いたいから、ついてきて」
ほしい、と言い切る前に咳がまた出た。ドラルクに勧められてお茶を飲みながら、これで合っているんかな、と思う。
わかりやすいやさしさを向けられるのは、妹以外にはじめてだ。
だから、いまだに対応がわからないままで……それはきっと、ドラルクたちには、とても失礼なことになっている。
でも、受け取りたいと思ってるのも嘘じゃない。
やりかたがわからないなら、教えてもらうのも悪ではない、はずだ。
ドラルクは笑って、いいよ、と言った。
はちみつをひとさじ

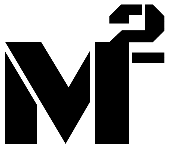
コメント