執着が薄れている、自覚がある。
はじめは誰かの目に留まればいい、程度だった。やたらと売れた理由は……俺にもよくわからない。たまたま文字をうまくあつかえただけかもしれないし、吸血鬼から被害が絶えない時代にあっていたのかもしれないが……、結果論だ。
誰かに認められたくて書いているんだから、認められるだけの理由がないと、さ。そういう重圧からぜんぶ解放された訳じゃないけど、確実に軽くはなっている。
それは全部、ドラルクのおかげだ。
でも。
だからといって、あれに依存するのはどうだろう。
ドラルクにはドラルクの人生があって、俺の存在はあくまで異物に過ぎねえのにな。そんなモノに依存されてプライベートまで侵食されるのはかわいそうだ。たとえ……呼び出してくるのがドラルクの側からだとしても。
俺の仕事に付き合わせるときは、俺の好き勝手にする。そうじゃないと、紙面上の『ロナルド様』と辻褄が合わなくなってしまうからだ。
だけど、ドラルクの用事に付き合うときは、なるべくドラルクの意に沿うような、そういう振る舞いをした。
出されたモノを食べる。
勧められたモノを遊ぶ。
愛をささやかれたら、うなずく。
俺もだよ、とひとことも言っちゃいねえのは、あいつ自身も気付いているだろう。この関係をあれがどう考えているか知らねえが、遊びでもなんでも俺には関係ない。全部ドラルクのすきにすればいいんだ。俺の気持ちなんかに、たいした価値はない。そもそも、誰かをすきになることなんかないはずだったんだから。
ただ……本気じゃないといいな、とは思った。
あいつの本気は、あいつのためにとっておくべきだよな。
□■□■□
「君のおねだりが聞きたい」
「はあ?」
いや、まあ、唐突だったか。
中途半端な高さで止まったスプーンには、私お手製のシチューが乗っている。彼の、彼だけのための得意料理だ。おいしいよ、という声音は無機質で、彼の感情ではないことがわかっている。わかっているけど、それをつつくような勇気もなかった。もし、実は味がわからないんだ、とか言われてしまったらどうしたらいいかわからなくなるじゃないか。まったく無くはなさそうなのが怖いし。
彼はすこし考えてから、いつもしてるだろ、と言う。
「仕事で」
「仕事でだからダメなんだ。それは君のおねだりじゃなくて、『ロナルド様』だろ」
「! ……、」
スプーンがシチューに戻っていった。口に運ばれないまま、溶けてどこにあるのかわからなくなった私の愛の結晶たち。
こうなるのはいやだ。
――私が吸血鬼だから壁を造られているのだろうか。
それとも、九九九の前に出逢っていたら?
ぼんやりと億劫そうにするすがたは、彼のいう『ロナルド様』ではない。そういうすがたを見せてもらえることに、優越感を覚えていたのははじめのころだけだ。いや、嘘かな。今も感じてはいるけど……それ以上が欲しくなった。
信用されているのはうれしい。
でも私は、信頼されたいのだ。
「八月、君の誕生日だろう。今年のお祝いは、君からのおねだりがいい」
「なんで俺の祝いをおまえに要求されてるんだ」
「おねだりを私が叶えるんだよ。最終的に与えるのは私で受け取るのは君だ」
要は単に、プレゼントを聞いているだけなんだよな。
でも、単にプレゼントはなにがいい、などと聞いたって「いらない」と返してくるのがこの子だ。まっすぐに聞いたって壁でガードされるのがわかりきっている。
ああ、まったく。
「君はいつになったら心を許してくれるんだろうな。まあ、難しいのはわかるけど」
「? 許してるだろ」
こと、と首をかしげるすがたは、まるでほんとうにわかってないみたいだ。まさか、心を許せていると本人は思っているのか?
「それで? 君が私に声をかけるのは仕事のときだけじゃないか」
「それ以外になにがあるんだよ。ビジネスパートナーなんだから、それがふつうだ」
「相棒のことをビジネスパートナーって呼ぶのはやめてくれ。それに、私たちは恋人じゃないのか?」
「………………、まあ……」
「待ってくれほんとうに違うと思ってる!?」
「そういうんじゃないけど……いや、いい。この話はここまでにしよう」
「する訳ないだろバカバカバカ!」
ほんとうに待ってくれ、前提が変わってくるんだが???
頭を抱えて、私はうつむく。私がこれまで明確なアクションを起こさなかったのは、ひとえに彼のペースを守ろうと思ったからだ。それじゃあ事が進まないと判断して、今日の『おねだりのおねだり』になった訳だが……。
私は何度も彼に好きだと言ったし、彼もうなずいてくれたはずだ。キスはもちろん、身体を重ねることだってしている。そのどれも、一度たりとも拒絶されたことはない。
……、待ってくれ。
拒絶されたことはない。
けど……求められたことも、ない。
「ドラルク?」
おとなしく、それでいて従順に、彼は私のようすをうかがっている。
ビジネスパートナーだ、と彼は言った。
恋人じゃないと思ってるのか、という問いには、そういうのじゃない、と。
恋人だとは思っているけど……、なんだというのだろう。話をむりやり終わらせて、彼はなにから目を逸らしたのか。
――恋人に近い、従順なもの。
まさか、まさか!
「ロナルドくん、違う。私は君を従えたい訳じゃない」
「? そうだろうな。どうしたんだよ」
ぱち、と彼がまばたくと、ふさふさのまつ毛が揺れる。ともすれば絵画のようだが、それは現実味がない、ということだ。彼のふるまいには……『彼』がいない。
「君には拒否権がある! キスもセックスも、君は拒絶してよかったんだ……」
「うん……?」
彼はもう一度、どうしたんだ、と言った。
「べつにいやだなんて思ってないよ」
「でも……、やりたいとも思ってないんだろう、君は」
「それは、まあ。そういうこと、あんまり興味ないだけで、やりたくない訳じゃない。おまえがやりたいなら、それでいいと思うぞ」
「そんな訳ない!」
そんな一方的な関係になりたかった訳じゃないんだ、私は!
お前、気付いてなかったんだな。そう言う彼の声音はやさしくて、私のことなんかなんとも思っていなさそうだった。悪い意味ではなく、ほんとうに、私たちの関係に問題があるとは思っていない声音だ。
「興味なさそうな顔してなかったなら、ほっとした。うまく演技できるもんだな」
「しないでくれ……」
「お前は俺の仕事にじゅうぶん付き合ってくれてるよ。俺はそれで満足だ。だから、おまえが俺でやりたいことを我慢する必要はない。いやじゃないのも嘘じゃない」
「……、でも、……」
「ほんとだよ。それで、要らなくなったら捨てればいい。全部おまえの好きにしな」
「は」
これで会話は終わりだ、とでもいうように、彼が食事を再開する。だけど、とても許せる内容じゃなかった。要らなくなったら捨てればいい……、まるで消耗品だ。
「……今日のシチュー、どうかな?」
「うん? おいしいよ」
「……、」
からっぽな笑みで告げられたことば。
そうか、というひとことを捻り出すので精いっぱいだった。
焦げたパンでも出してやろうか、と思う。
思うけど、たぶん彼は表情ひとつ変えずにおいしいよ、と言うだろう。無機質で、無感動な、記号としてのことば。
料理を出されたらおいしいと返せばいい。
ただそれだけ、一種の反射として落とし込まれているやりとり。
そんなものが欲しい訳じゃないのに、彼にはそれがわからないのだ、ということがわかってしまった。
ここは事務所。事務所とはいえ、彼はほとんどの依頼で最初から依頼人のところへ出向いていく。だからこの部屋はほとんど執筆用の缶詰部屋だ。「出勤するのって、意外と大事だぞ。気分が違う」とは彼の弁。
カタカタと彼がキーボードを鳴らすのを、応接用のソファにごろりと転んで聞く。優雅な夜である。
以前はそう思ってたんだけどなあ……。
あれから、キスもセックスもしていない。しなくていいのか、とは聞かれたけどな。したい、じゃなかったから、答えはしないよ、にした。彼から求められるまでしない。興味がないと言っていたから、興味を持たせるなにかが必要なのかもしれないが……、いまだそのスタートラインには立っていないのだ。
彼の誕生日は着々と近付いているが、彼のほしいモノなんか聞き出せそうにない。そもそも、彼に欲がなさすぎる現状じゃあ……。
「……なあ」
「うん?」
彼についてうんうん唸っていたから、タイピングの音が途絶えたことにも気付いていなかった。起き上がって彼をうかがうと、言いづらそうに口をつぐんでいる。
「ロナルド君?」
「あ、……ええと。暇じゃないか。依頼入ったら呼ぶから、散策してきてもいいぞ」
「暇じゃないよ。君の気配は心地がいいからな」
「……、」
そうか、という声音はやはり硬い。
このあいだ、くだんのやりとりをしていたときのほうがやわらかい声をしていた。暇じゃないか、というのは方便で、もっと気になる事があるのだろう。
立ち上がって彼の机に向かってみる。
「先生、進捗は?」
「……まあまあ」
「そうかい。お散歩する?」
「俺が? 俺はしねえよ。パトロールは組合の連中がやるだろう」
「パトロールじゃないよ、お散歩だ。君が散策してこいって言ったんだろ」
まさか忘れた訳じゃあるまいに。
彼は首をかしげて、なにを言ってるんだ、という顔をした。
「俺はおまえに言ったんだ。俺がついていったら意味がないよ」
「はあ〜? 意味がないって、私が一人でシンヨコ歩くことになんの意味が?」
ジョンはかぼちゃやツチノコと彼の家でお留守番だし、このままじゃほんとに私がひとりで知らない街をプラプラ歩くだけだ。散歩が趣味だ、という者ならそれもいいだろうが、私は引きこもりだぞ。
彼はなぜか目を泳がせて、もごつく。
「その……俺がいたら、邪魔になるかもしれないし」
「???」
「だから、……俺よりおもしろいなにかと、出逢うかもしれないだろ?」
「君より……?」
そんなもの存在するのか?
思わず首がかしぐ。そんな私に、彼はきゅうと眉根を寄せた。
「おまえ、最近俺になにも言わないだろう。飽きたモノのそばにいるより、ほかの、……あたらしいなにかを探しに出掛けているほうが、建設的だと思うんだが」
「は、……はあ〰︎〰︎〰︎ッ!!!???」
「うるさ」
「いやデカい声も出るだろうが!!」
なにを言っとるんだほんとうにこいつ!
「私は君に興味を失ったりしない!」
「いいって、そういうの。ヤる気がなくなったのは事実だろ」
「事実じゃないしなくなってもない。私はただ、君にその気が起きるまで待っているだけだ! 無理強いは趣味じゃないんだよ」
むしろ勃たない。人間と付き合うにあたってそっち方面のアダルトコンテンツとか検索して、陵辱ネタの多さに萎えて帰ってきたぐらい勃たない。
そんな私がほんとうに理解できないのか、彼は怪訝そうな顔をした。
「俺にその気が起きなかったらどうするんだよ」
「そんなの、このままなにもしないに決まっとるだろ」
「は……」
「絶句したいのはこっちなんだが〜!?」
仕事中の彼になんだこいつと思うことは多々あったが、オフの彼にはなかなかない。いや、いまはオフなのか? 仕事中ではあるのか……。
ぼんやり抜けていることにツッコミをいれることはあっても、こうも理解が難しいことはそうないはずだ。
「ロナルド君。聞きなさい」
「……、」
「私は君が好きだよ。仮に、君に中身がないのだとしてもだ」
彼の手がぴくりと揺れる。爪がキートップに当たり、がち、と音を立てた。上から私が見下ろす姿勢ではプレッシャーがあるのかもしれないな。彼のとなりへ移動して、ひざまずく。
「もしそうじゃなくて、隠している中身があるなら、私に見せてほしい。それを見て、私は君を否定したりしないし、失望したりもしない」
「あ……、む、無理だ。そんなの……」
「どうして?」
深海のような彼のひとみが、うろうろとさまよっている。あ、とか、う、とか、彼らしくない言い淀みかたをして。
……いや。
彼らしいところなんて、私は見たことがないのかもしれないんだ。
迷子みたいに震えている目の前の彼が、もしかしたら……。
「おまえに……、依存したり、したくない。これ以上迷惑かけるのは、いやだ」
「したらいいだろ、依存のひとつやふたつ。私は迷惑だなんて思わないよ」
「それは、実感がないから、で……」
「そうだな。だから試してみたらいい。そもそも、これ以上って言ったけどさ、私は君に迷惑をかけられているなんか思ったことないんだぞ」
うーん。
迷った。この言いかたはたぶん彼に刺さるけど、へんな刺さりかたをしそうな気もするのだ。とはいえ……暖簾に腕押しよりはマシなのかもしれないし。
「君が君を教えてくれないほうが、よっぽど迷惑かな」
「……、……!!」
がちゃ、とまた爪がキートップを叩く。
青くなった顔に手を伸ばしたいけど、まだ早いだろうか。きっと彼は否定をしない。でもそれは、否定できないだけなんだろうから。
「ロナルド君。触ってもいいかい。いやだったらちゃんと言うんだ」
「……、……あ……」
しばらく待ったが、彼の答えはあ、だけだった。了承ととるべきか悩んで……私は行動することに決める。ゆっくりと触れた頬は手袋越しでもあたたかい。
「いやな言いかたをしてごめんな。でも、事実なんだよ。私は君が知りたいんだ」
「俺、を……」
「そう。もし、私の言いなりになっているほうが楽だというならそれはそれで、君を導くことがいやな訳でもないし。ただ、君を捧げるような真似をされたくないんだ、ほんとうにただそれだけなんだよ」
ぐ、と彼がうつむく。私の手から逃げたい、というよりは、頭を上げていられなくなった、という感じだ。頬を撫でるのをやめて、その髪をすく。私が触れる唯一の銀。
「……おまえ、の」
「うん」
「お前のおかげで、息がしやすくなった。もう、それでじゅうぶんだ」
「そっか。それはよかった」
「これ以上は……、おまえの負担になるだけだって、わかってるんだ……」
「君はわかったんだろうけど、私はわからないんだよ。ためしに、君がやりたいってこと、ひとつ私に教えてくれたまえ」
「……ひとつ……」
長い前髪の下で、彼がこちらをちらりとのぞく。それにうなずいてやると、すいと目線を逸らされてしまった。
「俺は、……このままいてもらえたら、それで……。いや、いいんだ、お前が自分で行きたいと思ったところに行けばいい。べつに、むりにいてほしい訳じゃなくて、」
「わかったわかった。それがひとつなら、いくらでも叶えてやれるよ。ほかには?」
「ほ、ほかに……」
うむ、とまたうなずいてやる。彼はしばらくうろうろと視線をさまよわせたあと、ぎゅうとまぶたを閉じてしまった。
「急に……言われても、わかんねえよ。考えないようにしてたから……」
「……、そっか。じゃあ、思いついたらまた教えてくれ。誕生日にしてほしいこと、とかな!」
「……それ、まだ続いてたのかよ」
「終わる訳ないだろうが。原稿やりながらでいいし、ゆっくりでいいからさ。ああ、誕生日過ぎたっていいぞ。前後半年は祝っていいとされている」
「年がら年中じゃねえか」
お、ボケに乗ってきたな。
うんうん、これでいいんだよ。
「そうだよ。大事な子の誕生日なんて、どれだけ祝っても祝い足りないんだからさ」
「……、……」
立ち上がって、ふわふわの髪を撫でてやる。これが正解だったのか、彼はこくりとうなずいてくれた。
知りたい気持ちはもちろん強いが、だからといっていますぐ全裸に剥こう、なんてつもりはない。彼が怖がる依存だって、そんなものとっくにこっちがしているのだ。それに気付いてもらわないとな。
来たる誕生日、顔を真っ赤にした彼に「セックスがしたい」と請われてしまって、ひっくり返って死んだのはまた別の話である。そんなもんプレゼントになるか〜ッ!!
赤い退治人を狙い撃ち!5の展示作品でした。去年と似たような話だな……
イベントから来られた方はこちらへどうぞ。
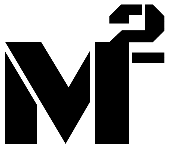

コメント