でっかいいぬを飼い始めた。
畏怖すべき不死の王、とか呼んでみたけど、実際はいぬだ。おおかみですらない。大神にすら等しい能力を持ってはいるけれどね。
いぬはよく懐き、私に腹を見せる。
「ドラ公?」
吸血鬼なのに、血は嫌いらしい。
最低限に留める吸血の代わりなのか、人間の食事をよく食べる。普通の人間の三倍くらい食べた。食事代は経費で落ちるのでよし。
なにも知らないようでいて、知識は深い。吸血鬼の特性についてことさらに詳しいため、生き字引として連れ歩くようになるのは自然だった。もともと、監視のためにその必要はあったのだけれど。
「どらこー。おおい」
「……、」
いまも私の命令を待ち望んでいる、従順ないぬ。
私、そういう趣味だったのかなあ。
「どうしたんだよ。お腹いてえとか?」
「いや、べつに」
「……俺、出てく? ギルドだったら、お前見てなくていいんだろ?」
「なんでさ。君はここにいるんだよ」
「でも……」
つい、と目元に彼の指が触れる。吸血鬼らしからぬ暖かいそれ。
「くま、またひどくなってる。……俺のこと、もしかして寝ねえで見てんの」
「それはまあ、もともとこういう顔なんだよ。君のせいじゃない、睡眠もちゃんととれているしね」
すり、と懐いてみせると、彼は離れてしまった。惜しかったなあ。
君をどうしたら手に入れられるのだろう。
「まあでも、今日はもう寝ようかな。君もそうしなさい」
「あ、……うん」
おやすみを言いあって、同じベッドに潜り込む。腕のなかに抱き込むようにすれば、彼はびくりと震えて、けれど、大人しく眠りについてしまうのだ。
「赤い子!」
「……ヒナイチだと言っているだろ。ロナルド」
「やあ、おつかれ。パトロールかな」
もはや見慣れた二人組だった。ヒョロガリの容貌からは想像もつかないほど、指揮の能力に秀でたダンピール。どんな殺し方でも死なない、不死の吸血鬼。
吸血鬼のほうが、嬉しそうな顔で走り寄ってきた。私からしたら仕留め損ねた宿敵なので、懐かれるのも困るんだが。
しかし彼は実際とても、いい子だった。なんだか弟ができた気分なのだ。
吸血鬼らしからぬ善性と、吸血鬼らしい享楽主義が、反発せずに同居している。頼まれたことは断らないから、私たちの退治を手伝ってくれることも多い。
そんな彼が、こそりと耳打ちをしてくる。
「(……あのさ。相談したいことがあるんだ)」
「相談?」
「(……声でかいって! ……そう、ドラ公には、聞かれたくない)」
「……、」
内容によっては『ドラ公』……彼と並び立つダンピール、吸対隊長のドラルクに、報告するかもしれないぞ。私がそう告げると、それでもいい、と彼は言う。
「(……ヒナがそう思うなら、いい。俺はもう、どうしたらいいかわかんねえ)」
「……? わかった」
「ドラ公、俺ちょっとヒナのパトロール手伝うわ」
「ああ、ヒナイチ君なら私も安心だな。ちょっとギルドで休ませてもらおうかしら」
「貧弱おじさん」
「やかましい」
ギルドはすぐそこだ。ドラルクと別れて、ロナルドに目配せをする。
「俺、さ。ドラ公のこと、すきになっちゃったみたいで。……ドラ公は仕事で仕方なく俺の世話をしてるのに、なんか、勘違いしちゃうっていうかさ。俺のこと、すきでやってくれてるならいいのに、とか思うのがつらくて。だから、……ヒナが俺の監視、やってくれないか」
「は」
「たぶん退治人なら大丈夫だろ? ヒナはすげえ強いしさ」
隣を歩く吸血鬼は、まっすぐ前を見てそう言った。
「……気持ちを伝えたり、だとかは」
「まさか! ドラ公が俺のことすきになるわけないだろ。気味悪がられたくないし」
「そんなことはないだろう、」
というか、なんならとっくにくっついたもんだと思っていたくらいだ。
ドラルクの、ロナルドへの世話焼きは明らかに監視の職域を超えている。ロナルドは監視されているにもかかわらず、ドラルクに従順だし、言いつけは必ず守るのだ。
ただならぬ関係なのではないか――と、下賤なうわさが囁かれる程度には、彼らは近いところにいる。
「……すきでいるだけなら、いいだろ。でも、勘違いしてつけあがるとか、いやだ」
「……ロナルド」
「俺、もうなんもしないぜ? 皆がこの街にいるために、やれって言われたことはやるし、やるなって言われたことはやらないから。ヒナの面倒なことはしないから」
――たまに、さっきみたいにすれ違ってさ、軽くあいさつとかするんだ。それくらいなら、俺は隠しごととか苦手だけど、ボロも出さなくて済むだろうし。
そんなことを言う彼のひとみが、泣きそうに濡れていて。それでも決壊しないせいで、こちらが哀しくなってしまう。自分が愛されるわけがないと確信していることば。
「だから、――……」
「ロナルド?」
ずる、と彼の身体が溶けた。吸血鬼の能力のひとつ、影に潜むこと。私の影に入り込んだロナルドが、精神感応で話しかけてくる。
『能力を使ってるやつがいる』
「……なに?」
『知らない気配だ。たぶんドラ公もすぐ気付くと思うけど、先に行く?』
「ああ、行く。案内してくれるな」
『ん。まずはこのまままっすぐ、信号まで――』
彼の道案内は、正確でわかりやすかった。肝心の現場までは大通りを案内されたので、若干癪に触るけども。
湿っぽい裏路地。
女性の腰に手を回し、いざ吸血せんとする高等吸血鬼がそこにいた。魅了を扱うのか、女性に反抗の意思は見られない。
「動くなッ!」
「ッ!?」
愛銃を構えて叫ぶと、吸血鬼がたじろいだ。ロナルドがなにを考えているのかはわからないが、身を潜めると決めたらしい。
私は小柄だ。そのうえ女であるので、どうしてもナメられやすいのが難点だった。
「く、退治人か。……だが、女! 俺の目を見るがいい!」
「言われて見るバカがいるか」
目を閉じても当てられる。問題はない。
がつん、と撃ちだす麻酔弾。どさりと倒れた音を確認してひとみを開くと、いつのまにか影から抜け出したロナルドが女性を抱えていた。ぱちんと指を鳴らしてから、大丈夫かと問いかけている。
「へ? えっ、あれ……? だいじょうぶ……だと、思います」
「そっか、よかった。なあヒナ、VRC一応行ったほうがいいんかな、このひと」
「うん、そうだな。この変態を連れて行くついでに診てもらうとするか」
状況を呑み込めない彼女に、私が説明した。魅了をかけられており、それはロナルドが解いたこと。魅了した犯人も私が捕縛しているから、不安なことはなにもないことを告げる。じわじわ恐怖が浮かんだのか、彼女はロナルドの胸に縋りついた。
「こわかったなあ。間に合ってよかった。よしよし」
彼は吸血鬼である。
そのはずなのに。
女性をやさしく受け止める姿は、まるで聖母のようだった。
「なんで事後処理に呼ぶのよ。闘いに呼んでよ」
「そう言わないでよ、にく美君」
私だって戦闘になると思って君を呼んだんだもん。実際には、赤い退治人と私のかわいいいぬがすべて終わらせていたけれど。
現場で合流した我々は、連れ立ってVRCにいる。彼はVRCには入りたがらないし、私も入れたくないから、ジョンと一緒に外で待機だ。
結果として、被害者の彼女はなんともなし。魅了の力は完璧に、ロナルド君により解除された。吸血も未遂で済んでいるから、仮性化したりとかもない。百点満点だね。
用済みになったVRCから出ると、ロナルド君はコンビニにたむろするヤンキーみたいに座っていた。こわっ。
「ロナルド君、帰ろっか」
いつもなら、これで彼は大よろこびで飛びついてくる。
けれど。
「……あー、えっと。あのさ、どらこう」
「……?」
もごもごと、ロナルド君は視線を合わせてくれない。どうしたの、と近寄ると、余計に縮こまってしまった。
おや?
「今日……、」
「うん」
「ドラルク!」
振り返れば、今日の功労者であるヒナイチ君だ。
一緒にいたのだから、彼の異変についてなにか知っているかな。
「その……すまない、ロナルドについてなんだが。私が預かることはできないか」
「へ? なんで?」
「あー……、ええと」
「ドラ公」
ううん前後を挟まれてるから話しにくいぞ。振り返れば、ロナルド君は立ち上がって、真剣な顔で私を見ていた。抱きかかえられたジョンが、彼を見上げている。
「俺、もうお前に迷惑かけたくないんだ」
「は?」
「だから、監視なんだけど、ヒナにやってもらおうと思う。そしたらドラ公はゆっくりゲームもできるし、寝られるだろ。たいちょー、大変なんだからさ」
――ヒナなら、強いし退治人だし、いいだろ?
「待って、なんで? 私、君のこと迷惑なんて言ってないぞ」
「うん、でも、ほら。けっこう一緒にいたからさ。ドラ公が疲れてるのとか、わかるようになっちまって……原因は俺、だろ」
「……そんな理由で、私から離れようと?」
「ん。やっぱりダメか? 監視ならべつにドラ公じゃなくてもいいと思って……あ、や、女の子の家はダメか! そうだ、フォンとかは? ミカエラんとこなら、ケンとトオルもいるし!」
「ダメだよ」
「ド、ドラルク」
ヒナイチ君が焦ったように声をかけてくれるし、ジョンもヌーヌー泣いている。
でもダメだ。止まれない。
「君は私と居るんだよ」
「え、でも」
「でももだってもない。これは上の決定だが、それだけじゃないんだ」
ああ、こんなところで言うつもりなかったのになあ。なにさVRCの入口って。最悪だ、ムードのムの字もありゃしないよ。
でも、ヒナイチ君とジョンが見ているから、無かったことにはならない。
「私は君が好きだから、君がほかの誰かと暮らすなんて耐えられないんだよね」
「ドッ」
「ヌァ!?」
「――、」
ぽとりと落とされたジョンが、にゃんぱらりならぬマジロぱらりを決めながら悲鳴を上げ。
次の瞬間。
だん、と彼は地面を蹴り、姿を消した。
「あ、え。……あ!? ド、ドラルク! わた、私ロナルドを追いかけて、」
「ああいや、大丈夫。ありがとうねヒナイチ君、証人になってくれて」
そしてごめんね。ジョンも。
「居場所なら気配でわかるから、ゆっくり追うよ。それで口説き落とす」
「う、うむ……頑張ってくれ、で、いいのか?」
「勿論。ありがとね」
逃がしてなんかやるものか。
王≒こいぬ

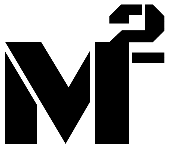
コメント
可愛くて大好きです!
ヒナちゃんにこっそりお話するシーンが特に好きです。
コメントありがとうございます!
本人に悪気は一切ないんですよね……