――ろなるどくんは、どらるくさまのこと、すき?
習得したヌー語がどこかで誤っていなければ、彼はたしかにそう言った。
静止は数秒。質問の意図を理解して、ふ、と口もとに笑みが浮かぶ。
「はは。そう見えてたか」
ことりと首をかしげて、彼――ジョンはわかりきった問いをする。
ぽっと出の人間ごとき……それも一度は主人を害した退治人。そんなものが愛する唯一の主人に余計な感情を抱くなんて、許せなくて当然だろう。
でも、彼のそれは杞憂だ。
あたたかな湯気をくゆらせるティーカップに視線を移す。……猫舌だから飲めない、なんて吸血鬼に言うのも屈辱的だから、いつもこうして冷めるのを待っていた。
「大丈夫、俺は勘違いしてないよ。あいつの好意はヒトに無害だってアピールなことぐらいはわかってる。……城のなかなんか誰も見てないんだから、そこまでしなくていいのにな」
演じることは得意だ。大衆の望む英雄しかり、吸血鬼の望む玩具しかり。……まあ、後者を望むヤツらはたいがいが銃の餌食となった訳だが……おそらく銃口から逃れてみせたのは、この先もドラルクだけになるだろう。ドラルクはそれを望んでいない、ただそれだけだったとはいえ。
誰かが見ている、という点では、俺の事務所のほうがよっぽどだ。城でこういったあつかいを受けていなければ、盗撮されているから気を付けろよ、と助言している。
「おまえの憂いは晴れたか?」
「ヌェ……」
さぞや安心した顔、もしくはすがすがしい顔でもしているだろう。そう思って彼を見ると、……なんだか潰れた顔をしている。やらかした、とでも書いてあるような。やはり、わかりきった質問をしてしまったのは恥ずかしいことなのかもしれない。
どういう言葉で慰めたらいいだろう? いや、俺に慰められるのはまさしく、恥の上塗りというものか。愛らしいアルマジロには、笑顔でいてもらいたい……たとえ、それが吸血鬼の使い魔であったとしても。
ドラルクの戻りを待たずに、ゲームをはじめてしまえばいいのかもしれない。そう思って口を開くのと、名を呼ばれるのはほぼ同時。
「ロナルドくん」
「なあ――、?」
振り返ると、くだんの吸血鬼が、なんとも言えない顔をしてこちらを見ていた。
悲しんでいるとも見えるし、怒っているとも見えるそれ。憮然とした表情、という表現を怒りの現れとするのは誤用だが、しかし失望しているとも見てとれた……この表情を文章にするのは、読者にただしく伝えるのは難しいだろう、などと考えるのは作家のさがとみせかけた逃避だ。
だけど、逃避をしたくもなるだろう。
ドラルクがそんな顔をする理由なんて、これっぽっちも思い浮かばないんだぞ。
名を呼んだきり、ドラルクは黙り込んでいる。だから俺が促さないと、場を持たすことすらできやしない。
「ドラルク?」
「……君は、……いや」
「ええと。お前を置いてゲームはじめようとしたのがバレたのか? 結果的にお前は間に合っているんだから、そう怒らないでくれよ」
「違う。はあ、まあ、なんとなく予想はしていたが……」
「? ……ん、ああ。さっきの話か」
帰ってきたタイミングからして、聞いていたんだろう。それで怒る理由はやっぱりわかんねえけど、不快にさせたなら謝るべきか。
こんなモノは必要がないし、噛み砕いてしまえば存在すらしねえのだ。
「他人に妙な気を持たれるのはしんどいだろう? 大丈夫だ、安心してくれ。お前にそういうつもりがないことはちゃんとわかってる。ただまあ……あまり誰彼かまわずやさしく振る舞わないほうが、身のためになるとは思うぞ」
「はあ。……しないよ、誰彼かまわずなんて」
「まあ、そうか。お前の城に来るのなんか、俺か大家さんくらいだもんな」
だからこそ、さみしさからこういうことになるのかもしれない。
とす、とドラルクが隣に座る。あれが席を立った目的である茶菓子は放置されて、ワゴンの上でさみしくしていることだろう。
「ロナルド君」
「うん?」
「君は、やわらかい心を持つ子だな。かわいいと思う子をやさしく愛でたり、こんな私がうっかり死んでも待っていてくれる。さらには復活の手伝いまでしてくれてさ」
「……? それは、まあ。待ってるのは、ただお前がいないと困るから……」
「そうだ。私も、君がいないと困るんだ」
「はあ……? そんな訳ないだろ」
無意識に語気が鋭くなって、だけどあれは動じなかった。
どうしてそう思うのかね。そういうドラルクの目はやさしい……詰問されている、というわけではない。だから、口を割る理由も、ほんとうならばないのだろう。
だけど、口は勝手に動いていた。
「俺は、お前の平穏をブチ壊したんだ。お前の退治を喧伝していたせいで、おまえがもとの……おだやかな生活に戻ることを阻害した。だから相棒なんかにならないと、無害であるって証明しなきゃならないといけない……そうしたのは俺だろう」
「……続けたまえ」
俺はドラルクのうなずきを求めたが、あれはそれに応じてくれない。しかたがないから、言われたとおりに言葉を進める。
「だから、……お前が俺を好む理由はない。多少関係ができて、印象が変わっても。俺はお前にとって害のままだ。そもそも俺は退治人だしな。……でも……」
吸血鬼のすべてが敵ではない。だけど、相手が退治人というだけで萎縮してしまうものは多い……パトカーを見ただけでなんとなく背筋を伸ばしてしまう、人間と同じ反応だ。咎められるべきではないが、そうされる側としてはさみしいことでもある。
だからこそ、そうではないようにみせてくれるドラルクがめずらしく、すこしだけ尊くさえ感じてしまうのだろうが。
――そんなのは俺の都合で、ドラルクには関係がない。
そう、ほんとうはわかっている。俺が相手をした九九九の連中がとくべつイカれていただけで、すべての吸血鬼が悪ではないのだ、と。
だけど、それを信じさせてくれたのは、ドラルクだ。
何度も脳内で繰り返した。俺はドラルクに救われたけど――でも、そんなのは俺の都合で、ドラルクには関係ないことなんだ。
押し付ける訳にはいかねえ。
でも。
「――はじめてだったんだ。……俺が、『ロナルド様』になってから……」
ひどい現場を見た退治のあとに、城に寄るよううながして、あたたかいもてなしで俺を休ませようとする。今日は疲れただろう、ゲームをするんじゃなくてゆっくりと星でも見よう、とか……俺には思いつきもしない方法で、俺の拠り所であろうとした。
怪我なりなんなり、身体のことになら、さんざ言われたことがある。
だけど……俺のこころについて、触れられたのははじめてだった。
そのせいで、離れがたくなっていたのはたしかだろう。ジョンに誤解をさせるほど。
でも。
だけど。
「俺はお前に救われたけど……そんなことは、お前には関係ないことだ。俺なんかに、退治人なんかに妙な気を持たれたって、迷惑なだけだろう。だから、ない」
ないということにする。
ドラルクにとって必要のないモノであるなら、大事にする必要はない。
生まれてくるそばから握りつぶしてしまえば、存在したことにはならない。
誰かに観測さえされなければ。
「ありえないよ。お前は俺がいなくなっても、楽になるだけで困りはしないんだ……そんなものに好かれたって、むしろそれに困っちゃうだろうにさ」
たとえば、このティーカップが割れたところで、あたらしいものを買うだけだ。
人間と触れることがおもしろかったのだとしたら、あたらしい人間を探せばいい。いくらでも代わりが効く――なんなら、俺ではないほうがより適している――。
「ロナルドくん」
「……、」
「よかった。私は君を救えていたんだな」
「……ああ。ありがとう」
ドラルクの優しさは、こんな俺にも向けられるのだ。こんなにうれしいことはない。
そう思って微笑んでみせると、あれもまた微笑みを返してくれる。うれしい。が、そのあとに続くことばは、なんだか難しいものだった。
「うむ。……だが、不完全だ」
「?」
「私が君のぜんぶを掬ってみせる。君はただ、享受してくれたらいい。怯えないで、このままそばにいてくれよ」
「すくって……、?」
そばにいる、とは。
とっさに理解ができなくて首をかしげると、ドラルクの手が俺の髪をはらう。じ、と俺をみつめるひとみには、敵意などなく……だれにも向けられたことのないような、あたたかい光が灯っていた。
でも、そんな訳はない。
あっちゃいけねえのだ。
「ふ、はは。お前がそんなこと、思う訳ないだろ」
「……なに?」
「怯えたりなんかしてねえよ。ちゃんとわきまえているだけだ。……だから、お前はなんにも気にしなくていい。吸血鬼らしく、やりたいことだけやればいい」
そこに俺の意思は必要ない。
俺がドラルクの意思を無視して、退治に引きずり回すのとおんなじだ。
ドラルクの微笑みは消えてしまったが、俺はそれをやめなかった。ただそれだけが、俺にできることだった。
「ドラルク、だから――」
「好きだよ」
おまえの好きにしてくれ。そう続けるはずのことばは出鼻をくじかれ、宙に浮く。
「好きだ。……残念ながら、君は私を好いてくれていないようだが……。私を好きになってもらえるように頑張るから。繰り返すけど、そばにいてほしいんだ」
好き。
ドラルクが、俺を?
「ずっと、君を大事にしているつもりだったんだ。足りなかったのなら……もう一度、私にチャンスをくれ。今度こそ、君を幸福に連れていってみせるとも」
「……幸福」
はて、と思う。
俺はもうとっくに救われている。それは幸福と言って差し支えがないだろう。
べつに、そばにいろと言われれば、そのとおりにするのは大した問題じゃねえし。そばにいられること自体も、たしかに幸福だ。
「俺はもう、幸福を得た。何度も言うけど、お前は気にしなくていい」
「するよ。気にする。君はそれを幸福というけれど、幸福っていうのは一方的なものじゃないんだ。私をしあわせにすることだけが、君の幸福ではないんだよ」
「……?」
よくわからない。
たぶんそれは顔に出ていて、でもドラルクは笑うことも、嘆息することもなかった。
「とにかく。私は君と仲良くなりたいんだ。どちらが上とか、そういうものはいい。仲の良い君のことなんだ、私に関係のないことになる訳がないだろ?」
仲良く。
ドラルクのことばを脳内で噛み砕こうとして、そのひとことが反響した。
仲良く……。
「……じゃ、じゃあ、」
「うん、……!?」
「こ、ういうこと、してもいい……?」
ほんのすこし腰を浮かせる。
こけた頬、という表現では足りないくらい落ち窪んだ頬に、キスとやらをしてみた。力加減だのはよくわからないし、触れただけで正直ビビって逃げちまったけど。
「ろ、ロナルド君、きみ」
「うへ、へへへ……。できるなんて、思ってなかった……」
「き……! 君が、望んだら、いつでもしてあげたぞ!」
うれしい。
うれしい!
でもさ、望むなんかできないだろう。そう言ったら、どうして、とドラルクが聞く。
そんなの、決まっているじゃねえか。
「だ、だって。おまえと、友人になれるなんて、ひとつも思ってなかったから……」
「……はい!?」
「お前らが……くふ、親愛のキス? してるの……ずっと、うらやましかったんだ。だから、その……、してみたかった……」
せっかく、ようやく、友人の席に座らせてもらえたんだ。これくらいはいいだろう。
それ以上なんか求めないし、もしいやな顔をされていたら二度としない。そういう気持ちでドラルクを見る……と、なんだか、すごく困った顔をしている。
ああ、だめだったんだ。
ほこほことあたたまっていた気持ちが、すうと冷えていく。
「あ……でも、おまえはこんなことされたくなかったよな。わる」
「アーッ違う! いいんだ、いいんだけど! でも私、いま君と恋人になれたんだと思ってたからさあ!」
恋人になれた。
誰と、誰が?
「ドラ、ル――?」
「わかった。友人だな。友人になってすぐのところで悪いんだけど、私とお付き合いしてもらえないかな!?」
「は、はあ!? なに言ってるんだ。お前がそんなこと思う訳ないだろ!」
「デジャブ! わかってたけど!!」
友人にだってなれると思っていなかったのに、恋人になれるなんて思う訳がない! ドラルクは俺を友人にしてもいいみたいだが、恋人にしていいとまで思う訳がない!!
「ドラルク、その、からかうのはやめてくれ。俺はもうじゅうぶんいっぱいなんだ、友人を消化するだけでけっこう胃がもたれているんだぞ」
「そうかそうか、どんどんもたれさせてくれればいい。いくらでも看病してやるさ」
「はあ?」
なんなんだ、こいつ。
やっぱり人間で遊んでいるだけか?
「君が今、なにを考えてるかわかっちゃうのがいやだな。……でもな、ロナルド君」
ドラルクの手がすいと伸ばされて、俺の下腹に触れた。
腹?
「君のこの、薄い腹に種を付けたい」
「は」
「君をどろどろに蕩かせ、私のこと以外なんにも考えられなくさせてやりたい。……こんなこと、友人に思うとでも?」
「ぁ、ぇ、は……っ」
「……はは、冗談だ。いきなりとって食ったりしないとも」
冗談じゃなかった! その目はぜんぜん冗談じゃなかった!!
あまりの急展開に、なにを言い返すこともできやしねえ。ぐるぐると目を回す俺に、ふう、とドラルクは嘆息した。
「君は急展開だと思っているだろうが、私はそうじゃないからな。むしろ、こちとら準備に準備を重ねて、布石をばらまき、着実に好感度を上げているつもりだったんだからな!」
「へぁ……?」
「クソーッなんもわからん顔をするな腹立つ!」
「ッ、」
腹立つ。
怒ってる――怒らせている!
「ごめん、ごめんって! その……っ、」
「違う!! 怒ってはいるけど、それは私にだ。君に怒ってる訳じゃ、……なくもないけど、とにかく違う」
「怒ってんじゃん……」
怒られるのはいやだ、誰だって。
ドラルクはふうと嘆息して、それに思わず身体がびくつく。だけど、大丈夫だよ、という声はやさしい……怒っているなんて、まるで嘘みたいに。
「いちばん怒っているのは自分にだ。君にうまく伝えられていなかったのは私なのに、その責任を君に転嫁するところだった。……」
ソファについていた手を握られる。また俺の身体が揺れたが、逃がしてもらえない。
「私は、君が好きだよ。ドラルクは、ロナルドが好き。ただそれだけなんだ」
「あ……う、」
「余計なフィルターなんかかけないで、ただ、私の渡すものを、受け取ってほしい」
余計なフィルターと言われても、なんのことだかわからねえ。そう素直に伝えたら、そうだよな、とうなずかれた。意図が読めずに首をかしげると、するりとあれの手が頬を撫でる。俺の手を握るのと、反対の手。
「私は君を好き。これは事実だ。君に否定されるものではない」
「……、」
「君は? 私が吸血鬼で、君が退治人ということを考えずに、答えてくれ」
「それは、……嫌いじゃねえと、思うけど……」
すきだ、というのは憚られた。
それがドラルクの望む答えだったとしても、だ。
「おまえに、しあわせでいてほしい、と思う。そのために、いらないものは排除してやれたらいい、とも思う」
「……、ああ」
「俺は、いらないものだから……捨てないといけないんだ。……友人としてぐらいは、許されたいと思ったけど……それも、本来は間違いだと、思う」
「……、」
「おまえのことしか考えられなくしたいって言ったけど……それはもう達成されてる。だから、これ以上は、もういい」
はく、とドラルクが息を呑む気配。
気配を感じるだけだ。俺の視線は下がって、ドラルクの腹を見つめている。
これ以上の問答は無駄だし、帰ったほうがいいだろう。そのためには、ドラルクが手を離す必要があるし、俺が振り払ったらドラルクはきっと死ぬんだ。
「私のことだけ、考えてくれている?」
「? うん」
「そうか。……そうか」
なにかに納得したようなドラルクに、ほっとした気持ちで顔をあげた。だけど……ドラルクが俺から手を離すことはない。するりと頬から後頭部に向かい、俺のことをゆるりと引き寄せた。ドラルクの胸部に誘い込まれる。
「……?」
「ありがとう。君が私を大事にしてくれて、とてもうれしく思っている」
「??? うん……?」
「だけど、君は重要なことを間違えているんだ。君はいらないものなんかじゃない。むしろ……私がいちばん大事にしたくて、いちばん手に入れたいものなんだ」
「いち、ばん……」
そんなはずはない。
そんな、はず、あっちゃいけねえだろう。
そう思っているはずなのに……舌がもつれてうまく動かなかった。そんな俺のことなんかほうっておけばいいのに、ぽろりとこぼれた涙がドラルクの手袋に染み込んだ。
「大丈夫。だいじょうぶ……」
ドラルクは、ロナルドがすき。
ドラルクは、ロナルドがいちばん大事で……手に入れたい。
――そんなの、もうとっくに。
ゆっくりと、ドラルクの胸に抱き込まれる。
俺はそれを拒否せずに、ただ黙って従った。
おともだちからはじめましょう

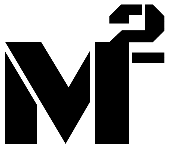
コメント