はじめての出会いだった。
人間と共存しようとする吸血鬼が、この世に居ない訳じゃない。
そんなことはあたりまえのはずなのに、その存在は簡単にかすんでいくのだ。俺の目の前に現れるのは、たいがいが人間をエサとしか見ちゃいねえ。いたぶり、弄んで、ゴミのように捨てることになんの感慨も抱かない。そんな連中を九九九体。
実際には、はじめてなんかじゃないとわかっていても。
それが俺のかぶせた濡れ衣であったとしても、だ。
退治するとまで言われてなお、バカみてえに愚直で素直な吸血鬼。
そんなものとは、はじめての出会いだったのだ。
「やあ、いらっしゃい!」
「おう」
おう、じゃねえ〜!
お邪魔します、のひとことも言えやしねえのに、そんな俺をドラルクは咎めない。それどころかニコニコと笑みを浮かべて、俺をエスコートしようとした。手を引くまではされないけど、自然な所作で振り返りながらホールまで連れていかれる。
差し出される手へとマントを預ければ、丁寧に受け取られる……その仕草はまるで、それが退治人の衣装であることに嫌悪感などありはしないかのようだった。
いや、おそらく、ないんだろうけど。
退治人なんか気にも留めていませんと言わんばかりに、ドラルクのすがたは自然だ。
だけどそれがありがたかった。あれだけの迷惑をかけておいて、こうやって遊んでいるだけで許されるっていうのも……不公平な感じはするが、本人が望むってんなら叶えてやるだけだからな。
俺に叶えられる望みなら叶えてやりたい。
気持ち悪い片想いなんかを表に出すつもりはないけど、それでも許される範囲なら、ドラルクになにかをしてやりたい、と思う。
ペットキャリーの蓋をひらけば、ツチノコとかぼちゃがうれしそうに飛び出した。同じくうれしそうにしたジョンがそれを出迎え、三匹で城を探検しはじめる……。
おだやかにそれを見送るドラルクの顔は親のようで、いいな、といつも思うんだ。
いつかこうやって、大事なひとを眺めるんだろうな。こいびととか、子どもとかさ。
吸血鬼の城に向かう、というポーズとしては、演出として武器を身につけなくちゃならねえ。そう説明しても、ドラルクは仕方がない、あたりまえのことだとうなずくだけだった。ほんとうなら不快だろうに、やさしいおとこだよな。あまつさえ、俺が外した装備をいれておく台まで用意してみせるから驚きだ。もちろん武器の居場所を把握しておきたいだけだとわかってはいるが、それを気遣いだと見せることができる、っていうのは才能だろう。
そうやって身軽になれば、次は食堂まで連れていかれた。
無駄に広い城には、無駄に広い食堂がある。普段は食事を摂るのがジョンひとりとなると、寂しいにもほどがありそうだ……なにせ、俺がひとり増えただけじゃ変化はほとんどないんだからさ。ツチノコやかぼちゃが増えたところで同じである。
「聞いて驚けロナルド君。今日はデザートがあります」
「デザート?」
「うん。いつも通りには作ったけど、多そうだったらデザートのぶんおなかをあけておいてくれるかい」
「だけど、残すのは……」
「比較的日持ちする材料にしておいたから、気にしないでくれよ。なんならお弁当にして持って帰ったっていいんだぞ」
「弁当……」
うちでもドラルクの料理が食える、のは、うれしいかもしれないが……。あんまりうれしいことばかりだと、身の程をわきまえられなくなりそうだ。
考えておく、とだけ言って、テーブルに座る。ほどなくワゴンを押したドラルクが戻ってきて、食卓がどんどん賑やかになっていった。
シチューとパン。俺には詳しい料理の名前がほとんどわからねえけど、このパンはオートミールを使っているんだと昔ドラルクが力説していた。ほかにもサラダとか、細かいものがいろいろ乗っている。日本人は米が主食だと知ってはいるけど、どうせたまに食べるなら普段とは違うものがいいだろう? とかなんとか。オートミールのパンはしっかりしているから、シチューをつけて食べるのにちょうどいい。
「でも、なんでデザート?」
「そりゃあ、後のおたのしみでしょ」
「???」
ドラルクが隠したいなら、そうさせるだけだけど……。
俺の向かいでブラッドワインを傾ける吸血鬼は、なぜだかすでに満足そうだった。
食事中の会話は他愛もないものだ。新作のゲームが面白そうだ、このあいだ買うと言っていたやつはもうクリアしていて、俺にもやってほしいので貸したい、もしくはここでやるのとどちらがいいか、エトセトラ。
友人というものがいるのなら、こういう会話をするんだろうか。
ドラルクが俺になにを求めているのかはよくわからねえままだけど、うまく演れているならいい、と思った。
ドラルクの料理はおいしい。んだと思う。
胃の容量を気にしろと言われたのも忘れてぱくぱくと平らげちまうから、たぶん。
「今日も口に合ってよかった」
「ん。……うまいよ」
ちゃんと言うのがマナーだったか。
シチューの器が底を見せはじめたところで、ドラルクが腰を上げる。
デザートの時間らしい。ちょっとだけそわつきながら、のこりのシチューを食べるのに集中するふりをした。でも、なんでデザートなんだろうな。ジョンはダイエットしないとだから、作りたい気分でも食べさせてやれなかったのかもしれねえ。
「お待たせ、ロナルド君」
「……それ、実物はじめて見たな」
「それ? ああ、クローシュのことか?」
手袋越しの爪が鉄製のフタをつつく。クローシュって言うのか。知らねえそんなの。
クローシュの乗った皿は大きく、食卓のけっこうな場所を占領した。腹を空けとけ、ってこういうことだったのか。これは食べきれないかもしれない。
「なんでわざわざ?」
「そりゃあ、とくべつだからに決まってるさ。――誕生日おめでとう、ロナルドくん」
「え……」
誕生日。
誕生日?
クローシュの中から現れたのは桃のタルトだった。それも、実がごろごろ乗ってるでかいやつ。なんで桃なんだ?
疑問が頭の中にいっぱいで、ありがとう、もうまく言えやしない。
「え……と、……ドラルク?」
「……君の誕生日を、八月の八日と見てな。やっぱりネットの情報なんか鵜呑みにはしちゃいけなかったかい?」
「いや……それはデマじゃない、けど。だけど、理由がないだろう」
「あるよ! 私が君の誕生日を祝いたかった。そんなのふつうだろ?」
「ふつう……」
世間一般の『ふつう』に関して、吸血鬼であるドラルクのほうがなぜか詳しい。
だから今回も、たぶんドラルクのほうがただしいんだろう、とは思う。
「本当はもっと、プレゼントとかも用意したかったんだが……気付いたのが遅くてね。今日君の約束を取り付けられたのも、ほとんど奇跡だと思ったよ」
この時期は桃が旬なんだ。そう言ったドラルクが、ホールのそれを切り分けていく。
「無理に全部食べようとしなくていいよ。君が一番に好きなだけ食べたら、ジョンやツチノコにも分けてあげよう」
「……うん」
誕生日を祝われるのがはじめて、なんて訳じゃない。
だけど、吸血鬼に……、すきなひとにそんなことをされるのは、はじめてだ。
じわりと涙が浮かびかけるのを、ドラルクは見て見ぬ振りで流してくれた。
そういうドラルクの善良さに、俺はどうしようもなく救われている。
だけど、それは勝手な俺の都合で、ドラルクには関係のない話だ。調子に乗ったり、ましてや味を占めてよりかかるなんて、絶対にあっちゃいけない。うまく飲み込んで、なんにもないふりをして、笑わなければいけないとわかっている。
わかっている、けど、どうしても我慢ができなくて、疑問が口から出ていた。
「――なんで、こんなにしてくれんの」
それを悔やむよりも先に、ドラルクがやさしく笑う。
「そりゃあ、君を愛しているからさ」
「……あ」
――あの三匹を見送ったときとおなじひとみ。
ぞわぞわとなにかが背筋を走る。呼吸が浅くなって、涙が溢れて止まらなくて……。感情の処理が間に合わない俺を、ドラルクは背中を撫でてあやしてくれた。
「それは無理だ」
すこしあと。
涙を落ち着かせて、桃のタルトをおいしくいただき、食後のお茶を嗜んでいる。
プレゼントにはならないけど。そう前置きしたドラルクは、『ちゃんとした』俺の退治に同行したい、と言った。
「どうして? 私の真の力は君も片鱗を見ているだろう」
「おまえを侮って、邪魔だと思ってる訳じゃないよ」
「ならどうして!」
ドラルクは荒くなった語気を恥じるように、すまない、とうつむく。
「だけど、……君の怪我をニュースで知るのはもういやなんだ。だから、お願い」
「……、」
「相棒なんだろう。……背中を預けてほしいよ。質問してもらえるのはうれしいし、困った仕事の時に呼んでくれるのもうれしいけど……本当に、君が死にそうだったとしても、私はなにもできないままじゃないか」
「……、……」
言い訳はいくらでも思いつく。
いままでひとりでやってこれたんだから、お前が手を出す必要はない。……なんか反感を買って喧嘩になりそうだ。
どうせ強いのなんか血を飲んでるあいだだけなんだし、日光とかではふつうに死ぬまんまじゃん。……俺は夜にしか戦わないから、これじゃあんまり脅せないか。
城に帰ったら出迎えてもらえるほうがうれしい。……いや、何様だ? これはねえ。
「……、」
「ロナルド君。聞いてる?」
「う」
うーん。
正直、さっきの衝撃で胸はひっくり返ったままだ。うまく声色を作れる自信もなく、結局俺は素直に言うことにした。
「……お前は、たのしいことが好きだろう。それはたまたま、いままで知らなかったから、たのしいって思わなかっただけのことかもしれない」
「う、うん?」
「退治に行って、お前の知らないような連中がなにしてたのか理解してさ。……で、それをお前が『たのしそう』だと思ったなら……俺はお前を退治しなきゃだろ」
「………………、うん?」
「お前を退治しなくていいように相棒ってことにしたんだ。なのに……そうなったら本末転倒じゃないか。だから無理だ」
「……あー、ええと。ロナルド君」
「なんだよ……」
あたたかい紅茶はおいしい。こくりと喉を潤すあいだ、ドラルクはうんうん唸ってなにかを考えている。
「ドラルク?」
「……私、君が思うほど無知じゃないと思うんだけど?」
「でも、人間の剥製とか知らなかっただろうが」
「いやまあ、そんな具体的なものは知らないけどさ!? ……反人間の連中がどういう思考でなにをしてるのか、知らない訳じゃない。昔からそういう連中はいたからな」
「……、」
「そして、私はずっと、そういうのが嫌いだ。ゲームのほうが圧倒的に面白いよ」
「……うん」
そうであってほしい。
そうであれないかもしれないものは排除したい。
それを素直に伝えると、ありがとう、とドラルクは微笑んでくれた。
「でも、私も胸を張って、君のパートナーだと言いたいよ。公私共に、ね」
「パー、トナー……、って」
「え? そうだろ、私は君に気持ちを伝えて、君もうなずいたよな?」
「へ、あ、うん? まあ……、」
気持ち。まあ、愛していると言われたのはうれしかったけど……公私共に、なんて、あまりにも行きすぎている。それじゃあ友人なんか通り越して、こいびとどうしかのようじゃないか……。
――こいびとどうし?
あいしている……。
「待っ……てくれ。……その、そういう意味……だ、った?」
「え、うん。……え!!!???」
「声デカ」
「デカくもなるわバカバカバカ!!」
きいと叫ばれて身をすくめる俺に、ドラルクはがしがし頭を掻いて気を散らした。せっかくきれいにセットされた頭がぐしゃつくのも気にせずに、俺をじっとみつめるあかいひとみ。魅了のちからがある訳でもないのに、身体が動かなくなる。
「ロナルド君」
「……?」
「私は君が好きだよ。愛している。誕生日だと知って祝ってあげたかったし、べつに誕生日じゃなくたって、いつだってふくふくと微笑んでいてほしいと思っている」
「うぇ」
「だけど、それは君から退治人を奪うことじゃないとも思っている。だから、きみがすこしでも笑顔でいられるように、君をもっと支えたいんだ。仕事に同行させてくれ」
「ド、あ」
「でも、すぐに答えは出さなくてもいいんだからな。私は君の答えをいくらでも待つ。君が振り向いてくれるように、いくらでも努力してみせるよ」
「待……まってくれ、ドラルク」
「うん」
「うん、って、そんな……」
そんな、ことを、言われても……。
ぐるぐると視界が回る錯覚に、思わず頭を抱えていた。急展開についていけない。
ドラルクが好き。
俺を?
愛している、だなんてまっすぐ言えるほどに……。
「……俺は」
「うん」
「お前に、嫌われていると、思っていた。お前の日常をブチ壊した、迷惑者だと……」
「そんなふうに思わせていたのか……ごめん。そんなこと、私は思っていないよ」
「……それでも、なにかの天秤にかけて……頭数に入れるのは便利、ぐらいのもので、それでもいいとも思ってたんだ。そんなことで罪滅ぼしになるなら楽すぎるな、って……でも、お前は、お前のそれは、ただの好意でいてくれたのか」
「ああ。そうだよ」
「……こんな思い違いをしている相手でも?」
「もちろん。私が好きになったのは君だからね」
腹に収まらなかったタルトは、乾かないようにとまたクローシュに覆われている。桃は柔らかくて甘かったし、生地は反対に甘すぎなくて、食べやすかったと思う。
味見のできないドラルクは、きっとジョンに頭を下げて、手伝ってもらったんだ。俺のために。俺だけのために……。
「……、」
「ロナルド君。……君が私に予定を合わせてくれるのは、ただ罪滅ぼしのためだけ? それとも……、私と会いたいと思って、忙しい予定をわざわざあけてくれていた?」
「それは、……違う。俺が、お前に会いたかったから……」
「ほんとうかい!」
ぱ、とうれしそうにされると困っちまう。
そういう顔をさせられるような相手ではない……だろう、こんなの。
俺がずうっとただのやさしさだと侮っていたものが、とても大事なものだったんだ。憤ってあたりまえだし、叱責されて然るべきだと思う。
「勇気を出して良かった。それこそ、君が私に会いたがってくれている、って確信を持っていられた訳じゃないからね……君のことばが聴けてうれしいよ!」
「……っ」
「さっきも言ったけど、答えを急がなくっていい。君が、君のために選ぶんだ」
そうじゃなきゃ、私はうれしくなくなっちゃうよ。
ドラルクはそう言って、穏やかな所作で席を立つ。
「ジョンたちに声をかけてくるよ。タルトを分けてあげてもいい?」
「あ、ああ……。もちろん」
はふ、と詰めていた息を吐いて、緊張を自覚した。
俺がそうなっていることは、きっとドラルクの本意じゃなかったんだろうことも。
「あー……」
断ることに意味はない、そうわかっていても、うなずくことに納得もできなかった。自分は異分子である、っていう刷り込みがそう簡単に消えてくれるとも思えねえのだ。
だから、もっと話がしたい。
あいつらがタルトを堪能したあと、もし、ふたりきりになる時間があれば……。
「……ふたりきり」
……俺はふつうの顔でいられるんだろうか?
クローシュにうつるいびつな顔は、とてもみられたものじゃなかった。
赤い退治人を狙い撃ち!4の展示作品でした。
イベントから来られた方はこちらへどうぞ。
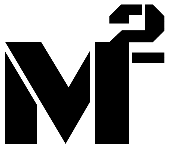

コメント