「手、出せ」
ぐ、とこちらに拳を向けて、ロナルド君はそう言った。
「手?」
無言で頷く彼の顔は、まったくの無である。ぶっちゃけ怖い。なにをされるんだ、私は。でも、彼が私を害すことはない、と思う。
「てのひらを上に」
「うん、ん?」
かちゃり、とふたつの鍵が落とされた。
「事務所と、俺の家の鍵」
「え」
「引っ越しはしねえ。けど、……うちに来るのは許してやる」
「え、……え!? うそ、いいのか?」
わあ、わああ!!
やったあー!! 私、招いてもらえるんだ、彼の家に!!
「うふ、うふふふふ」
「キモ……」
「うん、うんうん! へへ、うれし……い……、な?」
うれしい、うん、うれしいんだけれど。
彼はなんと言ったっけ。
「……引っ越してきて、くれないのかい?」
「……、」
彼はすこし、ほんのすこしだけ、申し訳なさそうな顔をする。
「……悪い。退治人として、譲れねえ。あの街で活動する理由がある」
「……、」
「通勤をお前に頼るのも、受け入れられねえ。……その代わり、に」
浮上した気持ちが、沈む。もちろんね、彼は退治人として誇りを持っているし、そんな彼が好きなのだから、否定することはできないけれど。
「……要らなきゃ、棄てろ」
「要る。……要るよ、ぜったい捨てたりなんかするもんか! ありがとう」
それが彼の信頼のかたちであることに、変わりはないのだ。
「邪魔するぜ」
「はぁい、いらっしゃ――、?」
いつもどおりのロナルド君は、いつもと違う子を引き連れていた。
すっかりもとの髪型に切り揃えられた銀糸を揺らし、彼はその子へ振り返る。
「ヒナ」
「……、失礼する。私は、神奈川県警吸血鬼対策課……副隊長の、ヒナイチだ」
「吸血鬼対策課……、」
赤毛の少女、だった。
見た目は普通の女の子だ。すこし小柄で、腰に揃えた日本刀が、幼さの残る雰囲気と何故か同居している。多分私服なのに、帯刀していていいのかなあ?
それだけなら、まあ、うん。彼にも交友関係があったんだなあ、というだけだが。
しかし、彼女は。
「……前に言ったろ。片割れのいない吸血鬼殺し」
「……、ああ。いらっしゃい、おふたりとも」
ううん。
名乗ってこそくれたんだが、警戒がすごい。
いやまあ、殺気だったら死んでるからね、そこまでじゃないのはありがたいけど。
彼女はすこしだけ逡巡してから、ずんずん進んで置いていくロナルド君の様子に、覚悟を決めるような頷きを見せた。
「邪魔をする!」
「はいはい」
けっこう元気な子みたいだねえ。
クルースニク。
白い羊膜に包まれて生まれる昼の子。
黒い羊膜に包まれて生まれる夜の子と対になり、殺し合う運命をもつ。
けれど、彼女は――対の子が、クドラクが見つからないのだ、という。
「――べつに、だからどうということはない、と思うんだが」
退治人か、吸対か。吸血鬼と対峙するための身分。ロナルド君は前者、彼女は後者である、ってことだ。だけど。
「吸対として、たくさんの吸血鬼と対峙したが。……クドラクは、どこにもいない」
私の淹れた紅茶を睨みつける彼女は、やはりというか、不安げだ。
「君はたしかに、クルースニクなんだね。私もわかる、というか、高位の吸血鬼なら、ひと目見ればわかるだろう。……だが、君の名前はヒナイチ君だ。だろ?」
「……、ああ」
「なら、それでいいじゃないか。君は君だもんな。それにさ、殺し合いなんてしないほうがいいに決まってるし」
「ハ。吸血鬼の言うことかよ」
ヒナイチ君の言葉を静かに聞いていた、ロナルド君の茶々入れは適切なタイミングだった。なるべく空気を軽くするように、マントで口元を覆ってみせる。
「君が言う〜? うちほどの穏健派は居ないんだぞ」
「俺だから言うんだ。どれだけ退治してきたと思ってる」
「九九九、プラスアルファ」
「そ。そんだけクソがいたんだよ」
茶請けに出したクッキーを、ロナルド君がつまみあげる。ヒナイチ君の視線がそこに釘付けになっているのを確認してから、彼は口に放り込んだ。形のいい歯が齧り取り、咀嚼する。ぺろ、と赤い舌がくちびるを舐めとる様がいやらしくなくて、彼が彼女をどう思っているのかが理解できた。
きっと、妹のように大切にしているのだ。
これに毒なんかない、うまいぞ、と教えるための咀嚼。
「うまい」
「そう、それはよかった。私腕上がっただろう?」
「かもな」
端的だけれど感情の乗った声音に、ヒナイチ君がごくりと喉を鳴らす。
「君もお食べよ」
今度は私に促されて、彼女は視線を泳がせた。
本当に、吸血鬼の出す食事を食べていいのか、という疑問と。ロナルド君への信頼――彼が食べているのなら大丈夫だろう、という推測。そのふたつのあいだで揺れているのがよくわかる。真面目な子だ。
「ヒナ」
「……うむ。いただこう」
そうっとつまみ上げた、ジャムの乗ったクッキー。あ、ブラッドジャムじゃないよ、もちろん。それを口に入れた瞬間、彼女のアホ毛がぴん、と立った。
「ほいひい!」
「ウワすっごい勢い!?」
バリバリむしゃむしゃむしゃあ!!
両手を使って次々とクッキーを口に放り込んでいく彼女に、説明を求めてロナルド君へ視線を動かすと、彼はやれやれ、みたいな感じで微笑ましそうに眺めている。
「クッキーモンスターって呼んでやれ。こいつはかなり食う」
「ええ……うん、まあ、喜んでもらえてなによりではあるんだが」
「おいしい! おいしい!」
あっという間に、山盛り用意していたクッキーの姿が消えていく。真面目な子、みたいなんだけどなあ。食欲は昼の子の三大欲求に数えられるものだし、仕方ないのか。
「ロナルド! おいしいぞ!」
「そうかよ。それを言うのは俺じゃねえだろ」
「んぐ。……おいしいぞ、ドラルク!」
「……、心配だなあ」
この子はこの子で、壺とか買わされやしないだろうか?
ぱああ、と花咲くように笑う彼女は、まるで向日葵のようだった。
こんな子が。
どうして、殺し合いなんかしなければならないのだろう。
「……、」
ロナルド君を見れば、ゆっくりと頷かれる。
「ヒナイチ君」
「うん?」
「君さえよければ、たまにおいで。私がロナルド君の事務所にいるときもあるから、事前にRINEしようか。交換してもいいかい?」
「……! ああ!」
そうして、連絡先を交換して、ついでに私とロナルド君とヒナイチ君のグループを作ってみたり。ジョンを紹介して、丸の虜がまたひとり増えたりなどして。
すっかり打ち解けた彼女が、こそりと個人チャットを飛ばしてくる。
――ありがとう。
――うん? どういたしまして?
――クッキーもだけどな、ロナルドが。あんなふうに笑うようになって、うれしいんだ。いつもあいつは、ずっと……いろんなものに、追われているようだったから。
ああ……本当に、どうしてこんな子が、そんな運命なのだろうね。
「うーん、心配だなァ……ジョンについていってもらえばよかった」
「過保護だな。刀持ってただろ、あいつ」
「そうは言ってもなあ。いくらクルースニクでも、女の子には変わりないだろうに」
「……、」
「?」
ヒナイチ君は、朝日が昇る前に帰っていった。窓のないロナルド君用の客室で、ふたりでシーツに包まっている。
女の子には変わりない。そう言ったら、ロナルド君が静かになってしまった。もしかして、あの子を女の子扱いするのって、あんまりよくないのかな。だけど、嫉妬をするくらいなら、ここにわざわざ連れてくることはないのだろうし。
彼の意図を図りかねていると、ロナルド君がふう、と息を吐いた。
「……、あいつは」
ぽつり、と落とされた言葉を、うん、と頷いて受け止める。
「まだ……一九だ。俺の妹と……同じくらい、で」
「……、うん」
「……なのに、……」
なのに。
「はじめの頃は、……正直、羨ましかった。クルースニク。絶対の退治人。あいつが負けるっつうことは、まずありえねえ。だが――」
「……負ける、っていうのは。命を落とすことはない、という程度なのかな」
「……そうだ。催眠にはかかるし、魅了も喰らう――命に関わらないからどうでもいい、なんて思われてるってことなんだろうが、よ」
絶対の退治人。
そもそも、だ。
どうして、ロナルド君が作家業なんてしているのか。ロナルドウォー戦記の、役割。
吸血鬼は退治人に敵わない。
そういう、明確なルールを作ってしまえばいいのだ。
敵わない相手に挑む事を、蛮勇である、と。
そうすれば、人を襲うことなんてなくなるだろう――という、ある種、無垢な。
エンターテイメントの皮を被った、願いの結晶。
「俺は、いいんだ。退治人の連中だって、覚悟ありきでこの仕事をしている」
「……、そうだな。出来れば、ちゃんと生きて帰ってきてほしいけど」
「努力はしてるだろ。……でも、あいつは」
「あの子は――」
ただ。
ただ、白い羊膜に包まれて生まれた。
ただ、それだけのことで。
「……元々、家が道場だとか。兄貴も吸対で仕事してる、だとか。そういうことを、あいつは言っちゃあいたけど、よ」
「でも、……そうだね。彼女は、クドラクを探している」
かく、と頷いて、彼はくるりと丸まった。
「クドラク――なんて、いなけりゃいいのに、な……」
クルースニク。
生まれた時の羊膜を携えれば、クドラクに――あるいは、吸血鬼に。けっして負けることはない、絶対の退治人。
だけど。
だけど、彼女がいつ、そんなものになりたいと言ったのだ。
「……、俺は。俺は、個人の退治人だ。それでも、デカい捕物があれば組合の要請も請ける。そういうときには、吸対も出動してる」
「うん」
「……、守ってみせるさ」
「うん、……うん。な、私も呼びたまえよ。一緒に守らせておくれ」
「お前はデカくて嵩張るから邪魔だ」
「えー!」
くふ、と笑って、彼は私の胸元にこつりと額を寄せた。
□■□■□
「ロナルド君。ロナルドくん?」
呼び鈴を鳴らしても、ドアをノックしても無反応だったので。仕方なく、貰った鍵を使うことにする。私は呼ばれて来たんだから、怒られることはなかろう。
そう、私は彼に、招かれているのだ。
「ロナルド君」
扉を開けると、ツチノコが首を傾げて待っていた。靴を脱いでみせれば、ついてこいとでも言うかのように部屋の奥へと進んでいく。靴箱の上には、帽子を被せられたかぼちゃ君がいて、じろりと私を睨んでいた。
そのひとみにひらりと手を振ってみせてから、ツチノコの背中を追う。
セーフハウスのなかで、もっとも私の城に近いものを選んだ、らしい。この部屋はひどく狭くて、彼の年収ならもっといい部屋を取れたはずなのだ。彼はあれだけの部数を売り上げてなお、ひどく質素な生活を好む。
作家業が金のためではないのだと、彼をここまで知るものなら皆が理解するだろう。
「ロナルドくん」
彼は丸くなっていた。
部屋が質素なら、寝具も質素だ。なんてことはない、敷布団。フローリングに敷くのは身体を冷やさないか、ちょっと心配なんだよなァ。今度、勝手にベッドを贈ろうかな。受取拒否とかされないように、私がいる時を指定して配送しよう。
「ロナルド君。来たよ」
「んゥ……」
ゆっくりと、深海のようなひとみが覗く。ぼんやりとしたそれは、まだまだ彼が眠りに囚われていることを伝えてくれた。ゆらゆら揺れて、ゆっくりと、私を捉え。
「……ん」
「んん?」
かぱ、とその両腕がひらかれた。
「え、っと。ロナルド君?」
「ん」
ん、と言われても、だ。
ええと……、なんかさ、抱きしめてくれって、言われているみたい、だが?
ぐぐ、と彼の眉根が寄る。それはさ、私が腕の中に入らないから、ってことで、いいんだろうか。わかんないなあ……。
「ロナルド君、寝てるだろう」
「ん」
寝てるんだ……。
うーん。
私もねえ、フローリングに直で寝たらつめたさで死ねるんだよな。
と言うわけで、彼の布団にお邪魔しよう。覆いかぶさるようにして、彼の腕のなかに体を収めてみる。
くふ、という、いつもの彼の笑い声。それが耳元で奏でられると、すぐに寝息へと変わってしまった。
は?
「え」
「……、」
「待って。待って、寝ないでくれロナルド君」
いや寝てたんだけどさあ!
すう、すう、と穏やかな吐息がして、まあそれはいい。彼が安らかに眠れているというのは、まあ……いい、うん。私が抱き枕にされる程度で、それが保たれるというのであれば。
でも。
でもだ。
それと、私のちんちんがイライラするのはまったく別問題なのである!!
ぎゅう、と抱きしめてくる彼の腕は、私を害さない。眠りに落ちてさえ、私を絞め殺さないのだ。だけど、絞め殺さないというだけで、私が逃げられないようにはされている。いや、マジで振り解けない。身動ぎもできないが、とりあえず苦しくて死ぬような体勢ではないから、彼が目覚めたら砂を抱いていました、なんてことにはならないのだろうが……。
「ロナルド君、なあ」
「……んー」
今日、まだロナルド君の声、ん、しか聞いてないんだけど。
私がしつこく声をかけるから、それがお気に召さないみたいだった。彼はぐずるようにその銀の御髪を擦り付けてくる。私の触れる唯一の銀がさ、そんなふうにふさふさっとさあ、あああ!! 失礼、興奮しました。
ぐりぐりと押しつけられるのに耐えていると、不意にその動きがピタリと止まる。
ん?
「………………、」
「あれ」
もしかして。
「……起きた?」
「……、ぉぅ」
「声ちっさ」
ンフ、と噴き出すと、視界の端に映る耳が、じわじわ赤く染まっていく。
「おはよ、ロナルド君。喉乾いてない? なにか飲む?」
「……飲む」
「そっか。じゃあ、離しておくれよ」
ゆるり、と名残惜しそうな両腕から力が抜けていった。ありがとう、と声をかけると、返ってくるのは悪い、という謝罪なものだから。
「なにが?」
「あ?」
「悪いこと、べつに君はしてないだろ」
「……? いや、でも」
「嬉しかったよ、君から抱きしめてもらえて。今度は起きてるときにしてくれたまえ」
「――、」
もふ、と銀糸をかき混ぜて、なるべくやさしく声をかければ、彼はまた、ん、と吐息で返事をするのだった。
寝過ごした。まあそれはいい。
それはいい、として、だ。
夢だと思った。夢ならば許されるだろう、と。
思っクソ現実だったんだが!?
ウスバカゲロウおじさんは嬉しいとかなんとかほざいていたが、俺のプライドはそこに考慮されていないのだ。
おかしいだろう。
成人を過ぎた、大人の男だぞ。
それが寝ぼけて、抱きしめるようにねだる。いや、無理だろ。気味が悪いにも程がある。ガキじゃねえんだ。自立した、社会人をどうにかこうにかやっているってのに。
あまつさえ、今度は起きてるときにしてね、などとあれはほざいていた。
無理だろ。
コイビトだとか、そういう名目があったとして、だ。
俺はそういうものではないだろう。
カラカラと、氷とグラスが当たる音がする。
「ほら、アイスティでよかったかな?」
「……ありがとう」
やめろ。
なにもなかったみたいに微笑みかけるな。
情けないとか、恥ずかしいとか、そういうふうに煽られでもすれば、笑い話として昇華できるかもしれねえっつうのに。
そうやって、当然のことみたいにするんじゃねえよ。
と、胸中でぐるぐる考えたところで、俺の口から出たのはさっきの礼だけだった。
銘柄もよく知らねえ、あれが勝手に俺の家に置いて行った茶葉。
紅茶なんだな、っつうのはわかる。組合じゃいつも炭酸飲料ばっかりで、こういうのを飲むようになったのはあれと知り合ってからだ。だから、紅茶だということはわかったところで、どういう茶葉だとか、産地がどうとか、なにも知らねえ。
だとしても。
『ロナルド様』が、『相棒の吸血鬼』に『紅茶を淹れられている』。
そんな情報は、ロナ戦には必要ねえ。
だから、描写のために勉強する必要も、ねえのだ。
あれが淹れる紅茶はうまい。
そんなことは、俺とジョンと、ツチノコだけが知ればいい。叶うならばかぼちゃにも教えてやりてえけど、口を彫らなかったのは俺のミスだし、今から口を掘ろうとするのはなんか、オペっぽくて怖えし。
まあ、あのクルースニクとか、教えてもいいだろうってヤツも居ないことはねえけどさ。それはそれ、あくまで、俺が知らせてもいいと思ったヤツだけが知っていれば、それでいいだけの話。
絶対に、知られたくないヤツもいるのだ。
「ロナルド君? まだ眠い?」
「ああ……、いや」
せっかく、あれが冷やしてくれたんだった。グラスを傾けると、睡眠により体温の上がった身体が冷まされていくのがわかる。
もったいねえな、とは思いつつ。身体が求めるままに、ぐいと飲み干す。
「わお、いい飲みっぷりだ。おかわりいるかい」
「いる」
グラスを返せば、勝手知ったる吸血鬼は引っ込んで、これまたあれが勝手に持ち込んだティーポットを傾けている。ひとつのグラスに紅茶、別のグラスに氷をいれると、紅茶を氷のほうにまとめた。その手間は無駄では? と首を傾げていると、元のグラスに氷ごと紅茶が戻されていく。カラカラとさっきと同じ、グラスに氷が当たる音。マドラーとかでかき混ぜているのではなく、氷と紅茶が流し込まれる音だったようだ。
氷はみるみる溶けていって、紅茶を冷やして消えた。
「どうぞ」
「おお……」
わざわざそんなことするのか、と思う。
どう考えても、ひとつのグラスで混ぜた方が楽じゃねえか?
マドラーひとつ洗うのと、洗うグラスが増えるのだったら、前者のほうがいい気がするんだが。わからねえ。あれがいるうちは洗い物もあれがやる。テメーでやろうとすると、「私の趣味を取らないでくれ」と眉を下げられてしまうのだ。
わざわざ。
ああして淹れられた紅茶を、俺はあっという間に飲み干したのか。
「……、」
「ん?」
もったいない、な。
わかっている。このまま飲まずにぬるくなってしまうことのほうが、はるかにもったいないことだ。さっさと、この温度が失われる前に飲み干してやるべきで。
だが、まあ。ちょっとぐらい、見つめていたい気分になってしまった。
「――、なあ」
「あ?」
だというのに、空気の読めない吸血鬼が、く、と俺の顎に手をかける。
顎に手をかける?
「は、」
違和感を覚えたときには、くちびるが塞がれたあとだった。
吸血鬼特有のつめたいくちびる。しかし、俺のくちびるもアイスティで冷やされていて、大きな温度差を感じることはない。
ただ触れるだけの。だというのに、児戯のようなものではねえ。むに、と角度を調整されている。かたちを確かめるようなそれ。
「ん、ゥ――」
顎にあったはずの手は、いつの間にか俺の後頭部を抱えていた。片方だったはずのそれが両方になって、逃さねえと言わんばかりに、だが、やさしく。
舌が突っ込まれてもおかしくねえのに、あれは、ドラルクはそうしなかった。
「……、え、っと。すまない、衝動が抑えられなくて」
「あ……?」
ゆっくりと顔を離して、もういちど、ごめん、と言われる。
「ごめんね。ツチノコの前で」
「……、あ!?」
あ。
あ!!
慌てて探したツチノコは、必死に壁を向いていた。
「て、めえ」
「ウワーッごめん、ごめんなさいー!」
ぐ、と拳を握る。握るが、振り抜くことはできなかった。だって、こいつが今日、どれだけ死んでるのかわからねえのだ。実は城でかなり死んだ後でした……とかで、依頼に間に合わねえなんてことがあっちゃならねえ。
そう、そうだ。そもそも、こいつを呼んだのは、依頼があるからで。こっちからのほうが近いから、早めに来られるなら来ていいぞ、と連絡したんだった。
情けなく頭を下げて謝っているドラルクに、おい、と声をかける。
「支度しろ。もう出るぞ」
「えっ。あれ?」
ぐ、と。もう一度、紅茶を一気に飲み干す。呆けたドラルクの横を抜け、シンクにグラスを置いた。洗うのは後でいいだろう。
テキパキと退治人衣装に着替えていく俺を、あれはなぜか目を丸くして見つめていた。なんだよ。言いたいことがあるなら言え。
「さっさとしろ。置いて行かれてえのか」
「あっ、いや! 待って待って、置いてかないでー!」
結局、ドラルクが『言いたいこと』を言ったのは、退治のすべてが終わって、帰路につこうというときだった。
曰く、せっかくいい雰囲気だったのに、急に仕事モードになるからびっくりした、ということらしい。
「おまえといい雰囲気になるより、仕事のほうが大事だろう」
「……、そうだよね。君はそういう子だよね……」
□■□■□
――うつくしい、白馬だった。
ひとつだけ、たてがみのうちにぴんと跳ねた房がある。それがまるで、ユニコーンのようにも思わせるような、そんなうつくしい、白馬。
ロナルド君が、呟く。
「――だ、めだ……」
彼女が、負けることはないのだろう。
それでも。
「だめ、だ。……だめだ」
傷つくことがないわけでは、ない。
「ダメだ――ヒナ!」
彼女は、ちろりとロナルド君を見遣り。
ドガ、とその後ろ足で、彼のことを蹴り飛ばした。ノーガードだったのだろう、ロナルド君はまっすぐ私に向かって吹っ飛んでくる。硬い鱗で受け止めるよりも、砂になったほうがよかったのかも。死にやすさのオンオフができればいいのに。
鼻先でロナルド君をつつく。大丈夫だ、という言葉と共に撫でられて、一応信じてやることとして。
もう一度、彼女のほうへ視線を向ける。
結末がたとえわかっているのだとしても。
目を逸らしてはならないと、私も彼も、思っていた。
ロナルド君からの呼び出し。
一年の時を経て復活したそれは、頻繁になったり、まれになったり。呼ばれないまま勝手に彼の事務所を訪れていたら、飛び込みの依頼が来ることもあった。
そして、もうひとつ。
彼から、わざわざ『絶対に来るな』、という連絡があったときは、大捕物が行われるときである。はじめにそれが来たときに、好奇心からふらふら顔を出してしまったんだよ。それも、あらかじめ吸血せずに公共交通機関を使ったせいで、私はいつもどおりすぐ死ぬ吸血鬼で。当然のように乱戦のなか私は死んでしまい、彼にまた塵を集めさせる手間をかけてしまった。
真顔でキレる彼は超畏怖かったので、めちゃくちゃいい吸血鬼になると思います。
と、いうわけでだ。
絶対に来るな、というロナルド君からの連絡、と。
もうひとつ――ヒナイチ君からの、しばらくそちらに行けなさそうだ、という連絡。
そんなのさあ、彼らの街でなにが起こっているのか、明らかじゃないか。
ロナルド君についていくため、質の良いブラッドワインを用意するようになって久しい。いまだに全盛期の力は取り戻せないし、コンスタントに飲んでないとすぐあの脆弱さに戻ってしまうけれど、だ。血を飲んでから力を取り戻していられる時間が、すこしずつだが長くなっている。
彼を守りたい。
彼が、守られるようなものではないとわかっているけれど。
誰かを守りたいと、彼が思うのなら。
そんな彼を守ってやりたい。
そう思うものが、ひとりくらい居たっていいだろう。
……、いや。
ひとりじゃないな。ジョンはもちろん、ツチノコも、かぼちゃ君も、そう思っているに違いないのだ。
そしてそれは、彼のまわりの人間たちだって、そうであるに違いない。
新横浜ハイボール――退治人組合の片隅で、飴を咥えたまま腕を組む。
吸血鬼対策課との合同捜査。声を張り上げるヒナは、相変わらず兄貴に仕事を押し付けられているようだった。ヒナはあくまで副隊長で、その兄貴――カズサ、とかいう男が隊長をやっているはずだが。前線に出て来ているところを、俺はほとんど見たことがない。こういうときに、音頭を取るのが隊長の仕事なんじゃねえの。
魔都、とまで呼ばれるこの街で、たかだか高位の吸血鬼程度でこんな戦線が組まれるこたあねえ。もちろん、そうなるだけの被害が出ているわけだ。
来るなよ、と連絡したザコの顔を思い出す。
「――、 。 、 。――」
ヒナの言葉に、童顔の男が挙手のうえで質問をした。興味がねえ。ヒナは真面目だから、あの男の言葉にふむ、と腕を組む。
「…… 、 。 ?」
だりい。
作戦会議なんて、意味があるものかよ。
俺がここに居る必要なんかねえのにな。
ヒナの言葉に頷いた、童顔の男がこちらを向く。どうせこの男がいる限り、この男を出し抜くことなんか出来やしねえ。
「――なあ、ロナルド! お前さんもそう思うじゃろ」
「……、ああ」
聞いてねえけど、あんたが言うならそうなんだろ。
俺の返答に気をよくしたのか、童顔の男――兄貴がにか、と歯を見せた。
「俺たちが組めば一〇〇人力じゃからの!」
「あ?」
俺たち、だと?
いやいや、組むのが俺だと決まったワケじゃねえ。そう願ったが、兄貴が肩に腕を回してくるのですべてを察した。終わりだ。
組みたくねえ。
俺がいかに劣っているか、見せつけられちまう。
兄貴にそのつもりがあるのならまだしも、だ。そんなつもりは一切なく、ただ純粋な心配だとかで、守られちまう。
いやだ。
いやだが、仕事は仕事。
守られるような、隙を見せなきゃいいだけの話。
できるだろう、なあ。お前はロナルドだ。『ロナルド様』なんだぜ。か弱いガキは卒業したんだ。なら、できるはずだろう。
至近距離で、兄貴が微笑む。
「な!」
「……、」
笑え。
口角を上げて、目を歪ませろ。
ああ、とひとこと言うだけでいい。
凝り固まってしまった表情筋を動かそうとしたところで、ぎいと、扉が開かれた。
「お待たせ、ロナルド君!」
満面の笑みで。
吸血鬼らしい牙を見せ、吸血鬼らしい笑みを浮かべ、まっすぐに俺を見つめる赤い瞳。ばさりと大仰に翻したマント。
「……、あ?」
「ドラルク!」
あれの名を呼ぶのは、俺よりヒナが先だった。
紳士らしく礼をして見せる吸血鬼に、ギルドの視線が釘付けになっている。
当然、兄貴も例外ではなく。じい、とあれを見つめている。
だが、ドラルクはそのどれをも意に介さなかった。俺に向かってまっすぐに、躊躇いなく進んでくる。兄貴が回した腕さえ気にせず、もういちどお待たせ、とのたまうのだ。お待たせもなにも、呼んだつもりなんかねえのに。
実際、ドラルクがこの店に現れること自体は珍しくなくなっている。はじめての顔合わせの日、砂のテンションが上がりまくってそこらじゅうのギルメンに迷惑をかけたのは苦い思い出だが、意外と連中も受け入れているらしい。よお、なんて手をあげて挨拶をするものもいて、ドラルクは律儀にそれを返していた。
「すまないね。飛んできたんだが、飛行機と並走するのがちょっと楽しくて」
「……、お前は楽しいかもしれねえけどよ、あちらさんのコックピットはさぞ大混乱だったんじゃねえのか」
「はは、うん、多分なあ。全部終わったらお詫びの電話入れようかな」
「迷惑だバカ」
イタ電以外のなにものでもねえだろ。
いや、そうじゃねえ。
「来るなっつったろうが、お前」
「うん。でもヒナイチ君もしばらく来られないっていうから、相当なんだろうなあ、と思ってな。人手は多いほうがいいじゃないか?」
「なんで役に立てるつもりでいるんだ」
「役に立つさ。ちゃんとブラッドワイン飲んできたし。血液パックも持ってきた」
ドヤ、と胸を張るおっさんはかわいくもなんともねえんだが。
くふ、と笑みがこぼれる。重怠い面倒臭さが、霧散していく感覚。
「気張れよ。もう、塵は集めねえからな」
「ああ。頑張るよ」
――さて。
肩に回されたままの、兄貴の腕に触れる。
触れるだけでは、離れてくれなかった。仕方がねえから、ぐい、と押して、明確な拒否を伝えてみる。
「悪いな。コンビに関しては、こいつが先約だ」
「――……、仕方がにゃあのう」
俺も、兄貴も、大人だからよ。
営業スマイルにすべてを隠して、距離を取る。
バーカウンターへ向かう兄貴に代わって、隣をドラルクが陣取った。
「で? 今度はなにが出たって?」
「……、あー」
んん。
やべえ、聞いてなかったとは言えねえよな。
ちろりとヒナへ視線をやれば、あれはジロリと睨んでくる。
「ヒナのほうが、説明うまいだろ」
「……聞いていなかったんだろう、ロナルド」
言わねえお約束だろ、そこは。
コホン、と咳払いをして、ヒナがこちらに向かってきた。
「……事件としては簡単な、吸血事件なんだ。すこしずつ事件現場が移動していて、そろそろこの新横浜にも出没するかもしれない」
「ほほう。同じ犯人だとする証拠は?」
「ああ……一命を取り留めた被害者たちの、証言が一致しているんだ」
声を鋭くして、ヒナは言う。
「――『黒い獣に襲われた』、と」
「え」
「?」
ドラルクのそれは明らかに、何かを知っている反応だった。
それに、ヒナもどこか、覚悟をするような表情をしている。
黒い獣。
――、黒?
「……、あ」
クドラク。
黒い羊膜に包まれて生まれる夜の子。
黒い獣――狼や馬などに変身して、人を襲う。
「合同捜査のカタチを取るが――発見次第、私に連絡を」
白い羊膜に包まれて生まれる昼の子と、殺し合う運命にあるもの。
ゆっくりと、隣を見る。ドラルクもまた、こちらを見ていた。
絶対に。
絶対に、会わせちゃならねえ。
俺たちふたりで仕留めてやる。
「……それだけ判れば充分。行こうか、ロナルド君」
「ハ、……指図すんじゃねえよ」
並んで歩き出す。
そんな俺たちに誘引されるように、組合内部も騒がしくなった。こういうデカい事件の時は、ツーマンセルかスリーマンセルが基本だ。俺が跳ね除けた兄貴も、きっとほかの誰かと組むだろう。
それを確認はしない。
俺が共に在るのは、この吸血鬼だけでいいのだ。
おまえはいずれ吸血鬼と戦うのだよ。
そうはじめに教えられたのはいつだろう。
剣を習ったのは、強制されてではないと思っている。ただ、そうすることが自然な環境だったから、そうした。家が道場。兄さんも剣を振るう。ならば私も、と。
吸血鬼対策課へと配属されたのも、私が志願したことだ。兄の影響ばかりを受けているわけではない、というのは、おなじ隊になってしまったせいで信憑性が欠けるかもしれないけれど。でも、本当だ。
私はいずれ吸血鬼と戦うのだ、そう信じていたから。
そうしないことが、考えられなかったからな。
私は負けない。
白い羊膜の加護があるかぎり、負けることはないのだ。
そういう運命になっている。
だから。
だから、守るんだ。
もうひとりの兄のように、私をからかい、けれど見守ってくれる、やさしい垂れ目の退治人だとか。
傍若無人に振り回そうとする退治人に寄り添ってみせ、私にもあたたかな食事を振る舞ってくれる吸血鬼だとか。
私が、私として、大事だと思ったものたちを――守ってみせる。
□■□■□
とはいえ、だ。
そう簡単に見つかるようなら、新横浜に辿り着く前にどこかしらで捕まっている。
黒い獣――クドラクだって、警戒はしているのだろう。被害情報もなければ、目撃情報もない。前者が無いので、そもそもルートを変えている可能性もあるが。
初日はドラルクの城で待機だったジョンも、警邏に参加するようになった。ツチノコとかぼちゃは、変わらず俺の自宅で待機。移動に使う経費がもったいない、という理由で、クソザコウスバカゲロウは自宅に泊まり込むようになってしまった。
棺桶を持ち込みたい、とのたまうあれを、そんなスペースはねえ、とはぐらかす。実際、あのセーフハウスは狭い。狭いとわかりきっていて、あそこを選んだのだ。棺桶を置くスペースがない家。スペースを理由に、はぐらかしてしまえる家を。
そもそも、コイビトになるのだって恐ろしかったのに。
それでも、まだ。
まだ、コイビトのほうが、引き返せる気がする。
敷布団じゃ死ぬ、という言葉は嘘じゃねえだろう。きっと死ぬ。ドラルクの死亡回数は、できるだけ蓄積されねえほうがいいものだ。
「金は出してやる。好きに選べ」
「え、いやいや。自分で買う、っていうか、一緒に寝ようよ、どうせならおっきいやつ買わないか? 並んで寝られるようにさ」
「使用用途をなんだと思ってる? つうか、そっちのほうが棺桶よりでけえ」
「敷布団敷かなくて良くなるんだから、結果広くなるだろ」
あそこはセーフハウスだ。あくまでも、身体を休める場所であって、寄り添いあうための場所ではない。まかり間違って、セックスなんかするつもりもねえ。
もしも、その用途であるならば。貧弱なあれに合わせた家を用意し――、
「ッ、」
「?」
じゃ、ねえよ、違う。いまは、いまはそういうときじゃねえ。思わずかぶりを振ると、なにも知らない吸血鬼はきょとんと小首を傾げる。
早くしろ、とせっついて、いやそうながらもドラルクが選んだベッドを買う。ギリギリまであれは自分で買うと言っていたが、実際にカードを差し出す速度で負けなけりゃあいい話だ。俺の顔が売れていて助かった点として、サインひとつで配送がタダになった。いや、そんなもんをケチるつもりはねえんだけど、店側が受け取ってくれねえんだよな。ロナルド様に買っていただけるなんて、とかなんとか。
ぜひ組み立てまで、と言われたが、退治用品で怪我するぜ、と微笑んだら引いてくれた。家の場所がバレるという点については、特に気にしていない。
「意外。組み立てとか自分でやるんだ。アレかい、他人の作業が信頼できないタイプなのかい?」
「いや? 向こうも仕事だし経験だって上だろ、んなナメた口利かねえよ。……俺たちには普通の時間帯だし、店を開けてんのも向こうだがな、あちらさんにとっちゃああくまでも『夜勤』、通常の時間帯じゃねえ。その分多く対価を払うにしたって、自分でできる範囲なら自分でやってやったほうがいいだろ」
「はえー」
血を飲んでるから手伝えるよ、とは言われたが、血だって安かねえのだ。もったいねえから見てろ、とだけ言って、ツチノコとジョンで重石とする。
マニュアルを眺めながら部品を確認していれば、またもドラルクが、空気の抜けたような音を出した。うるせえな。
「なんだよ」
「いや……いや、うん。ゲームは説明書見ないのに、組み立てはマニュアル見るんだなあ、と……」
「はあ? チュートリアルはやってるだろ」
「いや、まあ確かに?」
「ド素人が勘で組み立てたようなベッドで寝てえの?」
「うん、ごめん、その通りですね。お願いします」
斯くして、想定組み立て時間の半分ほどで、ベッドが完成した。
セミダブル。
ドラルクがガリッガリなせいで、もしくはおかげで、ギリギリ二人でも寝れちまいそうな広さのベッド、だが。
「ロナルド君、こっ」
「おやすみ」
こっちにおいで、と言い切られる前に、就寝の挨拶をしちまう。俺を迎えるために捲られたスペースにはジョンを差し込み、自分はツチノコを抱えて。
悪いとは、思っている。
だが、俺には線引きが必要なんだ。
お前が嫌いとか、そういうことじゃあけっしてねえんだよ、と――そう言い訳をすることが、許されるのかどうかもわからねえ。
この街に――あの男が活動するこの街にいるあいだは、相棒の体でいたいのだ。
もの言いたげな視線を背中に受けながら、ぎゅうとまぶたをくっつける。
吸血鬼と人間が、情を交わすこと自体は珍しいことでもない。
それが問題なわけじゃねえ。俺、という個人の問題だ。
ロナルド。
レッドバレットの弟。
百発百中、天才的な銃の腕前を持つ退治人の、弟が。
たしかに銃は外れねえ。
だが、一発で仕留められるとは限らず。
剣を扱い、競り合うこともできる。
だが、それひとつを極めたものには敵わねえ。
半端な腕前を、誇張した文章で誤魔化すような未熟者。
そんな俺が、吸血鬼と情を交わしている、などと。
まっくらなまぶたの裏に、ぼやりと童顔の男の影が浮かぶ。
ロナルド。
なあ、ロナルド――お前さんは、退治人には向かんよ。
「……ッ」
やめておけ、やめておけ。兄ちゃんに任せりゃええんじゃ。
「――……、ァ」
本を出す? バカなことを。そんなことして、狙われたらどうする。
「ロナルド君」
おお、えらい、えらいのう! ……だが、心配じゃの。怪我をしないようにな。
「ロナルド君!」
「ッ、うるせえ!」
肩にかかる手を振り払う。
つめたい感触はすぐに離れていって、砂が散らばる音がした。ヌー、という、かなしい泣き声もする。
なんでだ。兄貴は吸血鬼ではないから、砂にはならねえだろう。そう思って――いま俺が振り払ったのは、本当に兄貴だったのか、と疑問が湧く。
「――……、あ?」
暗い部屋では、人間である俺にはなにも見えねえ。
けれど、おそらく、――いや、確実に。
「ドラルク」
俺を呼んだのは。
「ドラルク」
俺に触れたのは。
「ドラ……ルク、」
俺が殺したのは。
「ドラルク!」
「うん。お待たせ、ロナルド君」
つい、と伸びてくる、枯れ枝みてえなゆびさきを。今度は振り払わず、好きにさせる。それは俺の頬をなぞって、それからやさしく引き寄せる。
「ロナルド君。大丈夫だよ」
「……、あ」
「驚かせてしまったね、ごめんね。ね、こちらに上がってくるといい。こわい夢を見たときは、誰かと寄り添うのが一番さ。ジョンもツチノコもそう思うだろう?」
ヌ、という声と、ノコ、という声に、背中を押されるようだった。
ゆっくりと、乗り上がったベッドは狭い。
けれど。
「……悪い」
「なにが? 君は悪いことなんか、なんにもしていないよ」
「……、ふ。おまえは、そういうところが、……」
「え、なに? あれ、えーっ!? 寝ちゃう!? 待って待って、そういうところがなんなのさ!? き、気になって眠れん!!」
そういうところが。
お前は悪魔のようだ、と思うよ。
数日ほど、捜索を続けたあとである。
質素な通知音を鳴らす端末を取り上げて、彼は思いっきり顔を歪めた。
「どうしたの?」
「……見つけたらしい」
「!」
誰が、と確認する声がどうしても硬くなってしまう。
彼は渋面のまま、絞り出すような声でこう言った。
「……レッドバレット」
他人行儀に、彼はお兄さんの退治人名を読み上げる。その存在の話はずいぶん前から聞いていて、実際に顔も何度か合わせているんだけれどね。完璧な兄。彼はそう信じているし、評判もいい。そんなお兄さんが見つけたという割に、彼の表情はひどく暗い――つまり。
聞かなくても、想像はついた。それでもなるべく、いつも通りの声を意識して。
「そう。もう捕まった?」
「いや……取り逃がした、らしい」
「ふむ」
「兄貴が……、」
彼はもう一度、震えた声色で、兄貴が、と言った。
兄貴が取り逃がすなんてありえない、と思っているのだろう。
「ロナルド君」
「……、捕獲だから、だろ。殺すのが許されてたら、兄貴が取り逃がすはずがねえ」
そう信じたい、という声色。けれど、表情はだいぶ戻ってきたね。いつもの、人を喰ったような笑みを浮かべて、彼は言う。
「行くぞ。……おい、竜になろうとするな」
「んぇ? 飛んで行ったほうが早くない?」
「バカ、こっちじゃ竜なんかそうそう飛ばねえんだよ。警戒させてどうする」
「そりゃそうか」
でも歩くのは疲れちゃうよな。そう肩のジョンに声をかける。ヌンヌッテ、とかわいらしく応援してくれる愛しの丸に、ロナルド君の笑みの種類が変わった。おさなげで、純真なそれを見せてくれる、それ自体はとってもいいことなんだけれど。
ここ、街中なんだよなあ〜!
ああほら、道ゆく罪なき人がざわついてるよ。君さあ、ただでさえ顔も腕もいいのに、自伝なんか出してさらに名を馳せているんだから。
君に気付いて、あわよくば、なんて陰から見守っている、『まだ』罪なき人たち。
そんな彼らに見せつけるために、私は彼に近付いた。
「?」
ふふん。
ほうらみなさま、見たまえ!
本来は敵であるはずの、高位の吸血鬼たる私。そんな私が近付いて、目元の髪に触れた。だと言うのに、ただ首を傾げるだけのロナルド君を!
「おい。なにファーってなってんだ」
「ンフ、ふふふ」
「殺すぞ」
そんなこと言って、殺さないんだよねえ〜。
人間も同胞も、私を羨ましがっているのだ。それに気付かないほど、彼が鈍感なわけではないだろう。ただ、当然のことだと思っている。
私が、彼に触れることを。
あるいは、彼に触れられる私が、羨まれることを。
彼と私、それぞれの価値を理解した上で。
「――ったく。遊んでる暇はねーんだよ」
「はあい。すまないね?」
わざとらしくマントを翻した彼の、隣に並ぶ。
私が前でも、彼が前でもなく。
隣に並んで、歩くのだ。
まだ見ぬ黒い獣とあの少女のように、運命などで繋がれているわけではない。
けれど。
だからこそ。
私たちが歩く道を、私たちが決めることができるのだ。
アテがまったくねえ、ことはねえ。
プライバシーがどうのこうので、監視カメラをそこかしこに設置できるモンでもねえし、人の目には限界がある。どんな街にも、闇はあるっつうワケだ。
で。
そういうトコロのおおよそすべて、組合で共有されている。
おおよそ、なんだよ。
共有されてる場所なんか、どうせ後から行っても意味はねえ。
だから、俺が行くのは抜け穴だ。
「ロナルド君、ロナルド君」
「あ?」
「めちゃくちゃ見えるようになってきた。ってことは、君は見えないんじゃないのか」
「まあな」
「まあな!?」
「でけえ声出すな」
バレたらどうする。
そう続けるために振り返った瞬間。
どむん!! と、全力のジョンに吹っ飛ばされた。
「が、っぐ!?」
「ヌヌン!」
「いい! あいつは!?」
ダサくひっくり返るのだけはなんとか阻止できたぜ。まあどうせ、書くときゃ華麗に受け止めたことにするんだが。
謝ってくる腹で受け止めたジョン、のあたりを見る。が、正直薄ぼんやりと丸いかたちが認識できる程度だ。当然、距離を取らされたあいつ――ドラルクが、どうなったかどうかなんか把握できやしねえ。使い魔である、ジョンの視界が頼りになる。
空き家問題、ってのはどこの街でも深刻だ。
街灯がなくたって、家から漏れる灯りがあれば、多少は人間だって行動できる。それさえも無くなっちまうような、闇。
「……、」
ドラルクはなにも言わねえ。
っつうよりか、言えねえ、んだろう。
あれは死んでいる間、意識がねえ。とはいえ、俺が見ている範囲ではだが、まだ今日は死んでねえはずである。殺されていようがいまいが、不用意な発言ができねえ状況にある、っつうのは変わらねえ、ってことだ。
ジョンが袖をついと引く。答える代わりに、ジョンを抱え直した。
相変わらず、俺の視界は真っ暗闇だが。
バカみてえに鋭い殺気は、もう隠れるつもりがねえらしい。
「――よお、吸血鬼。お望みの色じゃなくて悪かったな」
無言かよ。
兄貴と会ってんなら、俺の色には見覚えがあるはずだ。ドラルクも『見える』とかほざいてたから、それを認識してねえはずもない。
さ・て。
ちょいと困ったことがある。
向こうが反応してくれねえと、こっちも攻撃のしようがねえ。
なにせ、見えやしねえんだからよ。ジョンにスポッターを任せてスナイパーごっこするには、殺気があまりに近すぎる。一発でビンゴを当てたことが幸運なのか、はたまた不運なのか。いまんとこ、不幸が七割。
「(……肩に)」
ささやくと、ジョンは無言で腕から這い出て、俺の肩によじ登ってくれた。
左手は銃へ。
右手は剣へ。
それぞれが、いつでも対応できるように。
命の気配が感じられねえ。
人の手、あるいは吸血鬼の手が入らねえ場所であるならば、もっと獣に近いものたちの縄張りになっておかしくねえはずだ。虫の羽音ひとつさえ無い、家のなきがらたちの群れ。そこに、じっとりとした殺意だけがある。
ああ、いやだ。俺、ホラーは得意じゃねえんだよ。吸血鬼だとわかっていなけりゃ、ちょっとビビっちまうかもしれん。
このまま睨み合うことに、おそらく意義はねえが。
明るいところに誘導、ってのも厳しい。俺がこの場を離れたら、向こうがこっちを追う理由がねえからだ。普通に見逃して終わっちまう。
「……よお、吸血鬼」
もう一度。
「お望みの色に、会わせてやろうか?」
もちろん、嘘だが。
「伝承を破る存在になりてえ。……そう思って、この街に来たんだろ」
クドラクは、クルースニクに敵わない。
ヒナは、あれでまあまあ有名だ。異例の特進ってだけじゃなく、自分がなんであるかを明らかにしている。クルースニクはここにいるぞと、喧伝してるって訳だ。
クルースニクが居る。
それがわかっていて、この街にクドラクが来る理由はひとつ。
伝承を破る存在になりたい。
無謀ではなく、蛮勇ではなく。
運命をひっくり返すだけの価値が、己にあると証明したい。
クソザコの代名詞たるドラルクにさえあるらしい、畏怖欲とかいうふざけたモノ。
ふざけるなよ。
「……なあ、来いよ。ついてこい。そうすりゃあ、お前の悲願は達成される」
ふざけるな。
そんなこと、このロナルド様が許すわけねえだろうが、なあ!?
ゆっくりと、距離をとる。
殺意が、距離を詰めてきているのを確認しつつ。
「ああ、いいぞ。……この俺が、見届けてやるさ。なんなら、外伝として書いてやろうか。ああ、ああ! そうしたら、お前はどれだけの畏怖を集めるんだ?」
いくら闇っつったって、ある一定の場所から突然光がなくなるってワケじゃねえ。じわり、じわり、すこしずつ。人間が作った光に、黒い獣が照らされる。
吸血鬼と狼男は、種にして近い。
だから、ドラルクみてえに特殊なルーツを持たない限り、連中が変ずるのは往々にして狼ばっかりだ。次点で蝙蝠だが、これは戦闘力が低いからな。
代わり映えがしねえせいで、書くときに困るんだよ、お前ら。
黒い獣――黒い狼。
クドラク。
黒い羊膜に包まれて生まれる夜の子。
「……よお、イケメン。新しい伝承に会えて嬉しいぜ」
『……、』
発声機能がねえのか?
ヒナんとこに連れてくのが、嘘だってバレてんのかな。
右手を剣から離して、ジョンを撫でる。意を汲んでくれたのか、音もなくジョンは俺の肩を離れていった。俺には見えねえが、闇の中に取り残されたドラルクのもとへ向かっていっただろう。
組合のオーダーは捕獲。
俺はフリーランスの退治人だ。
フリーランスってのは、信頼がねえと成り立たねえ。ここで俺がオーダーを無視してクドラクを殺しちまったら、まあ――年単位で干されでもしそうだが。そもそも俺は半年以上仕事をサボったこともある。別に組合経由じゃなきゃ仕事ができねえ、なんてヒヨッコじゃねえからよ。
クルースニクに挑む、蛮勇を犯したクドラクは、たどり着くことすらできなかった。
そういうストーリーラインにしてやる。
できるだろう、なあ。一発で、ワン公のちいせえ眉間を貫けばいい。
連れて行く、そういう建前がある。だからゆっくり狙いを定める暇はねえけど。
早撃ちは苦手じゃねえんだ。
できる。
本当に?
兄貴が取り逃がしたのに?
「――……ッ、」
できる。
兄貴にできなかったことが?
は、と吐息が漏れる。だめだ。警戒させるな。そう思えば思うほどに、呼吸が速く、短く、浅くなっていく。
獣は相変わらず、ひとことも言葉を発さない。
だが、その眼光は鋭く、俺を射抜いていた。
だめだ。
気圧されるな。
クドラクは、クルースニクによって斃される。
だが。
クルースニクにしか斃せない、わけではねえ!
浅く乱れちまうのなら、止めてしまえばいい。
狙うは一点のみ。
呼吸を止めた俺に、クドラクはすこしだけ疑うそぶりを見せた。
――今!
「ッ!!」
『――!?』
結論から言えば。
失敗した。
弾丸は当たったんだ。だが、クドラクがバカみてえに早かった。獣のスピードに、吸血鬼としての高速移動が合わさっているんだろうよ。蹴り飛ばされた地面が抉れているのが、うっすらとだが確認できる。
俺がブチ込んだのは銀の弾丸。だから、ダメージにはなっている。だが、だがだ! 今は斃せなきゃ、意味がねえってのに。
「く……、」
契約とまではいかねえが、騙したことには変わりない。
明確な殺意。
こちらが、兄貴のように見逃されることはなくなった。
俺とクドラクの、どちらかの息が止まるまで――殺し合いは続く。
爪や牙にかかれば、俺なんかひとたまりもないだろう。リボルバーで撃ち出す、貴重な銀の弾丸。本来は牽制になんか使いたくねえが、背に腹は変えられねえ。どうせ経費で落とすんだから、存分にやってやろう。
問題は、リロードの一瞬だ。
リボルバーに弾を込めるよりも、オートマチックに持ち換えた方が早い。だがそれも、そっちの弾が切れるまでだ。両方ともからっけつになっちまえば、あとは隙が二倍になるだけ。
だから、可能ならば弾を当てる。
ギリギリまで狙え。
掠りでもすりゃあ御の字だ。
やっぱりっつうか、当てること自体はできるんだよな。
だが、止まらねえ。向こうも、痛みを無視して無理矢理動いていやがるんだ。おそらく、止まったら俺がリロードするってわかってるんだろうな。
カチン、と。
オートマチックがへたれた声を上げる。
「――ッ!」
『!! ……!?』
――あ。
ちょっと、もう、だめかもしれん、と思った。
けれど。
存在をすっかり忘れていた、あれが。
見覚えのある竜の爪が、眼前に迫っていた獣を薙いだ。
「――ド、」
『いいから、早く弾を!!』
「ッ!」
言葉を理解するよりも先に、身体が動いていた。オートマチックのマガジンを入れ換えてから、リボルバーにも弾を込める。
その間にも、竜と獣が鍔迫り合いを繰り広げていた。
圧倒的に、デカブツであるドラルクのほうが間合いは広い。ちょこまかと逃げ回る獣を、追いやるようにして爪を振り回している。
「どけ!」
返事はねえ。だが、ドラルクは翼を思いっきりはためかせて、宙に浮く。風圧に慣れない獣は、怯むような動きをした。
その僅かな隙を狙う。
獣の右の肩に、銀の弾丸が喰い込んだ。
『当たった!』
「喜ぶな!」
心臓でも眉間でもねえんだ、これで終わりじゃねえんだぞ。
獣は金切り声をあげた。終わりじゃあねえが、あのすばしっこい動きは制限されるはずだ。そうであってくれよ、なあ!
獣がふらふらとよろめいて――それから、地面を強く踏み締める。鋭い爪が地面を抉り、ぎゃり、と嫌な音を立てた。
睨みあう。
クドラクのほうだって、滅多矢鱈に飛び回ってたんだ。肩へのダメージもあるんだろう、荒く息を吐いている。
だが、俺も似たようなものだ。
ギリギリまでタイミングを測っていたらしい、ドラルクにはまだスタミナがありそうだが。しかし元が弱体化しまくったクソザコだから、こいつをアテにはできねえ。
そんな膠着状態に、またも闖入者がある。
――うつくしい、白馬だった。
ひとつだけ、たてがみのうちにぴんと跳ねた房がある。それがまるで、ユニコーンのようにも思わせるような、そんなうつくしい、白馬。
呟く。
「――だ、めだ……」
彼女が、負けることはないのだろう。
それでも。
「だめ、だ。……だめだ」
傷つくことがないわけでは、ない。
「ダメだ――ヒナ!」
俺の呼びかけに応えるように、彼女がこちらを見遣る。
それについ、油断しちまった。
あいつはドガ、とその後ろ足で、俺のことを蹴り飛ばしたのだ。ノーガードだったせいで、俺はまっすぐドラルクに向かって吹っ飛ばされる。強かに背中を鱗へ打ち付け、肺の空気が抜けた。かってえんだよバカ、なんでこういう時に塵にならねえんだ。
鼻先でドラルクが俺をつつく。大丈夫だ、と声をかけながらその鼻先を押しやろうとするが、衝撃のせいで撫でたみてえになっちまった。
俺のことなんかどうでもいい。
もう一度、彼女のほうへ視線を向ける。
結末がたとえわかっているのだとしても。
目を逸らしてはならねえと、俺もドラルクも、思っていた。
□■□■□
――私の仕事なんて、ほとんどあってないようなものだ。
ロナルドの銃。ドラルクの爪。
それらは私の蹄なんかより、よほど強いだろう。
探し求めた私の運命は、据え膳として出来上がっていた。
『――、』
黒い獣は、己の負けを悟ってもなお、私を睨みつけることはやめないようだ。ささやかだけれど、それはたしかに、最後の抵抗である。
運命に抗おうという意志を持つ、敬意を払うべきもの。
だから、私は嘶く。
決着は一瞬。
獣は、必死に回避しようとしたのだろう。がく、と脚が揺れて、けれど実際に動くことはできなかった。獣を視界に捉えたまま一気に近付く。
後ろ脚で、獣の頭蓋を蹴り上げるだけ。
ゴガッ!! という、鈍い音が響いた。そのあとには、獣が倒れ込む音――ではなく。さらさらと、静かに塵が舞う。
ただ、これだけ。
私は、ただ、これだけのために。
この一瞬のために――生きてきたのだ。
「(――……、なあ)」
「?」
あっけない決着に、見惚れているときだった。
私に背を預けていたロナルド君が、ひどく震えた声を出す。いままでに聞いたことがないような、か細い声。
「(……あれは――負けないんだよな。クドラクを殺す、まで)」
『(……うん? まあ、そうなるかな)』
「(……なら……)」
なら、と。
震える声で、彼は言う。
「(……なら、……クドラクを殺した、そのあとは?)」
『ッ!?』
凛と立っていた白馬の影がゆらめいて、赤毛の少女に戻っていく。
彼女は――ヒナイチ君のひとみは、なにも映していなかった。ぐらり、とその少女が傾ぐ。このままではまっすぐに、塵の海へと倒れ込むだろう。
けれど。
私が呼びかけるよりも速く、ロナルド君が動いていた。スライディングしながら、その身をクッションにして受け止めている。
『ロ……ナルドくん、』
「いや、……いや! 生きてる。気絶してるだけみてえだ」
『よ、よかったぁ……』
へなへなと力が抜けて、一緒に変身も解除されていた。大丈夫か、と慌てるジョンを宥めつつ、ふらふらと彼らのもとへ向かう。
ヒナイチ君を横抱きに抱え直して、ゆっくりと私に振り返る彼は、まるで迷子の子どもみたいに不安げだ。そんな彼ごと、ふたりを抱きしめる。
「……大丈夫。大丈夫だよ。呼吸も穏やかだし、きっとヒナイチ君は眠っているだけさ。だから、一緒に帰ろう。まずはマスターに報告だ、そうだろう?」
「……ッ」
彼がなにに怯えているのか。
それはきっと、彼女がこれまでに捻じ曲げた、運命の揺り戻しだ。
クドラクを斃すまで、クルースニクは負けない。
負けることがあってはならない、そういうことになっている。
だけど、あくまでもそれは斃すまで、なのだ。
それ以降の彼女を、天は見放す。
ならば。
「大丈夫だよ」
天がもう、彼女を守らないと言うのなら。
「私たちが守ればいい。ね、そうだろう?」
「――……ッ、」
彼はぎり、と歯軋りをして、それからゆっくり頷いた。
「うん。……君も疲れているだろう。私、もう一回変身するから、背にお乗りよ。血液パック飲むからちょっと待ってね」
「……ん、」
「!」
ふたりから腕を離して、懐のパックを取り出す。ロナルド君の腕のなかで、かすかにヒナイチ君が身動ぎをした。けれど、意識を取り戻したわけではないみたい。落胆した様子で、彼はヒナイチ君の呼吸を確かめている。
『おいで』
「ああ……、」
彼のステップになるよう、腕をちょっと無理な方向へ伸ばす。ゆっくりと立ち上がるロナルド君には、やはり疲労の色が濃い。それでもただの一歩だけふらついたら、あとはしっかりとこちらに踏み出すのだから大したものだよ。
英雄の最期は語られない。
悪い敵を倒しました、めでたしめでたし。お話はそこでお仕舞い――なんて、現実はそうならないのだからね。
でも、だけどだ。
これでようやく、彼女は自由になれる。
それも、突然放り出されるわけじゃない。だって私も、ロナルド君もいるんだぞ。昼間なら彼が、夜なら私が、一緒になんだってできるさ。ジョンだって、彼女の仲間――吸対たちも、退治人たちも。彼女を、ヒナイチ君として見ている。
英雄ではなく、ただひとりの少女。ちょっぴり食い意地が張っていて、とても真面目で、本当はかわいいものが好きな、女の子。
我々は、そんな彼女の友人である。
「ぬぐあああッ!! ぐあ、う……ッ」
「どーしたどーした。そのまんまじゃぶっ飛んじまうぜ?」
「う、うぐーっ! くそ、くそ。クッキぃいい……!!」
「はいどーん」
「あー!!!???」
「本当に情け容赦がないな、君は」
画面外にぶっ飛ばされていった、ヒナイチ君のキャラクター。クッキーを賭けた、彼女にとってはとても大事な勝負だ。私からしたら、クッキーなんていくらでも焼いてあげるんだし、そんなに絶望しなくてもいいんだけどなァ……。
勝者たるロナルド君が、優雅に脚を組む。よだれを垂らして、キラキラと目を輝かせているヒナイチ君ににやりと笑いかけて、賞品を口に含んだ。ゆっくりと咀嚼して、それから私を睨む。へ?
「ん。……おい」
「うん?」
「これ、ヒナ用だろ。甘い」
「あれ? 間違えたか。私としたことが」
ンフ。
もちろん、私は間違えてなんかいない。
これは彼の方便だ。ヒナイチ君はクッキーに夢中で私なんかアウトオブ眼中なので、了承の意を込めてロナルド君へとウインクをする。彼もまた、笑みを見せた。
「ん?」
「ロナルド君には甘すぎるよな。取ってくるから待っておくれ」
「いや、いいよ。ヒナ」
「んん?」
口開けろ。そう言うロナルド君に、ヒナイチ君はあまりにも素直に従った。彼の呼び名通り、さながら雛のようだ。少女の大きな口に、青年がクッキーを放り込む。
「ほむ!?」
「食え。残りもやる」
「はむ、ふむう!!」
「レディが口をいっぱいにして喋るんじゃありません」
軽く叱りつけるように、ぺそっと彼女の額に手を当てた。もちろん、レディの顔を本気で殴るつもりもなければ、そもそも今日は吸血していない。そんなことをしたら、ロナルド君の折檻を受けるより先に、反作用で砂になるだろう。
そしてもちろん、私のそんな接触なんか、彼女には衝撃のひとつも与えない。けれど彼女はきゅっと眉を寄せて、しっかりと咀嚼してからはにかんだ。
「うむ。……ありがとう!」
「おー」
はじめて会ったあの日より、やわらかくなった笑顔。それが運命からの解放によるものなのか、私の城に慣れてくれたからなのかはわからないけれど。
クッキーをたらふく食べて、ゲームをして。疲れてしまったのか、やがて彼女は眠りについた。彼女のために用意した部屋へロナルド君が運ぶ。少女らしい装いの、天蓋のベッド。ちょっと買うの恥ずかしかったけどね!
くう、くうと寝息を立てる少女。腕を組み、部屋の入り口からそれを眺めるロナルド君は、兄というよりは親のような顔をしている。
隣に立っている私が見惚れるような、やさしい微笑み。
「(……、よかったね)」
「(……ん? ああ、……そうだな)」
いまのところ、であるけれど。
やはり、揺り戻し自体は来ているらしい。それでも、命に関わるようなものはまだ。最近ちょっとドジっ娘属性狙ってる? というようなくらいの、かわいらしいものに留まっているらしい。吸対と退治人の職場は同じようで違うから、ロナルド君が護衛みたいなことをすることはあまりないのだという。
でも。
彼女を気にかけているのは、ロナルド君だけではない。
だから、大丈夫。
というわけで。
私もね、いくら紳士とはいえだ。溜まるものはあるんだよな。それもさあ、捜索中ずっと一緒に寝てたんだぞ。一回も! なんと一回も、私は手を出していない。これ、ちょっとめちゃくちゃ褒めてもらっていいと思うんだよ。
そっとロナルド君の腰に手を回す。くふ、といつもの笑い声がして、深海のようなひとみがこちらを捉えた。なんだよ、という声音が甘い。ああ、彼もちゃんと、恋人モードになってくれているみたいだ。
応えずに、彼の顔じゅうにキスをする。拒絶がないから、私も調子に乗ってしまうのだ。見つめあって、さあくちびるを、という時だった。
「ん……ぅ、」
「「!!」」
まあ、うん。
ほら、やっぱりさ、私も彼も、事件解決で浮かれていたよ。彼に殺さない程度の力で押し退けられて、慌ててヒナイチ君の部屋を出る。
「起きてねえ、……よな?」
「た、ぶん。……起きてても、あの子はそういうことを揶揄ったりしないだろうけど、……いや、すごく下手に気を遣われそうだ」
「……、……」
うーん、もうやめようになっちゃうかなあ。そう思いながらため息をつくと、視界にロナルド君の手が映り込む。それは私の頬を引き寄せて、彼のくちびると私のそれをくっつけた。
まだヒナイチ君の部屋の前だからだろう、触れるだけの、やさしいキス。
「……、ロナルド君の部屋、行こっか」
「……ぉぅ」
「声ちっさ」
赤く染まる頬に、はやく齧りつきたいものだ。
モノクロームの運命たち

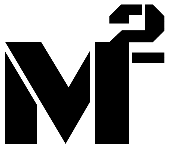
コメント
ロ様が他人の気配のある中で恋人モードになれるようになったのが、読んでいて最高に幸せな気持ちになりました!
ありがとうございます!
ちょっとずつ進展しているのに気付いていただけて幸いです🙌